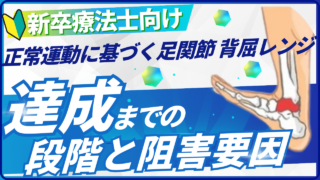
「新卒両報士向け ROM講座」の2回目として、『立ち上がり時の足関節のレンジ」に関して掘り下げていこうと思います。
・車椅子からベッド・ベッドから車椅子
・車椅子からトイレ・トイレから車椅子
といった所謂トランスファーの移乗介助を想定して、トランスファー時の問題を「ROM:関節可動域」の側面で理解する試みです。
トランスファーの目標
トランスファーの目標は患者と療法士で分けられると思います。
・患者側:
トランスファーの自立が達成できること
・療法士側:
トランスファーの全ての要素が理解できており、各段階で必要なROMが今どのレベルにあるかを把握していること
トランスファーの要素分解・ROMは初歩的段階
前回の動画では、新人療法士の方が理解しやすいよう、ベッドから車椅子に移乗する際のトランスファー・動作を要素分解することを提案しました。
①起き上がる→必要な各関節の可動性
②座る→必要な各関節の可動性
③立つ→必要な各関節の可動性
④方向を変える→必要な各関節の可動性
⑤座って行く→必要な各関節の可動性
①~⑤が達成できて、初めてトランスファー完了となる訳ですが、今回着目している「立ち上がり動作のROM」というのは、初歩的なステップの位置づけになります。
上記の①~⑤で、「③の立つ」というのを抜き出して、それに必要な動作を下から順番に書き換えるとこのようになります。
トランスファー完了
↑
着座
↑
お尻の方向転換
↑
立ち上がり
↑
ROM(関節可動性)
今回の動画で解説している「ROM(関節可動性)」は、まだ立ち上がり動作にすら達していない、前段階の話である事を理解しておいて下さい。
ROMには解剖・運動学の知識が必要だが…
ROMを理解するためには、解剖学や運動学の知識が必須ですが、専門学校で学ばれ、国家試験をパスした皆さんは既にこの領域を理解しているはずです。
・骨や筋肉、皮膚、筋膜の名称や位置
・筋肉が収縮すると関節運動が起こるメカニズム
・筋肉の起始停止 など…
こうした解剖学・運動学の中身は教科書に書いてあるし、皆さんの頭にも入ってることでしょう。僕もそうでした。
しかし、僕が新卒療法士として臨床に出始めた頃は、そうした学問的知識が備わっているにも関わらず、目の前の患者さんが立てない理由が分かりませんでした。
解剖学・運動学の知識を持ち合わせているにも関わらず、担当する患者さんが立ち上がることができない背景がさっぱり理解できない。
半年、1年ぐらいずっと悩みました。
悩んだ結果判明したのは、「正常運動」の知識が欠如しているということでした。
正常運動とは
正常運動とは一体なにか。
端的に言えば、数百人の母数データに基づいた、一般的な動きをパターン化したものです。
立ち上がる時のパターンは大体こういう風になっていて、関節の角度はこの位で、その際の筋活動はこう…というのを教えてくれる知識が正常運動です。
30年程前、僕はこのような「正常運動」を学校で習った記憶はありません。
今でこそ、石井慎一郎先生らが研究・発表されている「動作分析・バイオメカニクスに基づく運動学」など、筋電図から得られる情報や筋肉の作用に関節運動を組み合わせる理論がありますが、僕の時代にはこうした学問体系は確立されていませんでした。
特に僕は作業療法士という立場であり、理学療法士ではないので、動作についてはほぼ習ってきていません。
とは言え、「正常運動」の知識がないと、臨床におけるトランファーでROMの発想には至りません。
新卒療法士の方に改めてお伝えしたいのは、この動画は、トランスファーにおける達成度合いの「基礎中の基礎であるROMから講義をスタートしている」という点です。
「正常運動」ならびに「達成度合いの段階」を理解しないと、患者さんに対して立ち上がる動作をどう練習するか立案し、自立に導くかの筋道が見えてこないのです。
立ち上がりのROM
さてここから本題の「立ち上がりのROM」です。
結論は、「立ち上がるためには、足関節の背屈方向のレンジ・背屈方向のROMが十分に確保されていないければ、立ち上がることはできない」です。
これは文字情報で見るよりも、実際の動画を見て貰った方が早いです。
動画7:29~ で解説していますので、概要欄のチャプターをクリックしてご覧ください。
足関節の問題は骨盤運動にある
足関節の問題が、実は骨盤運動にある場合があります。
脳卒中片麻痺の方が身体を起こす際、骨盤帯の筋肉が必要ですが、大体のケースで、片麻痺の方の麻痺側の脚は外側に流れてしまっています。
麻痺脚が外に流れているという事は、股関節の周りの筋肉は外に引っ張られているということです。
加えて、身体は非麻痺側に傾いています。
すると、骨盤は後ろに引けて、ねじれている状態になります。
骨盤がねじれた状態で足部だけ治そうとしても底屈方向には動きません。
筋肉や靭帯で制限がかけられてしまいますが、具体的に何が制限となり、阻害要因となっているかは、是非ご自身でも調べてみて下さい。
足関節が動かないから骨盤が起こせない訳ですが、足関節のレンジの問題は、片麻痺の方の"初期状況"を考慮すると「骨盤が後ろに虚脱して落っこちている」と想定できます。
骨盤をきちんち立ち上げて、真っすぐに座れる状態にしてあげると、結果的には足関節のレンジも取れるケースがあります。
上記で、僕が「初期状況」と断りを付けたのは、脳卒中の初期段階が1-2ヶ月続けば、短縮や痙縮は発生するし、余計な筋の硬さによって底屈のレンジは落ちるからです。
筋肉の硬さがそもそも邪魔をしている場合も当然ありますが、骨盤が崩れていることが脳卒中の急性期の段階で生じているので、これが多少でも緩和できたら、筋肉の硬さはある程度は防ぐことができると考えられます。
教科書には全く載っていない
今日僕が動画でご紹介した一連の情報は、教科書には全く載っていません。
一般的な教科書に示されているのは「トランスファーでは、車椅子を非麻痺側にベッドに対して40-45度傾ける」といった内容です。
臨床30年以上の経験を経た今思うのは、「別に45度じゃなくていい」という事です。
教科書の内容は勿論重要ですが、何でもかんでも鵜呑みにせず、臨床では自分の頭で考えるようにしてみて下さい。
正常運動を脳卒中片麻痺者に適用するのは間違い
「立ち上がり動作で必要な関節可動性」を理解し達成するには、「正常運動」の知識も不可欠ですが、「正常運動」をそのまま脳卒中片麻痺の患者さんに適用することは間違いです。
今目の前の人が困っているのは、「正常運動」の知識を使ったら「ここが問題なんだ!」というのを発見し、それに対して解決策を探っていくのが重要です。
次回は、立ち上がるためには具体的に何が必要なのかについて解説していく予定です。
動画内容・チャプター
0:36 ROM達成目標・達成度合い
1:04 トランスファー:患者側の達成目標と療法士側の達成目標
1:26 ROMの立ち位置・レベル感
1:34 立ち上がりのROM:達成までの段階
2:22 ROMを知るには解剖・運動学の知識が必須
4:43 国試をパスしても患者が立てない理由が分からない
5:21 正常運動
6:03 バイオメカニクス・生体力学
6:40 正常運動を知らないとROMの発想は生まれない
7:34 立ち上がるための足関節の背屈レンジ・背屈方向のROM
8:21 車椅子で身体を起こした時の足関節の背屈角度
9:09 股関節が動くためには足関節の背屈が無ければ腰を起こせない
10:24 まずは足関節のレンジをきちんと確認する
10:45 足関節の問題は骨盤運動が原因の場合も
11:14 片麻痺者の麻痺側脚は外に流れている
11:57 骨盤が後ろに引けている状態
12:09 骨盤がねじれた状態で足部だけ治そうとしても底屈方向には動かない
13:07 脳卒中初期の段階
14:05 立ち上がるためには身体を起こして足底に荷重
14:32 今の話は教科書には全く載っていない
14:46 トランスファートは非麻痺側に45度ってホント!?
16:16 教科書の内容を鵜呑みにしてはいけない
16:40 正常運動を脳卒中片麻痺者に適用するのは間違い