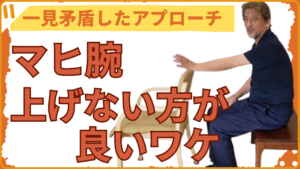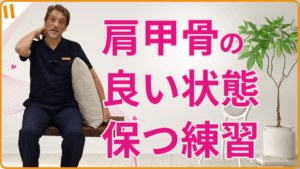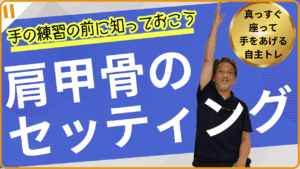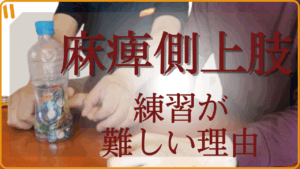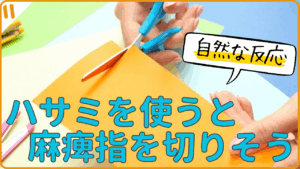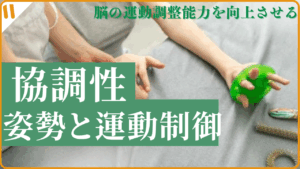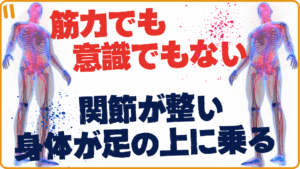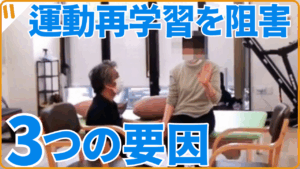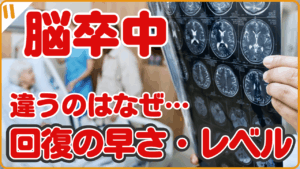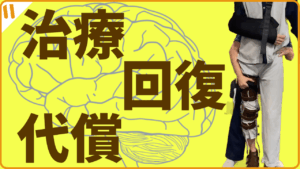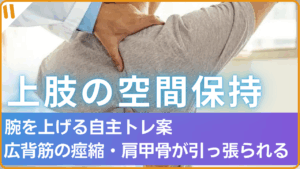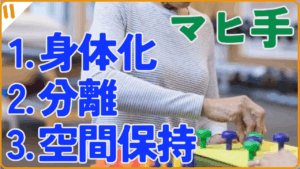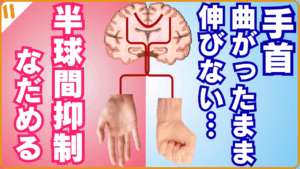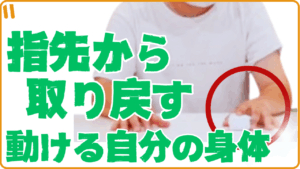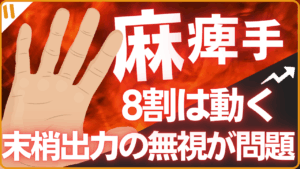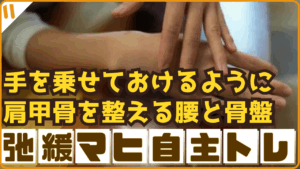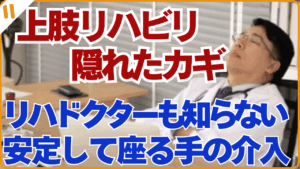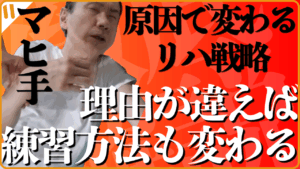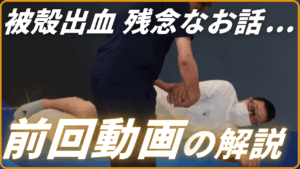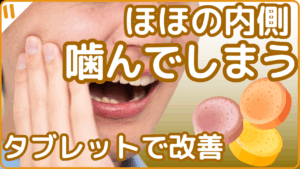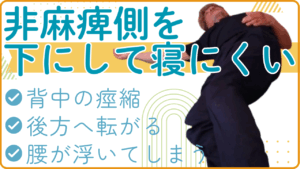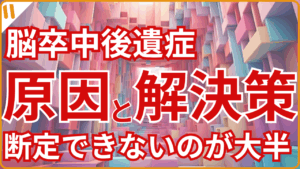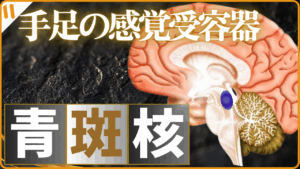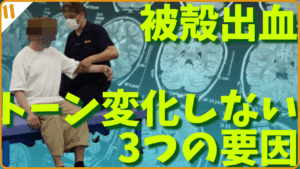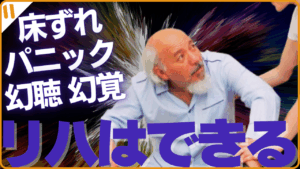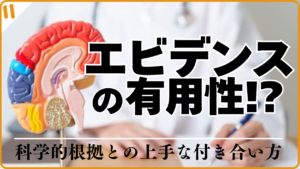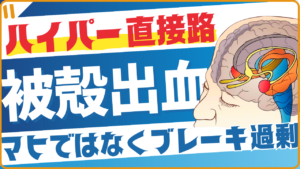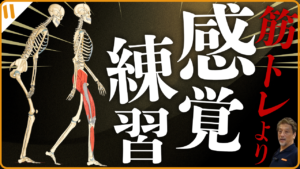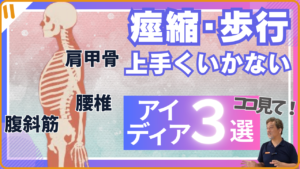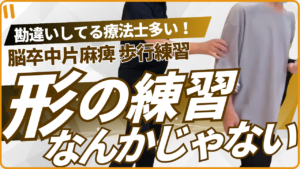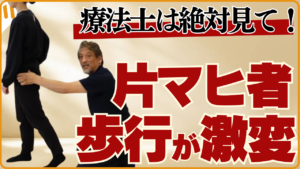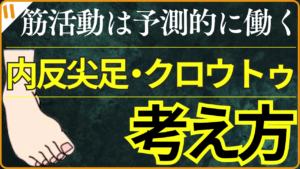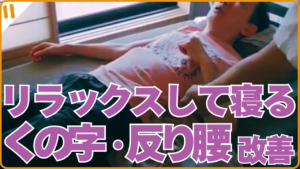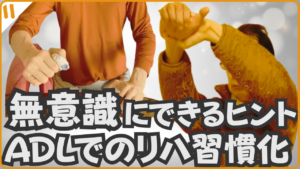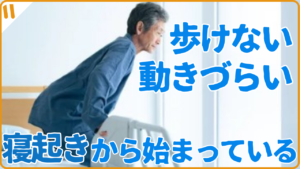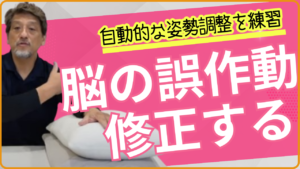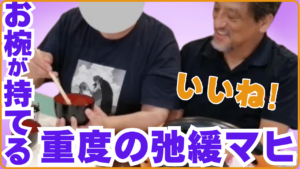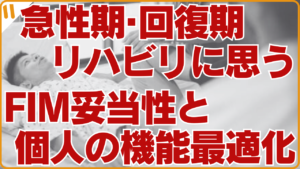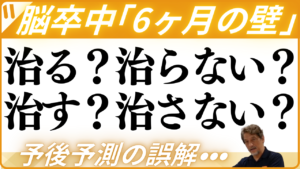【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する⑬】麻痺手自主トレ3・麻痺手を挙げようとしない方が良い理由・手を宙に上げようとするのではなく乗せてキープする
【ポイント・まとめ】 ★麻痺手の随意性を引き出す自主トレ:3:32 ~ ・脳卒中片麻痺者の特性: 手足が動かないのは、脳からの興奮がうまく伝わらず、別の方向に興奮がいってしまうことが原因・リハビリの一つの考え方として、「 […]
【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する⑫】麻痺手自主トレ2・肩甲骨の良い状態を保つ練習
【ポイント・まとめ】 ★ 4:39 肩甲骨の良い位置をキープする自主トレ ・麻痺側上肢を空間で保持するための前段階の練習・筋トレの前に必要な「筋肉が働ける条件づくり(セッティング)」がテーマ・肩甲骨と上腕骨の関係を良い位 […]
【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する⑪】麻痺手自主トレ1・麻痺側上肢の練習をする前に押えよう!片麻痺で肩甲骨が問題になる理由と改善の自主トレ・肩甲骨がどこにあるかを意識
【ポイント・まとめ】 ・麻痺側上肢の練習に入る前に、肩甲骨のセッティングをする・脳卒中片麻痺の方は、棘上筋(きょくじょうきん)や僧帽筋(そうぼうきん)が働かず、肩甲骨が正常に働かない事が多い・先ずは理論を押さえた上で、実 […]
【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する⑩】 麻痺手自主トレ考え方・麻痺側上肢の練習は難しい・空間保持ができないと、指や手の動きを出すのは困難
【ポイント・まとめ】 ・麻痺手(麻痺側上肢)のリハビリの難しい理由の一つは、「空間保持」ができないこと・手や腕が空中で安定している必要があるが、片麻痺の方には難しい・空間保持ができないと、指や手の動きを適切に練習すること […]
【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する⑨】弛緩性麻痺と痙性麻痺では練習方法が違う・混在している側面も・麻痺側上肢へのアプローチ
【ポイント・まとめ】 ・弛緩性麻痺:手足がダラーンと動かない状態・初期の段階で多く見られる・痙性麻痺:多少は動くが完全に自由ではなく、動こうとすると硬直したり、力が入ったりする ・臨床的に、両者は必ず混在している‐発症初 […]
【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する⑧】ハサミを使うと押さえている麻痺指を切りそう・道具特有の感覚情報を受け取る・uni.coさんからのコメントにお答え
【ゆにこさんからのコメント】 いつも有益なお話をありがとうございます 左麻痺、脳出血発症5年になりますハサミを使う時、麻痺手でモノを持つことになりますが、親指以外はモノの裏側にいき、目視できなくなりますよね 。そうなると […]
【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する⑦】歩行練習のためにテーブルの物を取る理由とは・協調性障害・筋の協調性・姿勢制御と運動制御
【結論】 ・脳卒中片麻痺のリハビリでは、「歩行が出来ないから歩行練習する」事だけが全てではない・歩行に繋がる筋や関節の協調性を再学習するには、姿勢制御や運動制御が『自動的に生じる』ようなアプローチが必要であり、その一つの […]
【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する⑥】安定性限界・支持性のお話
【まとめ・ポイント】 ・指示性とは、「支える力」のことで、単なる筋力ではない。・意識して練習してもなかなか身につかない。・支える=筋力だけではなく、全身のアライメントと姿勢制御が重要。 ・身体全体の重心が足裏の「安定性限 […]
【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する⑤】脳の働きに関わる3つの要素・脳はシステムとして働いている・できない動作を獲得するばかりが運動練習ではない
【まとめ・ポイント】 ・病気の特性を知ることが回復の可能性につながる・単なるあきらめではなく、正しい知識を持った上でリハビリのアプローチや考え方を変えることが大切 ・「動作練習=できないことを繰り返す」だけではない・“な […]
【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する④】運動再学習を邪魔する要因3選
【ポイント・まとめ】 ■前提・脳卒中発症の急性期~回復期初期を想定して解説・シナプス可塑性は誰にでもあり、再学習や回復は可能・ただし、脳卒中で脳細胞が壊死している場合、完全な回復は難しい・運動学習は可能だが限界があり、人 […]
【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する③】回復の早さやレベルが違うのはナゼ?学習の結果・早いうちからリハを始めても…実感としては変らない!?脳の可塑性・神経伝達物質
今日の動画では、脳卒中からの回復速度や程度が人それぞれ異なる理由について、脳の可塑性(かそせい)を踏まえて説明していきます。 シナプス・脳の可塑性(かそせい) 脳の可塑性とは、脳卒中などの病気になった後、脳が構造や機能を […]
【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する②】治癒・回復・代償の意味
今回の動画では、脳卒中が一体どういう病気なのか、そして、回復するとはどういう事なのかを考えていきたいと思います。 脊髄損傷 脊髄損傷というのがあります。脊髄というのは、脳から下にある、神経の束が通っている部位です。 脊髄 […]
【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する①】プロローグ・ 脳卒中とはどういう病気か・リハビリに対する誤解
今回の動画では、脳卒中とは一体どんな病気なのかを改めて考えていきたいと思います。潜在能力が残っている脳卒中片麻痺の方は多いはずですので、改善の可能性を見出していこうという試みです。 リハビリの基礎的な立ち位置 ①急性期: […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢⑨】空間保持・腕が上がらない→広背筋が痙縮で硬く肩甲骨が引っ張られる・自主トレ 11:52~
これまで「麻痺側上肢」にフォーカスを当て、①身体化 ②分離 ③空間保持と順番に講義を行ってきました。今回は最終回として、「③空間保持」について詳しく解説したいと思います。 今日の結論は、脳卒中片麻痺の方の麻痺側上肢がうま […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢⑧】分離運動:麻痺側上肢の回復段階・ブルンストロームステージ
前回の動画では、マヒ手を動かすための3つの達成目標として①身体化 ②分離 ③空間保持を取り上げました。そのうちの「②分離(分離運動)」について深掘りして考えてみたいと思います。 シグネ・ブルンストロ−ム著 「片麻痺の運動 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢⑦】動かないのはマヒの影響だけではない・マヒ手を動かすための3つの達成目標 ①身体化②分離 ③空間保持
今日は「マヒ手を動かすための3つの達成目標」について話します。動画冒頭では、法人化を見据えたトークイベント(8月17日・両国)の告知をしています。本編は 10:16 からスタートしますので、チャプターをクリックしてご覧く […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢⑥】8割以上の方の麻痺手は動くようになるの根拠とは・「手首が曲がったまま伸びません」というコメントにお答えします
先日「8割以上の方の巻き手は動くようになりますよ」という動画を投稿いたしました。その際、かず(kazu)さんという方から、「自分は手首が曲がったまま伸びません」というコメントを頂戴しました。 今回はこのコメントに回答する […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢⑤】介入場面全公開・マヒ指の練習から全身を調整する・被殻出血左片麻痺 ソムリエ石橋さん
今回は、脳出血・左片麻痺の石橋さんへの介入場面を全公開します。 石橋さんはレストランでソムリエとして復帰するためにリハビリに取り組んでおり、人差し指の練習を重点的に行っています。 「指が動く」と「体が整う」は密接な関係 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢④】弛緩性麻痺側上肢の復活を語り尽くす!マヒ手の8割は動けるようになる・末梢の出力を無視するのが問題
今日の動画では、麻痺側上肢の復活を語りつくします!結論は「8割以上の方のマヒ手は動く」という事です。 昔のように100%の動きには戻らないかもしれませんが、「動かない」と思っていた手が動き出す。今よりも改善する。僕が長年 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢③】弛緩性マヒ・肩甲骨の状態を整えるための腰と骨盤周りの練習・上肢の自主トレの要は姿勢です!
今日は、主に弛緩性マヒの方を対象とした、上肢自主トレをご紹介します。 マヒ手をテーブルに上げておくのが難しい方がメインの対象です。 最終目標は「手の随意性を高めること」ですが、前段階として、肩甲骨の状態を整えるための“腰 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢②】3つの要因 麻痺側上肢の潜在能力が発揮できない理由・病院で上肢に介入しない現状・廃用症候群
麻痺側上肢のポテンシャルを活かせない要因3つについて、急性期・回復期病院で積極的に上肢介入しない現状に触れつつ解説していこうと思います。 マヒ手は療法士が介入したからと言って治せるものではなく、改善こそ目指せるものの、何 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢①】あなたの手が上がらない理由は?身体構造から原因を探る・麻痺の部位が違うワケ
前回までお送りしてきた「被殻出血シリーズ」は一旦完了とし、今回からは「麻痺側上肢」について解説していこうと思います。 「マヒ」と一口に言っても原因や出現部位は人それぞれであり、原因要素に基づいてリハビリテーション戦略を策 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血⑧】前回介入場面の解説と残念なお話・運動主体感・遠心性コピー・身体所有感と自己と他者の区別
今日は、前回配信した40代男性 被殻出血 ソムリエの方に対する介入場面の詳しい解説をすると共に、皆さんに残念なお話をしようと思います。 いつもにも益して冒頭の前置きが長く、療法士向けの専門的な内容にも言及しますが、最後ま […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血⑦】介入場面を公開!手が動きそうな感覚・麻痺側上肢に介入する理由と実践方法
今日の動画では、麻痺側上肢に介入する動画をお届けしようと思います。 ソムリエの仕事に復帰 動画に登場頂くのは、被殻出血・左肩麻痺の若い男性で、ソムリエとして働いていらした方です。 リハビリでは、ソムリエに復帰するために必 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?口内編】顔面神経は同側支配・ラムネ飴を使った自主トレで改善・ほっぺたの内側を噛んでしまう・食べ物が残る
今日は被殻出血の後遺症として「口の中の問題」について解説していこうと思います。 「塩分チャージタブレット(ラムネのような飴)」を使った自主トレ方法の解説は 10:07 からスタートします。 タブレットを用いた自主トレ場面 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?回答編2】被殻出血・背中の筋の短縮と痙縮・健側を下にして横になりづらい:筋の硬さを解放する考え方
今回は「ヒロユキさん」から寄せられたご質問にお答えしながら、被殻出血の方における「背中の筋の短縮と痙縮」を中心に、筋の硬さを解放する方法について考察していきたいと思います。 脳卒中の後遺症・原因と解決法 脳卒中による後遺 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?回答編】バランス障害に対する寝返りの自主トレ・ワレンベルグ症候群・延髄外側症候群・脳卒中の後遺症は特定の原因や解決法がないケースが大半
48歳・男性・右片麻痺ワレンベルグ症候群のたかさんから寄せられたコメントにお答えする形で、脳卒中リハビリの発信に対する山田のスタンスを改めて述べたいと思います。 動画後半には、「バランス練習(寝返り動作)」のデモンストレ […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血⑥】青斑核とトーン改善・手足の感覚受容器を利用しノルアドレナリンで脳を覚醒させる
被殻出血の方がトーン変化(筋緊張の変化)を促すための仮説とアイディアとして、青斑核(せいはんかく)という脳の仕組みを説明しながら、 麻痺側手足の感覚受容器を刺激する自主トレをご紹介したいと思います。 痙性が強い方や低緊張 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血⑤】被殻出血の後遺症が重篤になる背景・筋緊張/トーンが変化しないのが問題
今日は、被殻出血の方で「トーンが変化しないのが問題」というお題で、動きづらさの背景を探っていこうと思います。 例によって、前置きや回り道が多いですが、結論は「トーン=筋緊張が変化しない事が動きづらさの背景にあり、脳機能の […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血④】褥瘡(じょくそう)の発生要因考察・厳しい状況でも初期のリハは実施可能:床ずれ・幻聴・幻覚・せん妄・混乱・パニック・急性期と回復期リハビリ
「Let's ケーススタディ」107ページに掲載している症例を再び取り上げ、被殻出血の方への介入のアイディアを探っていきます。 歩ける能力が残っているにも関わらず、急性期・回復期でリハビリが受けられない状態にあった方です […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血③】触られているのは分かるがどこを触られているのか分からない!感覚が問題・視床の体部位局在と運動の分解能
70代男性 左被殻出血・右片麻痺 失語症の方への介入もようをお届けします。 2025年4月29日に「リハビリ職人育成講座」にアップした『【新卒療法士向け ROM講座⑤】実践編:ROMの技術でどこまで改善できる?』の別場面 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血②】痙縮が問題・誤学習した歩行パターンを感覚を使って修正する・代償動作の修正介入
今日の動画では、「Let's ケーススタディ」に掲載している症例を取り上げ、誤学習した歩行パターンを感覚を使って修正する際の考え方などを解説してみようと思います。 右被殻出血・左片麻痺例 Let's ケーススタディ 症例 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?番外編4】EBMと民間療法:"確からしさ"があるものを安全に組み合わせる・堀尾法・ボバース・無資格者と有資格者
昨今の病院リハビリではEBM(エビデンス・ベースド・メディスン)を実施することが主流になっており、病院所属のPTやOTはEBSを重要視しつつ、ドクターの指示に従ったリハビリを提供するのがコンセンサスになっているようです。 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?番外編3】脳卒中エビデンス鵜呑みは危険!誰のためにどう利用する?脳機能は未だにナゾだらけ
今日は脳卒中の「エビデンス」について考えてみたいと思います。結論としては、科学的エビデンスを鵜呑みにせず、自分の中で根拠や裏付けとなるデータを判断できるようになる事が重要です。 CI療法と川平法 脳卒中のリハビリにはいく […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血①】マヒが原因ではない!被殻出血はブレーキを緩めるのが重要・基底核疾患・ハイパー直接路
これまでシリーズとしてお送りしてきた「片麻痺者が動けないのはなぜ?」では、自動的姿勢調整や伸展反応とバランスなどの考え方に基づき、椅子や平行棒などを利用して片足立ちする練習方法をご紹介してきました。 今日はからは「被殻出 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?⑩】ラクに歩く!最初は感覚の練習→筋肉を使う練習(14:56~)伸展反応とバランス=自動的に最適な位置に
シリーズ「片麻痺者が動けないのはなぜ?」第10回目として、今回は「片麻痺の方が自由に歩けない理由」を「伸展反応とバランス」という2つの側面に分けて解説しようと思います。 リハビリの在り方も2通りになる訳ですが、その練習が […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?⑨】療法士へのコメント返し:異常な運動連鎖からの解放を促す方法3選・1.腹斜筋 2.腰椎 3.肩甲骨
前回の動画「【片麻痺者が動けないのはなぜ?⑧】歩行練習を「形」の練習として捉えても無意味!」では、痙縮によって「異常な運動連鎖」が生じるということを解説しました。 痙縮により、腰椎が伸びるタイミングが狂ってしまったがゆえ […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?⑧】歩行練習を「形」の練習として捉えても無意味!異常な運動連鎖・ギックリ腰と片麻痺者の意外な関係JP
絶賛、ぎっくり腰継続中の山田です😭今日は、前回の「バランスのいい歩行練習のやり方・内反尖足とクロウトゥが出る原因」の続きとして、「異常な運動連鎖」について解説しながら、「歩行練習の考え方」について述べたいと思います。 前 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?番外編2】歩行の前に必ず〇〇を確認!バランスのいい歩行練習のやり方・内反尖足とクロウトゥが出る原因
今日は「バランスのいい歩行練習のやり方」という題目で、理学療法士の樫村さんにご協力頂き、脳卒中片麻痺者の方がどうすれば安定的でラクな歩行ができるかをデモンストレーションしていきたいと思います。 文字で読むよりも、実際の動 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?⑦】内反尖足とクロウトゥはバランスが原因・脳が損傷すると感覚入力・加工・出力に問題が生じる
今日の動画では「内反尖足・クロウトゥはバランスの悪さが原因」という主旨で、僕の30年以上にわたる臨床経験を踏まえた見解を述べたいと思います。 バランスの悪るさ→内反尖足・クロウトゥ ①バランスとは何か→予測的に動く②バラ […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?⑥】無意識の姿勢調整・頭部外傷のケースから考えるバランス練習
今日は2025年2月16日に山口県山口市で開催したセミナーで、対象者として参加頂いた「頭部外傷」の方について、下記テーマに沿って解説しながら概要をご報告したいと思います。 今日のテーマ ①姿勢は意識できない②作業記憶は容 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?⑤】障害は寝ている時から・“くの字と反り腰”の改善自主トレ・療法士が誤解しやすい点と対策
今日は「片麻痺者の問題は寝ている時からも起こっている」という視点から、Let's ケーススタディ 脳卒中リハビリテーションでも取り上げた「行動分析・寝返り」を解説していこうと思います。 Let's ケーススタディ 症例 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?番外編1】歯磨き習慣とリハビリ効果の意外な関係・意図的な動作練習よりADLでのリハビリ習慣化
今回は「片麻痺者が動けないのはなぜ?」シリーズの番外編として、「歯磨き習慣とリハビリ効果の意外な関係」について述べてみたいと思います。 日常生活を視野に入れた介入の考え方 僕の書籍「Let's ケーススタディ 脳卒中リハ […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?④】寝起きから始まる脳の誤作動・健側の肩甲骨の過使用・麻痺側の身体が存在しない感覚で動くのが当たり前になってしまう!?
今日のテーマは「脳の誤作動とイメージ」です。 結論は『本当に障害されている機能と残されているはずの機能をきちんと見極めましょう』ということです。見極めるためには「正常運動」の知識を持っておく事も大切です。 話の流れとして […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?③】「歩けない・動きづらい」は“寝起き”から始まっている!自分の身体を取り戻していないまま動作練習だけしてませんか?
今回も「Let's ケーススタディ 脳卒中リハビリテーション」の事例を取り上げ、「歩けない・動きづらい」は“寝起き”から始まっている!」について解説します。 Let's ケーススタディ 症例 p88 ◆p88 第3章:臨 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?②】脳の誤作動を修正・脳にアプローチをする方法
前回に引き続き、山田が上梓した「Let's ケーススタディ 脳卒中リハビリテーション」の事例を取り上げながら、「脳の誤作動を修正・脳にアプローチをする方法」について解説します。 Let's ケーススタディ 症例 p117 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?①】重度弛緩マヒと亜脱臼からお椀が持てるようになるまで
昨年からお送りしている「脳卒中の後遺症を理解する」シリーズの一環として、『片麻痺者が動けないのはナゼ?』というのを考えてみたいと思います。 第一回目は、山田が執筆した「Let's ケーススタディ 脳卒中リハビリテーション […]
【新年のご挨拶と2025のテーマ】今、当事者には何が求められているのか・理解と評価によって介入の方向性は大きく変わる
今回の動画は引き続き「脳卒中の後遺症」をテーマとし、「今、当事者には何が求められているのか」という切り口から、脳卒中リハビリの在り方を考えてみたいと思います。 療法士の分析・評価で介入方法は大きく変わる 論点を簡潔に述べ […]
【脳卒中の後遺症を理解する④】急性期・回復期・維持期で持っておきたい視点・FIM評価の妥当性と当事者個人の機能最適化
脳卒中の後遺症を理解するシリーズ4回目も、前回に引き続き、山田の考えを少し皆さんにシェアしますね。 とある病院での「臨床指導でのエピソード」をもとに、脳卒中発症後の急性期・回復期・維持期(生活期)で共通概念として持ってお […]
【脳卒中の後遺症を理解する③】脳部位の機能回復と代償による生活の自立・後遺障害を踏まえて前進する意識
今回は脳卒中後遺症を理解するシリーズの第3回目として、「脳部位の機能回復と代償による生活の自立」を考えてみたいと思います。 当事者が思い描く「脳の機能回復=治る」とは? 前回の動画でも触れましたが、脳卒中片麻痺の方が考え […]
【脳卒中の後遺症を理解する②】治る/治らない? VS 治す/治さない?・予後予測の誤解・「6ヶ月の壁」の論拠と意味
本日の動画では、脳卒中は「治る?治らない? VS 治す?治さない?」というテーマを掲げ、「6か月の壁」や「予後予測」にも触れつつ、言葉の定義や誤解を考えてみたいと思います。 テーマ3つ ①神経細胞と連絡→ここが損傷:脳細 […]
【脳卒中の後遺症を理解する①】脳卒中片麻痺から完全回復したと言ってる人は自分と何が違うのか・発症の経過と障害の違い
本日から5回にわたり「脳卒中の後遺症を理解するシリーズ」として、脳卒中の病態や後遺症をどう理解すれば良いのかという概論をお伝えしていこうと思います。 解説テーマ(予定) 第1回:発症からの経過と障害の違い(本当に障害され […]