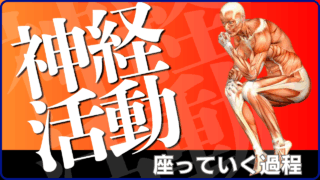
今日は「座っていく過程で起こる神経活動」について説明していこうと思います。
座っていく過程で方向転換をしたりといった動作を、どういうレベルで理解をするかというのが論点です。
結論・ポイント
・筋活動のパターンは神経活動によって変化する
・座っていく時には代償的な感覚に置き換えるのが有効な練習方法のひとつになる
神経活動とは
様々な要素があるので、1つにはまとめられないのですが、総じて言えることは「神経活動が起こっているから筋活動のパターンが変えられる」という事です。
筋活動パターンの変化は神経活動。
そして、神経活動は脳の活動です。
脳から発せられる神経のインパルスが、末端の筋肉に届くことまで含めれば、脳幹や小脳、脊髄、抹消神経など、全体の神経系システムという中で起こる何かしらの要因が筋活動のパターンを変えるきっかけになります。
つまり筋肉の活動量を変えるわけです。
認知活動
ヒトには感覚・知覚・認知という情報処理の段階があります。
それぞれのキーワードを検索すると、AIはこう答えてくれます。
①感覚:
外部からの刺激を感覚器が受け取り、神経系を介して脳に情報が送られる、最も基本的な情報処理の段階。
②知覚:
感覚によって脳に送られた情報を、過去の経験などに基づいて解釈し、特定の性質(色、形、重さ、大きさなど)を判断する段階。
③認知:
知覚された情報をさらに統合・解釈し、それが何であるか、どのように行動するかを判断する、より高次の精神活動全般。
①感覚
感覚は末端の器械受容器、網膜に映る像、耳の鼓膜が揺れる現象などがあります。
舌の先に何か化学物質が付いて、鼻の奥の鼻腔に何かしらの匂いが入ってくる…
様々な末端からの刺激が感覚です。
②知覚
感覚が神経を介して、脊髄を通って視床まで届きます。
視床まで来た感覚のことを知覚と言います。
視床にはほぼ全ての感覚が入ると言われています。
知覚というのは感覚に意味がある状態です。
以前は「嗅覚」は入っていかないされていましたが、最近の研究では、嗅覚の一部も視床に入っていくとされているようです。
③認知
知覚が一次感覚野から二次感覚野、三次感覚野に下っていく間に、認知が起こります。
「冷たいからこことの素材の差があるんだ」という意味が生じます。
「冷たい」という単純な知覚ではなく、その冷たさの意味、これを持って認知と言います。
お尻を向けるのには認知機能が必要(前回の復習)
前回お話ししたこのお尻を向けるのには「認知機能が必要ですよとお話しました。
認知機能も神経活動です。
自分のお尻って目で見えないので、自身の身体位置が分かっていないとお尻を向ける動作はできません。
この筋活動のパターンが変えられるのは、先にも言及したように、神経活動が起こっているからです。
代償的な動作
「振り向く」という動作をホワイトボードに書いてみました。
「振り向く」という動作で、お尻を方向転換する際、代償的な動作で賄えることができます。
代償的に、先に目で反対側を見ると、身体はそれに伴って動きます。
目は同眼神経によって、調整されます。
同眼神経と前庭神経核は密切な関係があります。
前庭神経核は耳の三半規管や耳石から出る前庭情報、前庭感覚を最初に受け取る脳幹の中にある神経核です。
前庭神経の役割:転倒時に抗重力伸展活動を生じさせる
前庭神経の役割は、転倒しそうな時に、抗重力伸展活動を生じさせることです。
転倒する時、身体にぎゅっと力が入ります。
頭を怪我しないように防御するためです。
脳はとても大切な臓器なので、頭を打たないような抗重力伸展活動によって、身体全体の力がギゅっと入るのが、前庭神経核の重要なファクターです。
頭が安定性限界を超える
この背景には、安定性限界を超えることがあげられます。
頭部の位置の変化によって三半規管・耳石の感覚情報は前庭神経核に行きます。
前庭神経核により、頭の位置が安定性限界を超えると、身体はギュっと力入れて元に
戻せという命令を出します。
この機能を使うと、目を先に動かせば、身体はその方向に向かって動く事になります。
代償手段だが方向を変える練習として有用
上記のアイディアは、あくまでも代償手段です。
「代償手段」と理解しつつ、敢えて、方向転換の練習に活用するというのを、僕は臨床でよく行います。
この練習では、お尻がちゃんと方向転換できた後に、「膝を緩めて」と声掛けをするにも注意が必要です。
療法士が当事者の方に、「膝を緩めてください」というのは決して間違いではありませんが、多くの方は膝を緩めることはできません。
脚が突っ張っているからです。
前庭神経核から入ってくる三半規管や耳石の感覚が過敏になっているので、ちょっとした頭の動揺に対し、抗重力伸展活動が過剰に働いてしまっているからです。
なので、なかなか緩められないといった状況になります。
土踏まずに体重負荷すると膝が緩みやすい
こうした時にも、代償的な手段は有用です。
足の裏に注目をしてもらいます。
土踏まずの辺りに体重が乗ると、「ああ、膝緩められた」という感覚がするはずです。
土踏まずに体重を乗せると、膝は緩みやすいのです。
ところが抗重力伸展活動が効きすぎて、脚がビューンと突っ張ってると、緩めるのが大変です。
なので、脳卒中片麻痺の方は、倒れるようにドスーンと座ってしまうんです。
「ドスンと座っちゃいけません」というのは言うのは簡単ですが、なぜドスンと座ってしまうのか…を考えないといけないです。
それは、膝の「グレーデッドコントロール」(運動の強度や負荷を段階的に変化させること)ができないからです。
この背景にも、前庭神経核=身体の強い力を出す神経活動が過敏になっていることがあるでしょう。
過敏な状況をなめるためには、他の感覚情報に置き換える代償手段が有効です。
目で確認し、土踏まずのところに体重が来るようにします。
そのままお尻がすっと降りていくように、目を使って下を見ながら、身体全体を屈曲させていく。
こうした代償的なアプローチが、実際の臨床現場では活用できると思います。
本来、こうした代償手段は使って欲しくないですが、日常生活が安定した状態で過ごせた方が、当事者の方がの人生にとって、豊かな時間になると考えています。
まとめ
座っていく時には、代償的な感覚に置き換えてあげることも実は有効な練習方法だ、という事を解説しました。
「筋活動のパターンは神経活動によって変化する」という事を覚えておいて下さい。
動画内容・チャプター
1:29 様々な筋活動のパターン
2:20 神経活動により筋活動のパターンが変えられる
2:56 神経活動とは
3:36 お尻を向けるのには認知機能が必要(前回の復習)
7:37 自分で問いを立てて考えられるのがベスト
8:20 代償的な動作
9:11 前庭神経の役割:転倒時に抗重力伸展活動を生じさせる
10:07 頭が安定性限界を超える
10:28 代償手段だが方向を変える練習として有用
12:00 土踏まずに体重負荷すると膝が緩みやすい
12:31 どすん!と座ってしまうのは膝のグレーデッドコントロールが効かないから
14:14 代償的な感覚に置き換えるのも有効な練習方法