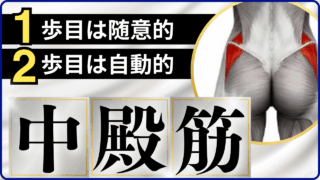
ポイント/まとめ
・中殿筋は股関節を外に開く働きがある筋肉だが、歩行中はその動きはあまり使わない。しかし、片足で立つときに骨盤を安定させる役割があり、実は歩行の安定にとても重要な筋肉。
・歩き始めの一歩目は、自分の意思によって始まる「随意運動」。脳卒中後などでは、この一歩目がうまく出せないことが多く、歩行が始められない原因になる。二歩目以降は脊髄の自動的な運動(CPG)によって続けられる。
・脳卒中片麻痺者の中には「筋力がないから歩けない」と思い込み、スクワットなどで太ももの筋肉を鍛えようとする人がいる。しかし、実際には体を支える力や感覚の問題、筋肉の使い方に原因があることが多い。
・股関節の奥にある小さな筋肉群(深層回旋筋群)は、股関節を安定させてスムーズな動きを支える。これらが働かないと、方向転換や片足立ちが不安定になる。太ももの大きな筋肉ばかり鍛えていると、逆にこの深い筋肉が使いづらくなる。
・脳卒中のリハビリで、早期に歩けるようになった人は、歩行が「うまくいっている」と思い込みやすい事がある。しかし方向転換や段差越えなどの動きで問題が起きやすく、改善が遅れることがある。
・歩行障害がある人に対して、単に筋トレをするのではなく、「支え方」「感覚」「身体の使い方」を改善する練習が必要。特に中殿筋や深層回旋筋を正しく働かせることが重要になる。
・この点に関しては、療法士も知識と経験を増やすのが不可欠。当事者が筋力不足と誤解している場合には、原因が使い方にあることをしっかり説明し、正しい練習方法へ導くことが必要。認知課題(段差を越える、方向転換、物を拾うなど)を通じて自然に正しい筋肉を使えるようにすることが効果的。
中殿筋の役割
前回動画の続きとして、「中殿筋」の役割についておさらいしておきましょう。
中殿筋は、歩行時や片足で立つ際に骨盤を安定させ、体幹が傾くのを防ぐ重要な役割を担っています。また、脚を外側に持ち上げる「股関節の外転動作」において主要な筋肉であり、股関節の内旋や外旋にも関与しています。
しかし、歩行の際には、脚を外に広げる(外転)ことは通常しません。
よって、歩行動作の中で大殿筋の働きには目が向きますが、どうしても、中殿筋のことは見落としてしまう…という方も多いと思います。
でも実は、中殿筋が歩行においてとても重要な役割を果たしています。
歩行の一歩目は随意的
歩行の“最初の一歩”は「随意的」な運動です。
「よし、歩こう!」と自分で意識して動き出そうとしない限り、歩行は始まりません。
たとえば赤ちゃんを抱っこして、そっと足の裏を床につけてあげると、足をバタバタ動かし始める。これは「初期歩行」と言われる反射的な動きで、足の裏からの感覚入力によって、歩行の神経回路である「CPG(Central Pattern Generator・中央パターン発生器)」が自動的に作動する仕組みです。
しかし、大人の私たちが交差点で赤信号を待っている時に、突然足がバタバタ動き出して歩き始めたら命に関わります。
なので、僕たちの大脳は「今は歩くな」という抑制の指令を出す事になります。因みに、これは「大脳基底核」が関係していると、個人的に理解しています。
多くの脳卒中片麻痺の方は「歩く能力」そのものは残ってるはずと考えます。
なぜなら、歩行に必要な神経回路(CPG)は脊髄に存在していて、そこが損傷していなければ機能は生きているはずだからです。
ただし、そのCPGを動かす“きっかけ”となる「歩こう」という意識である「随意的な一歩目」が出なければ、歩行は始まらない…ここがすごく厄介なところです。
歩行の二歩目は自動的
歩行における重要なポイントがもう一つあります。
二歩目からは「自動」になるという点です。
最初の一歩目は随意的に、「よし、歩くぞ!」と自分の大脳皮質が指令を出さなくてはいけない。しかし、二歩目からはCPGが働いて、自動的に歩行が続くんです。
これはもう、しっかりとしたエビデンスがある話で、論文にも出ている確かな知識です。
足を出す練習を一生懸命にしてしまう
こうした状況で、脳卒中片麻痺の方は、「麻痺している側の脚が動かないから、自分は歩けないのだ」と理解している方が多い気がします。
だから、自然と「麻痺側の足をどうにかして動かさなくてはいけない」と思い込み、先に麻痺側の足を出そうとするんですね。
一生懸命考えて、何とかしようとしているわけで、だからこそ、ついつい「足を出す練習」ばかりに意識が向いてしまう。
これが当事者の心理だと思いますし、当然の反応だと僕は思います。
深層回旋筋・深層外旋六筋
さて、「深層回旋筋」は「深層外旋六筋」とも呼ばれ、股関節の深部に存在する6つの筋肉の総称を言います。
梨状筋、内閉鎖筋、上双子筋、下双子筋、大腿方形筋、外閉鎖筋から構成されています。
これらの筋は、股関節の外旋に関与するだけでなく、股関節の安定性を保つ上でも重要な役割を果たしています。
歩行では、上記の筋群以外に、腰椎や骨盤、大腿骨が関係してきます。
股関節が屈伸することで、足が前後に振り出す事が可能となり、「歩く」動作に繋がります。
しかし、「前後に足を振る」だけでは歩く事はできません。
足を空中に持ち上げるには…
歩行で足を前に出すには、足を空中に持ち上げる必要があります。
足を浮かせるために不可欠なのが、反対側の足による支えです。
左足を振り出したいなら、右足で体を支えられていなきゃいけない。
右足を出したいなら、左足が安定して立てていないといけない。
「非麻痺側の足を先に出せばいい」とは言いますが、そもそも、良い方の足を出すためには、麻痺側で立たないといけません。
当事者の方にとってみれば、麻痺側で支えるのは怖くてできない事です。
「支える感覚」が分からないので足が出せないのです。
片脚立位が出来るのは中殿筋のおかげ
中殿筋は、片足立ちのときに骨盤をしっかり安定させ、「立って支える」という基本的な姿勢制御を助ける筋肉です。中殿筋がしっかり働くことで、初めて「反対側の足を空中に浮かせて前に出す」ことが可能になります。
歩行を可能にするためには、「振り出す足」よりも、「支える足の安定」が圧倒的に重要です。
中殿筋がしっかり収縮すると、骨盤を反対側に押し出すように働きます。
これにより、片足で立っている時に骨盤が安定し、反対側の足を曲げて空中に浮かせることができるのです。
筋トレでは深層回旋筋が働きづらくなる
歩行が困難な時、当事者の方が最初に取り組むのが「筋トレ」です。
しかし、皮肉なことに、筋トレをし過ぎると、「深層回旋筋」が働きにくくなってしまう事があります。
深層回旋筋が働かなくなると、股関節の回旋運動が起こりにくくなり、足を持ち上げる動作が不安定になります。その結果、中殿筋も働きづらくなり、片足立ちの安定性が損なわれてしまいます。
さらに注意したいのは、筋トレのやり方です。
スクワットや腿上げなどで大腿四頭筋やハムストリングスといった表層の筋肉ばかり鍛えると、深層回旋筋の働きが抑制されてしまい、股関節の安定性が低下します。そうなると中殿筋の機能も落ち、結果的に足を前に出す動作や歩行がうまくできなくなってしまいます。
マヒ由来ではない
「これが麻痺だけが原因で起きているのか?」と聞かれれば、私は違うと思います。
前回もお話しした通り、大殿筋はほとんどの場合、機能が残っていることが多いです。そうなると、深層回旋六筋などのインナーマッスルも、麻痺はない、或いは、麻痺があっても非常に軽度であると考えることができます。
セラピストの方は、片脚立位の練習をたくさん行っていますが、『片脚立位のために深層回旋筋をしっかり働かせるという視点やアイデア』は欠けていることが多いように感じます。
だから、「毎日一生懸命支える練習をしているのに、なかなか支えられない」という状況になっているように思えます。
認知機能を使った動きの練習
脳卒中を発症した後、早期に歩けるようになる方がいます。
一見すると順調に見えますが、方向転換時に足を小刻みに動かすなど、無理な動きをしていることがあります。これは、股関節の深層回旋筋や中殿筋がうまく働いていないためです。
早いうちから歩けるようになることだけに固執せず、認知機能を使った動きの練習(段差昇降、方向転換、物を拾うなど)を行い、筋肉を「うまく使う」訓練も必要です。
多くの人は筋力が足りないと感じますが、実際には「使い方」が問題です。
次の段階の動きを意識的に練習することが、よりスムーズな歩行につながります。
この点はしっかり理解しておいて頂きたいと思います。
動画内容・チャプター
0:56 原宿リハビリテーション病院でのセミナー
1:59 歩行における中殿筋の役割
2:14 足を外転させる筋肉
2:49 一歩目は随意的
4:03 脊髄にあるCPG・神経回路は損傷されていない
4:44 足を出す練習を一生懸命にしてしまう
5:54 二歩目は自動
6:37 筋トレでは深層回旋筋が働きづらくなる
7:24 脚を空中に持ち上げる必要
→麻痺足で立っている感覚が分からず怖い
8:22 片脚立位が出来るのは中殿筋のおかげ
9:13 深層回旋筋が動かない→股関節の回旋が起こらなくなる
9:59 スクワットは大腿直筋を鍛えすぎてしまう
10:35 療法士が知らないと支える練習をしても効果が出ない
11:29 方向転換の際に足踏みする患者さん
12:37 早期に歩けるようになった方には認知機能を使って歩く練習を
13:21 マヒや筋力が弱いのが原因ではない