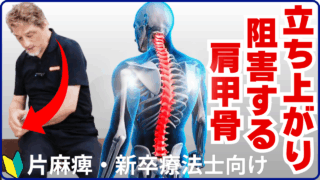
新人療法士向けに、脳卒中片麻痺者の「立ち上がり動作」に関与するROM(レンジオブモーション・関節稼働域)がどのように成り立っているのか解説しています。
肩甲骨の可動性が立ち上がりを阻害
「立ち上がる」という動作の際、当然ながら立ち上がる前には身体が起きてこないといけません。両下肢に荷重しなければならず、且つ、これまで解説してきた足関節や膝股関節、脊柱の可動性も担保されていなければなりません。
これらの関節や筋の動きを阻害する要因の一つが「肩甲骨」だというのが、本日のテーマです。
肩甲骨の働き
肩甲骨は肩関節の一部で、背中の上部に位置する逆三角形の平らな骨のことです。
腕と体幹をつなぎ、肩関節の動きをサポートする重要な役割を担っています。
肩甲骨は、鎖骨や上腕骨と連動して、肩関節を形成しています。
トランスファーにおける立ち上がりの際に、下肢の動作になぜ肩甲骨が影響を及ぼすのか、疑問に感じた方も多いかもしれません。
肩甲骨は脊柱の傾きに大きく関与しています。
肩甲骨は上肢の土台になる部位なので、上肢に触らなければ一見関係なさそうに思われます。
しかし、脊柱が動いて肋骨が動けば、それに伴って肩甲骨も動きます。
例えば、僕が動画中のように木製のベンチに座っている状態から、骨盤を起こして脊柱が上に伸びる時、脊柱の可動性が必要ですが、もし仮に肩甲骨がキュッと固まって動かなければ脊柱も動かすことはできません。
肩甲骨が脊柱の稼働性を阻害すると、結果的には、立ち上がる動作で身体の滑らかな動きを阻害してしまう事になります。
肩甲骨の稼働性が低下すると脊柱の動きがうまく出せない。
すると、脳卒中片麻痺の方は、どこかに捕まってギュっと引っ張らなきゃ立てない状態になったり、プッシュアップしないといけない状態になったりします。
肩甲骨が稼働性を低下させる要因
では、肩甲骨が稼働性を低下させる要因を考えてみます。
「立ち上がりの動作」をイメージする時、身体は左右対象で前にお辞儀するような感じて、体重を前方に移動します。
この時、脊柱を中心に考えると、脊柱は真っすぐな棒なので、これが真っすぐに倒れるためには、言わずもがな、脊柱は真っすぐである必要があります。
しかし、脳卒中で左片麻痺の方を例に取ると、左麻痺側の上肢の随意性が乏しく、ぶらんとして肩甲骨が下がっていることが頻繁に観察されます。
これだけで、脊柱の位置関係が変わっている事になります。
身体が真っすぐに伸ばせないのは非麻痺側が原因
こうした状況で、患者さんは麻痺側に倒れるのが怖いから、麻痺手を非麻痺側の方に引っ張り寄せて座っている事が多いです。
体幹が潰れた状態で、且つ、肩甲骨が稼働性を低下させているので、非麻痺側の手しか動かない状態になります。
本来であれば、健側の身体はしっかり起き上がって、脊柱が高い位置を保つことができ、手が自由に動かせるはずなのですが、脊柱がくちゅんと潰してしまっているので、手は自由に動かすことはできません。
安易に療法士が「身体を伸ばしてご飯を食べましょうね」など声掛けをしてしまうのですが、当事者の方にしてみれば、身体を真っすぐに伸ばせない理由があるわけです。
身体が真っすぐに伸びない大きな理由が「麻痺側にある」と考えがちですが、実際には非麻痺側が潰れている…という事もあるのです。
麻痺側ばかりに注目しがち
脳卒中片麻痺の方を担当する際、どうしても僕たちは「麻痺側」ばかりに目が行きがちです。
・麻痺側の身体が伸びてないなあ
・麻痺側の臀部が働いてないなあ
というのは、新人療法士の方でもすぐに気づくことです。
しかし、ヒトの身体は基本的に左右の関係性で成り立っています。
片側が潰れば反対側も当然潰れます。
麻痺側の手を使おうと頑張っていってどんどん緊張感が高まってくると、非麻痺側を踏ん張って、力を出そうとします。
非麻痺側をぐーっと突っ張って、一生懸命頑張って手伸ばそうとする。
これでは患者さんはラクに動くことはできません。
非麻痺側がゆったりして良い肩甲骨の位置を保ち、肩甲骨が十分な稼働性を保つことができれば、麻痺側の上肢の練習がスムーズにできたり、足に過重する練習がスムーズにできたりします。
ヒトの身体は基本的に左右対象
肩甲骨っていうのは左右対になって動きます。
ヒトの身体はが左右対象に動くようにできているので、左右対象に動けたら1つの長方形がまっすぐに動きます。
ところが、脳卒中片麻痺の方で、プッシュアップのように身体を傾けて起こしたり、力ずくで立ったりするのがが癖になっている場合、非麻痺側がちゃんと伸びていません。
そもそも、非麻痺側の身体の使い方をよく分かっていない方もおられるかもしれません。
僕たち療法士は、つい自分たちが何を考えずともスムーズに動けるから、そういう視点を見失いがちですし、非麻痺側は健康なのだから…と無視してしまう事もあるかもしれません。
「左右対象で動いているか」という視点を持つのが重要です。
麻痺側の殿筋や下部体幹の緊張、上肢の状態のみならず、非麻痺側でもお尻が使え、脚が使えて、肩甲骨が良い位置にキープ出来ているかを見落とさないようにするのが大切です。
麻痺側の随意性がそれほど高くなくとも、非麻痺側の体幹がしっかり起き上がり、肩甲骨の可動性が確保出来ていたら、「立ち上がる動作」は確実に、そして、正常ににできます。
断言します。
まとめ
「立ち上がる」という動作の阻害要因として肩甲骨の可動性があり、特に、非麻痺側の肩甲骨の可動性が存在するというのを解説しました。
このことを考慮した上で、臨床に取り組むのは非常に有効な手段だと思っています、
新卒の療法士に向けて「トランスファー」の自立を目指すために、「ROM」という視点で何を確認したら良いのか。
ひとつひとつかみ砕いて、要素分解しながらお伝えしています。
ここで紹介しているのは、「立ち上がる動作・起立動作」に入る手前の、"身体の使い方"の所です。
この段階でつまずいていたり、上手く出来ていない新人療法士の方が多いような印象を受けたので、この動画を配信しました。
次回は、トータルに立ち上がる動作として「ROM」をどういう視点で考えるべきか講義したいと思います。
動画内容・チャプター
0:46 立ち上がりの動作:身体が起き上がる
1:16 肩甲骨の稼働性が阻害要因
1:47 肩甲骨は脊柱の可動性に関与
2:51 脊柱の動きが出せないとラクに動けない
3:14 肩甲骨の稼働性が低下する理由
4:13 脳卒中片麻痺者が取りがちな姿勢
5:23 非麻痺側の体幹が潰れている
6:41 非麻痺側に問題がある
8:07 左右対象で動いているかを確認する
9:48 起立動作の手前の"身体の使い方"からつまずいている