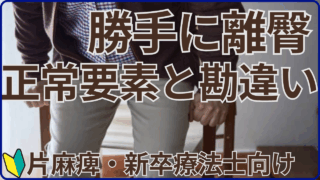
今日から「立ち上がりの筋活動パターン」について解説していきます。
『座っている状態から立っている状態に移行していく間』が立ち上がる動作であるとも考えられるので、そもそも上手に座れているのか、立つ姿勢が安定しているのかという視点を持つ事が重要だと前回の動画で講義しました。
ここでは、立ち上がる動作の時に必要な筋活動をどう考えればよいのか、「立ち上がりの正常要素と対象者の勘違い」というテーマを据えて解説してみようと思います。
立ち上がりの正常要素と対象者の勘違い
このシリーズで何度が触れているように、筋活動は同時進行で様々な筋肉が働く状態を言いますが、その中で、僕たちの意識にのぼってくる筋活動は限られています。
「立ち上がりの動作の正常要素」に関する基本原則を知らないままでは、対象の方がどこでうまくいっていないのかを見誤ってしまう可能性があります。
(必ずしも正常運動である必要はなく、その判断は臨床状況によってケースバイケースですが)
若い療法士の方を拝見していて、立ち上がる動作の大まかな形は知っているものの、どういう筋活動や関節運動が発生しているのかという細かいメカニズムまで熟知できていないような気がしています。
特に、こうした情報は教科書にも載っていないので、専門学校のカリキュラムで習得する機会もないようです。
その結果、何となく世間に広まっているような表面的なリハビリ介入に終わってしまい、「座っているところからお辞儀するように前に身体を倒したら足をぐっと踏ん張ります…」といった紋切型の指導になっているのではと感じています。
このような伝え方で、当事者の方がうまくリハビリが進むのであれば良いですが、思ったようなリハビリ効果が得られない方が大半ではないでしょうか。
立ち上がりのデモンストレーション
実際に、立ち上がる時の状況を再現してみましょう。
動画 3:41 から開始しますのでチャプターをクリックしてご覧ください。
立ち上がるというのは、座っている所から重心を足底に移し、身体を起こす事です。
身体を前に傾ける際、前に倒れないように、背中側の筋肉がブレーキとして働きます。
そして、股関節を曲げるので、股関節の屈曲を果たす筋として腸腰筋が働く必要があります。
コアスタビリティ
ヒトの体幹部の安定性を担っているのが「コアスタビリティ」です。
コアスタビリティとは、体幹の安定性のことで、体の中心部(コア)を安定させる能力を指します。
それに寄与しているのが、インナーマッスルと呼ばれる筋群です。
体の深層に位置するインナーマッスルとして、骨盤底筋群、横隔膜、腹横筋、多裂筋が同時に働くことで、僕たちの姿勢が維持でき、スムーズな動きが実現します。
ところが、多くの片麻痺の方では、体幹部の筋活動が生じないので、「身体を前に倒す」と言われた時に「屈曲活動」だと勘違いしてしまいます。
屈曲活動ではなく「伸展活動」が正しいのです。
身体を伸展し、ひとかたまりとした身体を前に傾けていく。
つまり、股関節の屈曲機能を発揮させるのが望ましい状態になります。
ハムストリングス
股関節の屈極を使っていくと「ハムストリングス」が働きます。
立ち上がり動作では、運動方向として身体は前に傾きますが、座骨結節は後ろに行きます。
身体が1つの塊(かたまり)だとすれば、質量中心を真ん中として回転が起こるので、頭は前に来ますが、お尻は後ろに下がります。
つまり、座骨結節と膝のと後ろの方についているハムストリングスは引き伸ばされます。
筋肉は引き伸ばされると、「伸張反射」という反射を起こします。自動的に筋が収縮するので、身体を前に倒して座骨結節が後ろに行くと、ハムストリングスの伸張反射で勝手に「離臀」が生じます。
このように「離臀」が反射レベルで起きると言うのを知らないと、介入の際に上手く立ち回ることはできません。
多くの脳卒中片麻痺の方で散見される失敗場面として、足を伸ばそうとししているシーンがあります。
立ち上がりの際に脚を伸ばそうと意識・イメージしてしまうので、立ち上がるどころか、後ろに傾いてしまいます。
順序としては、前に傾いて足底に荷重できたらお尻が上がってくるので、それを上に持ち上げるという流れになります。
持ち上げる際に、大腿が後ろに送られ、ハムストリングスが働きます。
「離臀」のプロセスでは、ハムストリングスの筋活動を高めていけば、身体は自然と上に起きてきます。
ハムストリングスが下方に坐骨結節を引っ張ってくれるので、それに伴って、骨盤と脊柱起立筋が起き上がる事になります。
大腿四頭筋の強さを目安にしてしまう
立ち上がり動作の際、当事者と療法士の両方が「大腿四頭筋の強さ」を1つの目安としてしまう場合があります。
「膝を伸ばす運動なんだから大腿四頭筋が重要」と捉えるのは間違いではありませんが、ここで押さえておくべきポイントは、「大腿四頭筋はハムストリングスの拮抗筋」だという点です。
大腿四頭筋を使いすぎると、ハムストリングスは弱くなります。
これは「相反抑制」として皆さんもご存知と思います。
相反抑制は、筋肉が収縮する際、反対の動きをする筋肉(拮抗筋)が弛緩する神経反射のことです。
相反抑制が起こってしまうので、大腿四頭筋を使えば使うほどハムストリングは弱くなり、離臀も自然に起こらなくなります。
思った通りに離臀が起こらないので、片麻痺の方はプッシュアップをしてみたり、脚を突っ張ってみたり、手を引っ張って身体をムリヤリ起こそうとしてしまうのです。
一連の筋活動を押さえる
・ハムストリングが働く
・コアスタビリティが機能し、下部体幹の緊張が一定にたもたれる
・身体がひと塊になる
・足関節で下腿三頭筋が働き、底屈方向に力が出せる
・前脛骨筋も同時に機能している…
一連の筋活動が遂行できた時に、「立ち上がる」動作が達成できます。
こうした筋活動のパターンを把握しておくと、どこに問題の原因があるのかが特定がしやすくなり、見当違いのリハビリを提供することが防げます。
筋力低下でも反射レベルで立ち上がりは可能
立ち上がり動作でお尻が上がらない時、臀筋が上がるように介入をしてあげると、立てるようになる方は意外と多いです。
筋力低下が相当進行している方でも、立ち上がるという動作は、ほぼ反射レベルでできるケースがあります。
運動力学的なレベルで言えば、筋肉の活動使わずとも、骨関節や靭帯の強さだけで動ける方は多いという印象を抱いています。
「筋力が低下しているから立てない」という短絡的な判断は、8割型間違いではないだろうか…というのが個人的な推察です。
「筋力」ではなく、「筋肉の使い方」が間違っている。
座位から骨盤を起こして前に傾き、ハムストリングスの伸張反射が起こる段階でつまずいている方が非常に多いなとというのが僕の臨床実感です。
リハビリ職人育成講座・有料版
では、立ち上がり動作でボトルネックになっている箇所を解決するためにはどう介入すればよいのか。
申し訳ありませんが、具体的な技術に関しては、「リハビリ職人育成講座」の有料版にてご案内していますので、ご興味がある方はそちらの講義をご覧ください。
脳卒中片麻痺の方が立てない場合、「立てないから立つ練習をしましょう」というのが役に立たないというのを、講座を通じて深く学んで頂けると思います。
動画内容・チャプター
0:25 前回:姿勢保持の筋活動
0:55 今回:立ち上がる動作の筋活動
1:24 立ち上がりの動作の正常要素
3:41 立ち上がりのデモンストレーション
4:25 コアスタビリティ
4:47 屈極活動と勘違い→正しくは伸展活動
5:08 ハムストリングスが働く・伸張反射
7:13 大腿四頭筋の強さを目安にしてしまう
(ハムストリングスの拮抗筋・相反抑制)
9:12 筋力低下でも反射レベルで立ち上がりは可能
10:03 成立させるための介入とは…