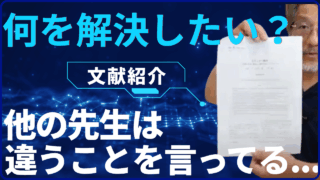
前回の動画をアップした所、ハンドルネーム「かかしさん」という方よりコメントを頂戴しました。
ご質問にお答えする形で、皆さんの学習にどう繋げていけば良いのか、山田の考えをシェアしたいと思います。
かかしさんからのコメント
少しお聞きします。ストロークラボの金子先生は離殿時の四頭筋活動を大切にされていましたが、先生はハムストリングスの伸張反射が大切とのことでしたがどちらが正しいのでしょうか?
山田より返答
私の主張は、「使いすぎや勘違い」が問題で、あくまでも離殿時の「同時収縮(ハムストリングスと大腿四頭筋を同時に使う)」は必須です。
が、しかし、当事者や若手の療法士が「膝を伸ばす」という勘違いをされているので、あえて「ハムストリングス」という呼称を使っております。
大腿四頭筋が「必要ない」という意味ではないというご理解をして頂けたら幸いです。
つまり、どちらも正解という見解です。
①どう理解する?文脈の違い
離殿に際して「大腿四頭筋」を重要視するか、「ハムストリングスの伸張反射」に重きを置くかは、両方正しいという事になります。
大事なのは文脈を考える事です。
金子唯史先生は個人的に知っており、脳卒中片麻痺に対する神経学的アプローチやハンドリング講座を実践されていると理解しています。
僕は彼のセミナー内容を詳しく把握していませんが、恐らく「片麻痺者が上手く立ち上がるための解決方法」をテーマに掲げていらっしゃるのだと推察します。
実際の臨床現場で、皆さんが担当する片麻痺の方は、色々な障害を抱えており、そこに潜む問題も多岐にわたります。
前回の「新卒療法士向け 筋活動パターン講座」の動画では、一つの考え方として「ハムストリングスの伸張反射」をお伝えしましたが、何も深く考えずに臨床にいきなり落とし込むのは危険です。
文脈を考える
立ち上がる動作において、皆さんの目の前にいる脳卒中片麻痺の方が、うまく立てない理由がハムストリングスにあるのか、大腿四頭筋にあるのか、足関節にあるのか、肩甲帯にあるのか…それは皆さんにしか分かりません。
皆さん自身が自分の力で評価をするために、一つの考え方として持っておいた方が良いと提案しているのが「ハムストリングスの伸張反射」なのです。
金子先生の講習会と山田の講座では、「文脈や背景が違う」という事を押さえておいて下さい。
②他の情報にあたる
持っている知識が正しくとも、目の前の方が立ち上がれたり、脚を振り出すことができなければその知識に意味はありません。
僕が言っているハムストリングスの伸張反射も、一つの正しい知識ではありますが、これだけでは臨床では役に立ちません。
目の前で困っている方を何とかしてあげたいなら、状況を正しく把握すると同時に、不足している情報を補いつつ勉強するしかないと思います。
力学的負荷に着目した動作分析
2002年と少し古いですが、大変優れた論文がありますのでご紹介します。
■関西理学療法
2002 年 2 巻 p. 25-40
特集1:正常動作を考える 立ち上がり動作
―力学的負荷に着目した動作分析とアライメント―
後藤 淳, 高田 毅, 末廣 健児
奈良社会保険病院 リハビリテーション科
https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282680…
この論文は示唆に富んでいますが、あくまで「データから読み取れる傾向はこうです」と言っているに過ぎず、絶対の正解ではありません。
③何を解決したいのか
解剖学や運動学、神経科学など、様々な学問からデータが取れるようになっていますが、100%科学的に正しいのかどうかについては誰も分かりません。
僕たち療法士は、常に新しい知見を探し求める科学者の立場でもありますが、その新しい知見は大体多くの場合、「仮説」として提案されています。
自分で調べたり、他の情報にあたるとは言っても、『正しいか・正しくないか』を追究するのではなく、現在の研究ではこうなっているが、自分の目の前にいる当事者の方は一体どうなのか、何につまずいて困っているのか…を見定める必要があります。
そして、それは直接介入をしている皆さんにしかできないことです。
入手した情報が正しいのか、正しくないのかに振り回されるのではなく、自分が解決したい問題をはっきりさせ、それに必要な情報を集めて仮説を立て、検証しながら目の前の人を改善へと導くことが肝心です。
動画内容・チャプター
1:06 かかしさんからのコメント
1:40 3つのテーマ
2:06 質問内容:四頭筋活動かハムストリングスか
2:30 ①どう理解する?(文脈の違い)
4:12 片麻痺者が立ち上がる為の方法
5:15 ハムストの伸張反射を臨床に落とし込むのはリスキー
6:42 背景がある
7:32 とあるPTのエピソード(愚痴)
9:02 他の情報にあたる
9:22 文献:2002年 関西理学療法
11:53 データから読み取れる傾向
13:21 新しい知見は「仮説」
14:53 自分で調べる・仮説立ててみる
15:22 自分が何を解決したいのか