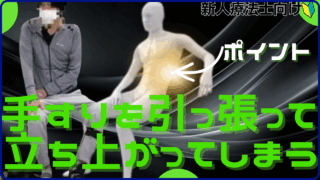
脳卒中片麻痺の方で、手すりをぎゅっと掴み、その力を利用して立ち上がるというのを選択される方がいます。
これまで講義をしてきた筋活動のパターンや関節の稼働域、姿勢の安定という側面で考えた場合、なぜそういう動作を選択してしまうのかという事を解説してみようと思います。
結論
結論を先に述べると、「そうしなければ動き出せないから」です。
その理由はいくつかあると思いますが、少なくとも、当事者の方が選択・判断してその動作をしてるということは、そうしないと動き出せないというのが最初の段階にあるということです。
こうした動作を回復期病院の入院中に繰り返し練習をしてきたら、『自分はこういう風に動く」と学習し、身体は覚える事になります。
この現象を見て、ある程度経験がある療法士なら、「誤学習」が起きているのでよろしくないなと判断することができます。
当事者の方が、いつもこの選択肢しか持っていなければ、手すりをぎゅっと掴むという、同じシュエーションでしか動けないという事になります。
本来であれば、手すりがあってもなくても、立ったり座ったりできた方が良いです。
山田のクライアント
動画 3:44 からご紹介している男性は、僕のクライアントで、「Let's ケーススタディ 脳卒中リハビリテーション」のモデルとしても登場下さった方です。
座位では、麻痺脚が著しく外転してしまっていて、非麻痺側でぐっと押さえこんで身体を何とか起こそうとされているように伺えます。
この方は、手すりを使わなくても立てるのですが、立ち上がる時にぐっと右の肩を挙上されるので、結果的に手すりを引っ張ってるのと同じような筋活動パターンを使っている事になります。
脚が内側に来ない座り方が問題
こういう方と対峙した時に、恐らく多くの療法士が、「両下肢が真っすぐでないと立てないから、下肢の位置を整えて立ち上がりの練習をする…」という判断をされると思います。
動画をご覧頂いている先生方も、同様の事を行った経験があるかもしれませんが、どうでしたでしょうか?上手く行った事はありますか?
介入の結果、当事者の方が誤学習を修正した動作パターンで動けるようになり、座位で脚が外に開かないようになった、とはならないと思います。
なぜならば、脚が内側に来ないことが問題ではなく、「脚が内側に来ないような座り方をしていることが問題」だからです。
体重移動から始める
前回の動画では、立ち上がり・離臀の際に「ハムストリングスが重要」という事について言及しましたが、今は離臀の前の話です。
立ち上がりにおいて、通常我々は「体重移動」から始めます。
安定姿勢からは動き出せず、体重が移動が最初のとっかかりになります。
ニュートンの運動力学に「慣性の法則」というのがあります。
物体は、外から力が作用しない限り、静止しているものは静止し続け、運動しているものはそのままの速度と向きで等速直線運動を続けます。
ニュートンの運動力学の法則に即して僕たちの身体も機能しているので、座位の状態に対して何かしらの「外力」が働かない限り、僕たちはここから動き出せません。
では「外力」が何に相当するかと言うと、「体重を移す」ための外力。
すなわち、「股関節屈曲」になります。
もっと積極的に股関節を屈極させたら、脚を上げる動作になります。
脚を上げる時は、自ずと、体重は後ろに傾きます。
反対に、股関節屈曲で体重を前にする時には、体が前に移動します。
腸腰筋と大腿直筋の作用によって股関節を屈曲しますが、上肢の重さは前にかかってくるので、ハムストリングスや下腿三頭筋によって、底屈方向・下に押し付ける作用も同時に働く必要があります。
麻痺脚が外に流れているのではない
先ほどの男性の身体状況を再び考えてみましょう。
彼の場合、麻痺脚が外に流れているのではなく、「麻痺側臀部が機能していない」と評価する事ができると思います。
「麻痺側のお尻が座面を感じ取り、その上で身体を起こす」というのをしていないので、身体が崩れて、頭が斜めになってしまっているのです。
この方は、非麻痺側の手で、身体を真っすぐに押し上げることで、「自分はまっすぐに座れている」という確認をされています。
麻痺側の身体感覚は、姿勢コントロールでは一切使われていません。
使われていないので、麻痺側の腰を起こして股関節を屈曲する事ができていません。
よって、手すりを引っ張って股関節を曲げないと、体重移動が起こらないという状況になっているのです。
座る姿勢から介入しないといけない
健康体である僕が再現すると、椅子の半分だけに座って、残りの半分は、お尻が"空気椅子状態"になっているのと同じです。
麻痺側の臀部を当てにしておらず、感覚が無いに等しい状態で座っているのです。
これに対して療法士が取るべき行動は、大元の「座る姿勢から介入」することです。
麻痺側の脚の状態を見て、『外側に脚が開いているので、脚の位置を直してあげる事』ではありません。
療法士が立ち座りの手助けをしてくれれば、その時には麻痺脚は使えるけれども、座った途端またお尻の感覚は見失われてしまい、元の状態に戻ってしまいます。
これでは効果が持続せず、思うような結果も出せないでしょう。
下部体幹に働きかける
座る姿勢から介入する際に、最初にアプローチするのは「下部体幹」です。
腹横筋や腹斜筋などが適切に機能しているかどうかを確認します。
言い換えれば、それらの筋肉が「うまく働いていない時にはどんな状態になるのか?」を把握し、その上で、筋の働き方を丁寧に観察・評価していくプロセスになります。
必要以上に緊張して働き過ぎている部分や、逆に活動が弱くなっていて、過小に働きすぎている所も見極めます。
そうした点を整理しながら、立った姿勢からゆっくりと座る練習へと進み、下部体幹の安定が保てていれば、手すりに頼らずに立ち上がることも可能かもしれない、という見通しが立てられるでしょう。
筋活動パターンの臨床応用
上記のようにして、筋の働き方のパターンを、実際の臨床場面で具体的に活用していくことができるのです。
筋の働きの傾向を捉えることで、現場でのリハビリや運動指導に役立てることができるようになるというワケです。
具体的な手技については、有料版の「リハビリ職人育成講座」で解説していますので、ご興味のある方は登録してみて下さい。
動画内容・チャプター
0:19 健側の手で手すりを引っ張って立ち上がる
0:49 脳の中で動作を選択している
2:13 結論:そうしなければ動き出せないから
3:04 誤学習:手すりがないと自分は動けない
3:25 動き出しの筋活動を考える
3:44 山田のクライアント
4:59 脚が内側に来ない座り方が問題
5:50 体重移動から始める
7:06 体重を移す為の外力→股関節屈曲
8:45 麻痺脚が外に流れているのではない→麻痺側臀部が機能していない
10:11 座る姿勢から介入しないといけない
10:48 練習したのに結果が出せない
11:16 下部体幹に働きかける
12:08 筋活動パターンの臨床応用
12:25 詳細は有料版にて