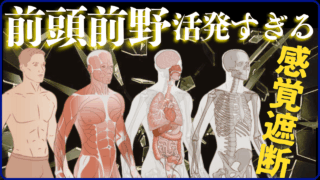
今回は「脳卒中片麻痺者に対する立ち上がり動作の捉え方」について、リハビリ現場でよくある「落とし穴」と、それを乗り越える視点をお話しします。新卒・若手の療法士の方に是非知っておいて頂きたい内容です。
立てるのになぜ歩けない?
臨床現場でよく見るのが「立てるけど歩き出せない」という片麻痺の方です。
立位は何とか安定して取れるのに、そこからの一歩が出ない。
その原因を「筋力不足」だと判断していませんか?
或いは、「立つことはできるけど歩くのは難しいんだ」と決めつけてしまう…
実は、そうした評価の8割は見立て違いです。
本当の理由は、「感覚統合がうまくいっていないこと」にあると断言できます。
感覚統合が動作の質を決める
立ち上がり動作は、頭の位置、視野の変化、足裏の接地感、筋の伸張など、複数の感覚情報が瞬時に変化し、それらが統合されてはじめてスムーズな筋活動が起きます。
具体的に言うと…
・足関節の背屈の角度
・股関節の位置・角度
・脊柱の角度
・頭の位置
・目線の変化・床からの距離
・見える面積や範囲
・三半規管からの前庭感覚
・接触感覚
・筋紡錘と腱紡錘
身体の色々な部位や神経などが時々刻々と変化しながら、同時進行で無意識に活動できる必要があります。
しかし、片麻痺の方は、感覚が鈍くなっていたり、脳内でその情報を上手にまとめられなかったりします。
加えて、「うまく動こう」と頭で考えすぎると、前頭前野が過剰に働き、感覚処理がさらにブロックされてしまうのです。これは非常に厄介な事です。
“考える動作”は感覚を鈍らせる?
患者さんの多くは、リハビリ中に「こうかな? 先生、これで合ってますか?」と一生懸命に訴えてこられます。
つまり、動作を“頭でやろう”としているのです。
前述した前頭前野をめいっぱい使っている状況です。
でも、本来の動作は“身体が勝手にやってくれる”ものであって、意識して動かすものではありません。
意識すればするほど、感覚がぼやけ、動作はギクシャクしてしまう。ここが大きなポイントです。
感覚に“気づく”練習が効果的
私が臨床現場でよく行うのは、「感覚に注目させる」練習です。
例えば、「足元を見ながら立ってみて」「お尻が上がる感覚を確かめてみて」「視線の高さが変わるのを感じてみて」などというふうに患者さんに指示します。
こうすることで、特定の感覚への注意が高まり、前頭前野の活動が落ち着き、統合が促進されます。
まずは『ひとつの感覚』に集中させてみましょう。意外なほど、スムーズに動き出せることがあります。
正しい練習と質の高さ
反対に、一般的なリハビリ場面でよく見かける光景が、紋切型の声掛けによる練習です。
具体的な理由や目的があってこうした練習をするのは良いですが、見よう見まねでただやっているだけでは効果は薄いと思われます。
「しっかり体を起こして、頭を前に出して、足で踏ん張って…」
表面的な形の練習だけでは、うまくいかないことが多いです。
動作の“かたち”だけを繰り返しても、感覚のズレが残っていれば、タイミングの合った筋活動は生まれません。
だからこそ、「どんな練習をするか」が極めて重要。動作の質を高めるには、過剰に意識しすぎない、感覚統合に注目したアプローチが不可欠です。
まとめ
脳卒中片麻痺のリハでは、「なんとなく動ける」「不安で怖いけどとにかく動く」という状態から「安心してラクに動ける」へのステップアップが鍵です。
そして、それを実現できるか否かは、僕たち療法士の『観察力と提案力』にかかっています。
次回は「立ち上がり動作における筋活動パターン」について深掘りしていきます。
動画内容・チャプター
0:21 前回:肩甲帯の重さが動作に悪影響を及ぼす
1:07 脳卒中片麻痺者は別で考える必要がある
2:11 臨床判断の8割は間違っている
2:35 タイミング良い筋活動には感覚統合が必須
3:23 動作を繰り返し練習しただけでは良くならない
3:41 意識の問題
4:35 筋活動は意識的にはできない
6:32 1つの動作に集約できて筋肉は活動を始められる
8:25 感覚統合:脳内作用なので意識には上らない
9:05 片麻痺者が形の練習をしても効果は薄い
9:53 何も考えずに筋肉がタイミング良くどんどん切り替わる
10:26 前頭前野の過活動:感覚が遮断される傾向
11:01 一生懸命考えてしまうと統合が起こらない
11:24 動く感覚は言葉でもなく、頭で考える事でもない
12:07 1つの感覚に注目できると感覚統合は起こりやすい
12:37 感覚統合は意識的になればなるほどうまくいかなくなる
13:12 当事者は自信がなく、怖くて、どうした良いか分からない
13:50 来週:筋活動パターン 立ち上がり・離殿