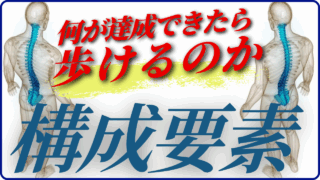
今日から新卒療法士向けに「歩行の構成要素」と「歩行障害の要因」を取り上げ、ビギナーでも分かりやすいレベルで解説しようと思います。
結論・まとめ
・脳卒中片麻痺の方が歩けない原因として、非麻痺側の体幹に問題ある
・表面的な現象として、麻痺脚で支えられないので歩行できないように見えるが、それが全てではない
・運動と姿勢を考える
・腹筋や腹斜筋、腹横筋、腹直筋、多裂筋、脊柱起立筋などがバランスよく働き、脚の動きに合わせて骨盤の上の体幹も動くのが不可欠
・前皮質脊髄路は両側支配
・急性期/亜急性期:非麻痺側の脚でしっかり立ち、身体を起こす練習が効果的
見た目の現象から生まれる誤解
脳卒中片麻痺で歩けない状態において、見た目の現象としては、麻痺足で体重が支えらなかったり、麻痺足が動かないので歩けないように見えてしまいます。
ところがこれは誤解です。
この時期に歩けない事の原因はマヒが全てではありません。
ここで想定している時期は、脳卒中発症初期の急性期から回復期に移行したばかりの1ヶ月程度としています。
結論:非麻痺側の体幹に問題あり
脳卒中片麻痺者が歩けない原因として、非麻痺側の体幹に問題が存在する場合があります。
ここで考えるべき歩行の正常要素として、「二つの要素」があります。
1.歩行運動エリア
2.骨盤から上の体幹頭頚部
上記2つは、運動(交互の下肢の動き)と姿勢(骨盤から上の体幹頭頚部)です。
慣性の法則を考えるとしっくりきますが、身体の構造に対する運動法則では、脚だけが動いたら上半身は倒れます。
達成条件:脚の運動に対して身体が脚の上に置かれていること
歩行の達成条件として「脚の運動に対して身体が常に脚の上に置かれていること」が必須となります。
ポイントとして挙げた、「運動と姿勢コントロール」が大切である理由が分かると思います。
骨盤と下肢は骨で直接繋がっていますが、体幹と骨盤は背骨でしか繋がっていません。
背骨は積み木のような構造で、ぐにゃぐにゃ動くので、バランスが崩れないように止めておく必要があります。
そのために働くのが腹筋や腹斜筋、腹横筋、腹直筋、多裂筋、脊柱起立筋などです。
これらの筋群が、バランスよく働くことで、脚の動きに合わせて骨盤の上の体幹も動いてくれるのです。
これが歩行で達成したい基礎条件です。
視床出血や被殻出血では基本的に麻痺は出ない
視床は感覚を司る部位であり、運動を司る部位ではありません。
視床核など、直接運動に関係する経路へのダメージなどを除き、原則として視床が障害されても運動麻痺は生じません。
同様に、被殻出血でも基本的に麻痺は出ないので、歩けない状態にはならないと理解しています。
最初のマヒは脳ショックが原因の可能性
だとすれば「歩行障害の要因」とは何か。
何がうまくいかなくて歩く事ができないのでしょうか?
発症初期に出現する「マヒ」は、急性期や亜急性期にかけての「脳ショック」が原因だと捉えています。
脊髄損傷になると、脊髄全体が炎症を起こして、機能不全が生じることがあります。
これを「脊髄ショック」と呼びます。
脳も同じで、脳に何らかのダメージが及んだ場合も、「脳ショック」により炎症や浮腫が生じます。
この「脳ショック」によって、初期の麻痺が生じているのだとすれば、ショックが収まってきたら、徐々に残存機能は蘇ってきます。
これが、自然回復のプロセスであり、医療が何もしなくても自然治癒するという流れです。
※脳ショック由来のマヒなのか、皮質脊髄路が壊れてしまって起こるマヒなのか判別はつきません。
前皮質脊髄路(両側支配)
さて、前皮質脊髄路は姿勢コントロールに関わる、両側支配の神経回路です。
両側支配なので、右の脳が損傷すると、左の脳にも影響が出ます。
仮に、右の脳の損傷によって麻痺が残った場合、目に見える現象としては左上下肢の麻痺ですが、姿勢コントロールに関しては両方で障害されている事になります。
非麻痺側の体幹でも問題が生じてしまうという事です。
これは、急性期や亜急性期にかけて起こる大きな問題です。
両側の体幹がバランスよく活動しなければ、上半身は極めて不安定な状態になります。
体幹がブランブランしていたら、仮に脚が動くようになっても、身体を硬直化させて、代償手段を使って歩くしか術がありません。
自由にラクに歩ける状態からはかけ離れてしまうのです。
急性期・亜急性期:非麻痺側の脚でしっかり立ち身体を起こす練習
上記のような状況になるのを防ぐには、急性期・亜急性期である程度バイタルも落ち着いてきて、少し負荷が高いリハができるようになったら、非麻痺側の脚でしっかり立ち身体を起こして、手がある程度自由になるような練習をしないといけません。
この練習をすると、両側で均等に姿勢コントロールができるようになり、体幹が働きやすくなります。
臨床現場では、脚が動く・動かないの前に、きちんと立てているかどうかを観察・評価することも大切でしょう。
立とうとした時にグラグラするとか、身体が硬くなっていて、非麻痺側の動きもぎこちない様子が見られれば、いくら歩く練習を重ねた所で、上手に歩けるようにはなりません。
ここを理解しておく必要があります。
歩行と障害の知識を統合して考える
新卒療法士が臨床でつまずくのに、使える知識を持っていないことが背景にあると思っています。
情報が不足している。
「正常な歩行の構成要素」と「歩行障害の要因」に関する知識はそれなりに持っていても、両者をうまく統合しながら、もう1つ上のレベルで考えられるようになれば、皆さんの能力も早いスピードで進化するでしょう。
歩行障害の背景には、「非麻痺側の体幹の不安定さ」が隠れている事もあり、その事に7年間気づけなかった患者さんもいます。
皆さんは今のうちに、歩行と体幹の関係をしっかり学んでおいてください。
動画内容・チャプター
0:23 新卒者向け「歩行と歩行障害」
1:34 歩行の構成要素と脳卒中により障害されること
2:04 見た目の現象から生まれる誤解
2:34 想定している時期
3:16 結論:非麻痺側の体幹に問題あり
3:40 脚には何故マヒが生じたのか
4:33 歩くための二つの要素(歩行運動エリアと骨盤から上の体幹頭頚部)
5:11 慣性の法則:脚だけが動いたら上半身は倒れる
6:06 達成条件1:脚の運動に対して身体が脚の上に置かれていること
(姿勢コントロールと運動コントロール)
7:23 腹筋の重要性(骨盤と体感を繋ぐ)
8:05 小脳疾患の場合は脚だけ動く
8:38 視床は感覚を司る・運動を司る部位ではない
9:27 視床出血や被殻出血では基本的に麻痺は出ない
10:07 最初のマヒは脳ショックが原因の可能性
11:57 前皮質脊髄路(両側支配)
13:32 急性期・亜急性期:非麻痺側の脚でしっかり立ち身体を起こす練習
14:22 脚と上半身が連動して動く必要がある
15:22 歩行と障害の知識を統合して考える
16:35 視床出血 発症7年のクライアントのエピソード