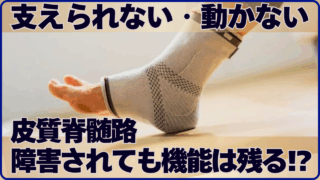
「歩行と歩行障害講座」第2回目の今日は、「運動性」について講義したいと思います。
前回は、急性期での姿勢コントロールについて解説しました。
(体幹筋は両側支配であり、片麻痺でも両側に影響が出る可能性がある)
今回は、麻痺足が「支えない・動かない」理由について考察してみようと思います。
結論・ポイント
・皮質脊髄路が損傷したことによる麻痺は末端(手足にしか出現しない)
・殿筋や肩関節周囲筋などの中枢部の筋活動は能力が残っている方が多い
歩けない現象:本当にマヒが原因?
脳卒中片麻痺の方を担当した際、「立てない・歩けない」の原因は麻痺と考えるのが一般的です。
しかし、「運動麻痺=支えられない」ではない事もあるのです。
皆さんがご存知の「皮質脊髄路」は主に手足の末梢を制御しています。
特に「外側皮質脊髄路」は、ファインムーブメントなど、細かく精密な動きをコントロールしています。
つまり、極端な言い方をすれば、皮質脊髄路が障害されたところで、立てないわけはない。
麻痺があっても「脚で支えることは可能なはず」というのが個人的な考えです。
特にお尻(臀筋)が萎縮しているケースが多い印象です。
廃用性症候群の典型的な形であり、リハビリ開始前に、どれだけ安静にしていたかも考慮すべきです。
ドクターから許可が出たからと言って、背景を考慮せず、いきなりハードなリハビリを開始するというのも危険かもしれません。
感覚と認知機能の重要性
脳の病気になると、自ずと、認知や感覚にも影響が出ます。
感覚に関しては、脚が「地面についている感覚」が得られなければ、力を出すことはできません。
筋力は“抵抗”があってこそ発揮されるものだからです。
支えるには大腿骨の固定が必須であり、それを担うのが大殿筋です。
大殿筋の役割
大殿筋は股関節の安定性と脚のアライメントに関与しています。
大殿筋が働かないと脚は不安定になり、グラグラしてしまいます。
脚の補強を行うのに「装具を使う」というアイディアを真っ先に思い描くと思いますが、下肢装具では大殿筋の役割を補えないことがあります。
脚の構造は、骨盤の関節窩に大腿骨頭がおさまり、大腿骨、脛骨、腓骨、膝蓋骨、足関節があり、その先には足部の骨から成る、多関節構造です。
多関節構造から成る脚に一定の力を加えても、骨がまっすぐに配列できるようアラインメントを整えるには、大殿筋の働きが欠かせません。
超下肢装具は膝折れを防ぐことは可能ですが、殿筋の補完や股関節の安定性はまかなってくれません。
更に、感覚が悪いと、大殿筋が働いていても「怖い」と感じてしまう当事者の方が多いです。認識がのぼってこないからです。
感覚を掴み取り、感じ取った感覚を判断できる認知能力があるというのも重要なファクターです。
認知機能
リハビリを実施する大前提として、自分の状態や周囲の状況を理解できないと、立つことすら難しい状況に陥ります。
また、認知機能の低下により、感情失禁を呈し、怒りっぽくなったり、妄想したり、幻覚を見たりと、感情のコントロールも困難になります。
症状と同じように、覚醒レベルも人によって異なる事を認識しておいてください。
小脳の役割と認知
さて、脳卒中で小脳や脳幹が影響を受けると、覚醒レベルや運動学習能力が低下します。
・小脳+脳幹→覚醒中枢
・小脳→運動中枢:運動の自動化に関与する
・覚醒と運動は直接障害されなくても一時的に低下→低緊張が出現
・小脳が障害される→考えないと動けない
・小脳出力は前頭前野にも届く → 認知機能の低下につながる可能性(仮説)
上記も絡めて、当事者の方が心身ともに混乱していると、練習が進まないだけではなく、筋活動が生じません。
科学的なエビデンスは探し出せていませんが、少なくとも、僕が長年臨床で見て来た限りではこのような結論に達しています。
故に、基礎的な事である「支えられる脚」を獲得するための練習をする必要が出てくるワケです。
臀筋へのアプローチ
大殿筋が使えないことで、「麻痺足が支えられない」、「怖くて動けない」という状況になるのですから、大殿筋をきちんと使えるようになる方法を検討します。
この時に、当事者の方の気持ちの焦りも相まって、スクワットなどの「筋トレ」に意識が向きがちです。ですが、スクワットを実施しても、鍛えられるのはハムストリングスや大腿四頭筋でしかありません。
こうした筋肉は意識できる筋肉ですが、大殿筋は意外と意識できない部位です。
意識しづらい筋肉をきちんと鍛えて、調整する必要があります。
こうした場面では、大殿筋が「完全に麻痺しているのか」を多角的に評価することが大切です。長期臥床による廃用性、小脳による影響(中枢部の問題)、殿筋で支え動くという感覚が乏しい…これらを複合的に加味して評価します。
解決策の一つのポイントは「感覚練習」です。
ブリッジ(お尻上げ)などで大殿筋の感覚と筋出力を高めるのが効果的です。
個々の患者さんに合わせたリハビリ手法などは、折を見て解説していこうと思います。
まとめ
・皮質脊髄路の障害による麻痺は手足にしか出現しない
・殿筋や肩関節周囲筋など中枢部の機能は残存している
・障害の要因を麻痺だけでなく多角的に捉える(感覚・認知・姿勢・廃用など)
・麻痺:支えられないではない → 「支えるとは何か」を再評価する視点が大切
動画内容・チャプター
1:49 歩けない現象:そもそもなぜ支えられないのか
2:42 本当にマヒが原因?
3:04 殿筋・股関節周囲筋(廃用症候群)
4:04 感覚の乏しさ
5:04 脚がブラブラしても膝の屈伸はできる
5:44 大殿筋を考える
7:07 股関節の安定性を賄うためには感覚が重要
7:51 感じ取った感覚を判断できる能力があるか
8:01 周囲の状況を理解できるか
8:48 感情や行動のコントロールができるか
9:52 覚醒の問題
10:17 小脳の影響(前頭前野・認知機能)
13:29 下肢ではなく大殿筋の作用
13:51 焦って筋トレに走る傾向
14:46 感覚練習の必要性
15:07 長期臥床による廃用症候群
18:08 まとめ