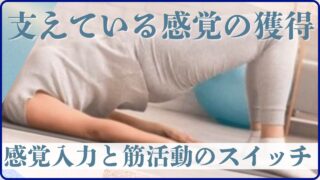
ポイント/まとめ
■結論
・支えられるようになるには「力」よりも「感覚」が重要
・「エンジンをかける準備」と「段階的なアプローチ」が臨床で活かせる
■過去動画の復習
・麻痺足の指示性や動作性を理解するための前段
第1回:非麻痺側の体幹
第2回:中枢部の筋活動・認知機能
第3回:中殿筋や深層回旋筋
■考え方
・「足を支える」「膝を伸ばす」練習では本質的な効果は薄い
・必要なのは「支えているという感覚」の獲得
・感覚がないと、膝が伸びても「怖くて動けない」
■支えられるようになるには準備が必要
・「エンジンをかける」=筋肉を使う準備をする
・麻痺は「エンジンがかかっていない」状態
・力を入れるより先に、感覚入力と筋活動のスイッチを入れる
■例:お尻上げ(ブリッジ)
・単にお尻が上がるだけではダメ
・背中の反りで上がるのは意味がない
・股関節の伸展でお尻が上がることが重要
・大殿筋・中殿筋がしっかり働く感覚を当事者に意識させる
■段階付けと達成目標
・毎日リハビリできる回復期病院と違い自費リハでは週1や月1回のことも多い
・回復期の強みを生かして「段階的な目標設定」が重要
・例:今日は感覚の入力まで、明日ははもう少し長く支えられる、その次に立位練習…というように 階段を登るように進める
■麻痺側下肢で支えられるようになるための要素
・大殿筋・中殿筋・深層外旋筋の活性
・腹筋群と体幹の筋肉の働き
・腰椎の可動性(骨盤と股関節の連動が必要)
■下肢装具について
・長下肢装具は決して悪いわけではないが、早期から装具だけに頼ると「支える感覚」が育たない
・外したときに伸展パターンが強くなったり、恐怖が出ることも
動画内容・チャプター
0:45 麻痺足の指示性や動作性を理解するための前段
1:21 支えられている感覚が重要
2:17 達成目標と段階付け
5:40 認知機能の低下
6:15 力任せにやったら感覚は分からない
7:25 横になってお尻上げから始める
8:09 殿筋が働くためには股関節が動かないといけない
9:40 練習成果の確認方法(足裏)
10:04 麻痺が支えない≠筋力が弱い
11:01 長下肢装具の功罪
11:28 歩行の構成要素
13:44 次回テーマ「筋肉の連動性」