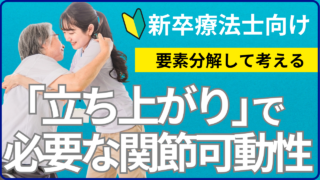
4月から新卒者の療法士向けに、脳卒中片麻痺のリハビリについて、初級編から丁寧に解説するシリーズを展開していきます。
第1回目は「ROM:関節可動域」についてお話をしていきます。
新人1年目の方が患者さんを担当した時に「どこから手を付けて良いか分からない!」という混乱状況を脱するために、先ずは「動作を分析して考える」という方法を提案したいと思います。
新人教育プログラム・きちんと教えてくれる人はいる?
新年度から新卒療法士として働き始める方も多いと思われますが、通常は一般企業のように、最初の1-2週間や数ヶ月間は、どの施設でも「新人研修」や「新人教育プログラム」が実施されるかと思います。
僕が新人療法士だった30数年前、勤務していたのは小さい病院でしたが、先輩PTが二人いたものの、どちらも若手に教育を施し、育成するというスキルと意識は持ち合わせていませんでした。
療法士学校を卒業した数年目の僕に対して「山田さん、新卒で学校で習いたてだから、僕たちの代わりに新人に教えてあげてよ!」と丸投げ状態でした。
昔と違って今は新人療法士の育成制度や実地研修の在り方も変わっているのでしょうが、組織によっては「臨床現場で使えるノウハウや技術」をきちんと教えて貰っていない若手の方も存在する気がしています。
このシリーズではその穴埋めをすべく、新人療法士の方でも分かりやすいような講義を行っていく予定です。
移乗動作・どこから手を付けて良いか分からない
第1回目の今日は「ROM:関節可動域」をテーマにします。
ROMと言っても内容は多岐にわたるので、目標設定のひとつとして「トランスファー」に焦点を当てて解説を進めていきます。
脳卒中など脳血管疾患を発症された方が急性期から回復期病院に移る時点で、「動けるようになる」というのが第一の目標になります。
病棟の看護師からは、当事者の方を「早く一人で車椅子に乗れるようにしてあげて下さい」と依頼され、大抵のケースで最初のオーダーは「トランスファー」になります。
新人が担当するのは、症状やバイタル、認知機能、メンタルが比較的安定している患者さんであるケースが多いでしょう。
比較的軽度に見える患者さんを対応する場合であっても、いざ実際に一人で立って貰おうとすると、当事者の方は車椅子のアームレストにグッとしがみついたまま、力強くヨイショ!と大変そうに動かれたりします。
こういう場面で、新人療法士は「どこから手を付けて良いかが分からない」という状況に陥ってしまいます。
車いすからラクに移乗出るようになったのは誰?
新人療法士が自身のスキルとしてトランスファーの技術を習得できないまま1-2年が過ぎてしまう…という場合もあるようです。
臨床現場では自分が「移乗介助することで頭がいっぱい」なので、患者さんに対する治療の全体像が見えていなかったり、当事者の能力を評価しながら移乗介助していくといった余裕が全くありません。
本来であれば、トランスファーの介助量を減らしていきながら、別のリハビリにステップアップしていくのが望ましいのですが、そういう高等技術を施すのは新人1-2年目では先ず無理でしょう。
回数をこなしていくうちに「当事者が楽に移乗が出来るようになりました」という実感があっても、実はそれは、単に自分が「楽に移乗介助できるようになった」という療法士側の自分都合の解釈かもしれません。
トランスファーを要素分解して考えてみる
どこから手を付ければ良いか分からないという場面では、『動作を分解して見る』という手段が大変有用です。
ベッドから車いすに移乗する際のトランスファーを要素分解してみると、5つの段階に分けることができます。
①起き上がる→必要な各関節の可動性
②座る→必要な各関節の可動性
③立つ→必要な各関節の可動性
④方向を変える→必要な各関節の可動性
⑤座って行く→必要な各関節の可動性
この順序で先ずは考え、一番問題となってるのはどの段階なのか、検討してみることは大いに意義があります。
担当する患者さんは恐らく①~⑤までの全てで問題を抱えているはずと思いますが、どの番号で、どういう状態になっているかを整理することは、自分の介入内容を整理する上でも役立ちます。
ROMを軸にして起き上がり動作を考える
「起き上がる」という動作において必要な関節の可動性は、療法士として絶対必須の知識です。
療法士の皆さんは是非自分で考えてみてください。
「①起き上がる動作」をROMの視点から考えることは重要ですが、新人の方が実践するとなるとかなりハードルは高いでしょう。
「起き上がる」という動作には実に様々なバリエーションが存在します。
新卒の療法士が「起き上がる」動作から実践を始めてしまうと、混乱に陥ってしまうことが予測されます。
個人的な意見として、初心者の方は「③立ち上がる」から始めて貰うといいかなと思います。
「立ち上がる」動作で必要な関節可動性
トランスファーの際に必要な「③立ち上がる動作」のROMの要素を考えてみましょう。
車椅に座っていられる、或いは、起き上がってベッドに座っていられるために必要な身体要素は、ROMの枠組みに限ってみても、股関節と膝関節、足関節が最低でも90度曲がっている必要があります。足関節は背屈は0度にならなければいけません。
これが出来るか、出来ないかで、座位姿勢は大きく変わります。
立ち上がるためには、最低でも股関節が100度は曲がらないと、立ち上がる動作へ移行することはできないと言われています。
加えて、立ち上がる際は足底に荷重されるので、膝も足関節もある程度の屈曲・底屈方向への可動域がないと、僕たちが通常イメージするような「立ち上がり」は実現できません。
脳卒中片麻痺の方で、仮に能力が残っていたとしても、関節の角度がキープできないので、立ち上がりに移行できない方はいらっしゃいます。
他にも、ご高齢で股関節や膝にレジ制限がかかっている方だと、僕たちが想像するような「立ち上がり」の動作では困難が伴う事が多いです。
トランスファーの理解を深め、臨床力を高めるためにも、立ち上がる動作とは一体どういう要素で成り立っているのかを考えて欲しいですし、その評価基準としてROMを活用するのは分かりやすいのではと考えています。
①~⑤に示したように、各動作に応じた関節の可動性を頭に叩き込んでおくと、スッキリ整理することができます。
同時に、トランスファーの介助の前に「脚の関節動くかな」とか「膝の関節がちゃんと曲がるかな」という事を確かめる余裕も出てきます。
ROMを測る意義
ROMを測る意義や有用性を押さえた上で、ROMが少し悪いなという風に判断できたら、その部位がROMとして悪いとなぜ動作ができないのかという事を、ご自身の頭で考えてみて下さい。
これは非常に良い勉強になると思います。
ROMの正常な可動範囲を把握していれば、良いか悪いかはご自身で判断できると思いますので、評価できた時点で、レンジの狭さや関節可動域の狭さが、動作をどのように阻害しているのか…という合理的な思考へと頭を使うことができます。
まとめ
今日は『新卒療法士向け・脳卒中片麻痺者へのリハビリ解説①』として、本日はトランスファーを構成している動作を要素分解し、ROMの観点から、今どこの機能が上手く働いていないのかを推察する方法をお伝えしました。
基本中の基本ですが、ROM・関節可動域をきちんと理解しておくだけで、新卒療法士の方が臨床で対応できる内容が広がり、今後の引き出しも増えるはずです。
レンジ制限がある場合の解決法については、別の機会に講義したいと思います。
動画内容・チャプター
0:57 ROM:関節可動域
1:27 病院での新人研修・プログラム
2:13 30年前のエピソード
3:01 ROMの目標:トランスファー
3:40 回復期では動くことが期待される
4:26 「どこから手を付けて良いか分からない」という状況
5:43 見た目の障害がクローズアップされてしまう
6:19トランスファーが上手く出来ない・やり方を教えて貰えない
6:47 当事者の能力を評価しながら介助量を減らす技量は1年目では難しい
7:16 【解決策】動作を分解してみる
8:11 ①起き上がることができるか→この時必要な各関節の可動性
9:24 起き上がる動作には様々なバリエーションがある
10:13 初心者は③立ち上がる 動作からスタート
10:45 一番問題なのはどのレベルか考える
11:48 「立ち上がる」動作で必要な関節可動性
12:55 股関節・膝関節の90度の屈曲・背屈0度
14:44 関節の角度がキープできず立ち上がりに移行できない
15:14 立ち上がりはどういう要素で出来上がっているのか(ROMで考える)
15:47 トランスファーの前に見るべきポイントが分かる
17:14 MMT(徒手筋力テスト)は難易度が高い