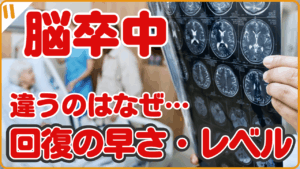【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する②】治癒・回復・代償の意味
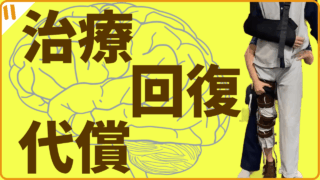
今回の動画では、脳卒中が一体どういう病気なのか、そして、回復するとはどういう事なのかを考えていきたいと思います。
目次
脊髄損傷
脊髄損傷というのがあります。
脊髄というのは、脳から下にある、神経の束が通っている部位です。
脊髄が損傷したり、骨折によって二次的に押え付けられたりすると、そこから先の神経が途えてしまい、神経の信号が末端の筋肉までいかなくなるので麻痺が起こります。
脊髄は一度ダメージを受けると再生しないので、麻痺もずっと残ります。
力士やラグビー選手など、頸椎が圧迫されるなどして、一時に脊髄部に炎症が生じた場合は、脊髄が直接損傷を受けていないので、復活することがあります。
不全麻痺
脊髄には無数の神経繊維が通っていますが、脳、脊髄、末梢神経などの損傷により不全麻痺が生じます。
運動機能や感覚機能が完全には消失せず、部分的に保たれている状態です。
動きそのものは残っているが非常に弱く、脚は動くけれど、体重支えるほど強くない…といった事が起こります。
こうしたケースでは筋力強化を図ります。
「一つの神経で筋肉をたくさん働かせるようにすれば良い」という考えに基づきリハビリを実施します。元通りにはならないけれども、筋トレを中心にして徐々に改善する事を目指します。
脊髄損傷の不全麻痺で「ロフストランド杖」を用いて歩行達成されている方もおられます。
脳卒中片麻痺
脳卒中に代表されるように、脳神経も一度ダメージを受けると基本的には回復しません。
僕の30年以上の臨床経験を踏まえて言うと、脳卒中片の場合は「完全麻痺はない」と考えています。大かれ少なかれ「不全麻痺」だと捉えています。
「脊髄損傷の不全麻痺」と同様に、脳卒中の場合も、脳の神経細胞の一部分が壊れてしまっている状態で、「不全麻痺」が出現します。
特に脳梗塞では、不全麻痺の方が多い印象です。
「不全麻痺」なのですから、残存している機能を復活できるようにしたら、100%元のように戻ることは難しくとも、また動くようになりますというのが基本的なスタンスです。
脳卒中運動麻痺回復可塑性理論とステージ理論
「脳卒中運動麻痺回復可塑性理論とステージ理論に依拠したリハビリテーション」というタイトルの論文を発表された、原寛美先生という方がおられます。
https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282679386438912
原先生は脳卒中関連のドクターでは非常に有名な方です。
上記の論文から、一部を紹介します。
急性期の回復メカニズムは残存している皮質脊髄路(ひしつせきずいろ)を刺激し、興奮性を高めることで麻痺の回復を促進する時期となる。
この1/3の興奮性は、3ヶ月までには消失する。
急性期リハビリの重要性
脚や手の随意性を司る一次運動野を起点に通っている「皮質脊髄路」の3分の2が死滅したとします。
残存している3分の1を刺激することで、30%まで落ちた皮質脊髄路の機能を、70-80%近くまで回復させるというのが「急性期リハビリにおける重要な取り組み」と位置付けています。
残存している脳細胞に対しても、何もしなければ後遺症は残ってしまうので、然るべきリハビリをして、活用できるパーセンテージを上げていこうというのが「回復」の意味する所です。
「3分の1の興奮性は、3ヶ月までには消失する」といった事からも、原先生は、急性期医療が非常に重要だと説いておられます。
『急性期医療では、リハビりは必要ない』という極端な解説をしている方もいるようですが、それは誤解です。
原先生のように、命がけで脳卒中の事を考えているドクターが「急性期のリハは重要」と述べられています。その事を理解して欲しいと思います。
回復期リハと代償獲得
一方で、急性期や回復期初期に当たる3ヶ月を過ぎたら、その後は回復の見込みが一切ないという事では決してありません。
原先生の論文で取り上げた「皮質脊髄路」のほかに、赤核脊髄路(せきかくせきずいろ)という、普段は使われていない神経回路が存在する事が分かっています。
赤核脊髄路は退化しており、まだ解明されていない部分が多いですが、脳卒中後の運動機能回復において代償的な役割を果たす可能性があるとして研究が進められています。
赤核脊髄路を補完的に使うことで、再び動きを取り戻すリハビリがあり、これを「代償」と言います。
装具や道具の活用
「代償」を強化する方法として、装具や道具を用いる手段が取れます。
残存している3分の1の皮質脊髄路を、30%から80%まで回復させたとしましょう。
100%には達しないので、装具や杖の機能をプラスさせることで、元の生活に近づけるようにしていきます。
杖や下肢装具にも様々な種類があり、使い勝手が違ったり、補強してくれる強度が違ったりします。
脳卒中の後遺症として出る現象は人それぞれなので、その人にマッチした装具や道具を選ぶ必要があります。
また症状も時々刻々と変化するので、その時々のコンディションやフェーズに応じて選び変えていくことも必要かもしれません。
下肢装具は外すべき?
歩行時の下肢装具については、多くの疑問や悩みの声が寄せられています。
装具のおかげで安心して歩けているのであれば、そのまま使用し続けるのが良いでしょう。これはまるで眼鏡をかけるのと同じことです。眼鏡がなければ細かい文字が見えませんが、僕にとっては必要不可欠なものです。
もし眼鏡が不要で、肉眼で全てが見えるならば、こんなに楽なことはありません。
しかしながら、眼鏡をかけた方が仕事がはかどるため、僕は眼鏡を選びます。つまり、下肢装具も眼鏡と同じような役割だと理解していただけると助かります。
脳卒中片麻痺で下肢装具を使っていることが悪いというわけではありません。装具を使って安心して日常生活を送れるならば、無理に変える必要はありません。
ただし、なかには家の中で装具を使わない方もいます。これは、身体機能が装具なしでも問題ないレベルにあるということです。
それでも、外出時には環境が変わるため、安全のために下肢装具を着用することが望ましいと考えられます。
代償手段で自分らしい生活を送る人も
片麻痺の当事者であり作業療法士でもある山田阿実さんという女性がいらっしゃいます。
このチャンネルにもゲストとして出演されたことがあり、以前は脳フェス名古屋の代表を務めておられました。
そんな彼女が、つい先日ご出産されました。本当に喜ばしいニュースです。
山田さんは、日々の暮らしの中でさまざまな工夫を取り入れて生活されています。
たとえば、寝起きの際に非麻痺側の手を使って身体を起こしたり、麻痺手を引き寄せてから起き上がるといった動作も行っています。これは代償的な方法のひとつです。
ですが、そうした工夫を重ねながらも、山田さんはとても豊かな日常を送っておられます。
仕事を続け、ご結婚もされ、そして赤ちゃんにも恵まれました。
女性として、実に前向きで素敵な人生を歩まれています。
代償的な手段での生活が良いか悪いかは、やはりご本人の価値観によるものです。
僕としては、「代償」という言葉には、人それぞれ受け取り方に違いがあり、とても繊細な表現だと感じています…
「脳卒中片麻痺における『代償』という言葉が、時には『もっと努力しろ』というニュアンスに聞こえることがあります。人によっては、『代償手段でも構わない』という表現が、少し突き放すように聞こえることがあるかもしれません。
次回
今回は、治癒・回復・代償の意味について解説しました。
次回は、「代償手段や装具を使って後遺症をカバーしていても、動きやすくなる人とそうでない人がいるのはなぜか?」という点について、もう少し掘り下げて考えてみたいと思います。
■文献
原 寛美
相澤病院脳卒中脳神経センターリハビリテーション科
脳卒中運動麻痺回復可塑性理論とステージ理論に依拠したリハビリテーション
https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282679386438912
動画内容・チャプター
0:32 脳卒中の後遺症は治らないが改善はする
1:07 皮膚や骨は再生、自然治癒する
4:09 脊髄損傷:脊髄は再生しない
4:59 とある力士のエピソード
6:01 不全麻痺
8:14 脳卒中:脳の神経は回復しない
8:28 脳卒中は完全マヒではない
9:23 急性期:脳卒中運動麻痺回復可塑性理論とステージ理論
14:47 急性期の3か月を過ぎても代償的動作で日常生活を送れるようになる
15:03 皮質脊髄路
15:28 赤核脊髄路
16:53 各人で症状は異なる
17:50 保険制度の問題をカバーする存在としての自費リハ
18:58 代償:装具は外すべき?
21:06 片麻痺当事者でOTの山田阿実さん
23:57 代償手段で自分らしい生活を送る考えもある
25:28 次回:回復レベルに個人差があるのはなぜか