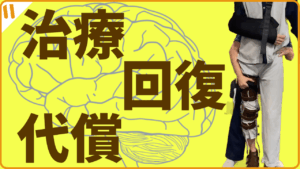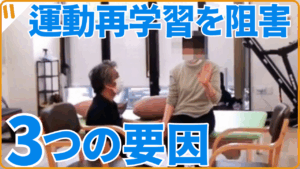【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する③】回復の早さやレベルが違うのはナゼ?学習の結果・早いうちからリハを始めても…実感としては変らない!?脳の可塑性・神経伝達物質
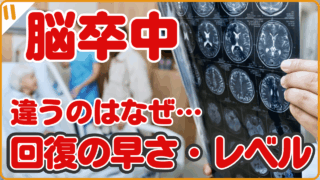
今日の動画では、脳卒中からの回復速度や程度が人それぞれ異なる理由について、脳の可塑性(かそせい)を踏まえて説明していきます。
目次
シナプス・脳の可塑性(かそせい)
脳の可塑性とは、脳卒中などの病気になった後、脳が構造や機能を柔軟に適応させる能力のことを言います。損傷を受けた部分の機能を、別の脳の領域が補完したり、新しい神経回路を作り出して失われた機能を回復させることができます。
この機能は、病気だけではなく、経験や学習によっても強化されることが知られています。
僕たちが生まれた時、脳も身体も小さく、歩けるようになるまで数ヶ月かかりますが、成長とともに脳の構造が変わり、短時間で知識や能力を身につける事ができるようになります。これは脳が「可塑性」を持つおかげです。
脳の神経回路が学習や経験を通じて常に変わり続け、身体や行動も成長・成熟します。
シナプス可塑性は、単なる回復力ではなく、学習によって新たな神経回路を形成し、機能を高める過程です。
同時に、脳の可塑性は年齢とともに徐々に低下していく機能でもあります。
昔は100メートル10秒程度で走れたものが、今では20秒以上かかることがあります。
とは言え、こうした能力は完全になくなるわけではありません。
時間はかかったとしても、走る能力は残っています。
加齢や病気の影響で、学習効率やスピードが落ちることがありますが、意識的な学習や練習、刺激によって可塑性を維持・促進することは可能です。
神経細胞・神経伝達物質
神経細胞は、体の中で情報をやりとりするための「電線」のような役割を持つ細胞です。
神経伝達物質は、その電線と電線のすき間で情報を渡す「メッセージの運び屋」のようなものです。
この仕組みで、私たちの身体が動いたり、思考や情動が生まれます。
神経伝達物質は送り手側から放出され、受け手側の受容体に受け取られるので、基本的には一方通行です。
脳卒中になると次の細胞へ司令が届かない
シナプスの繋がりが強ければ、身体もうまく動かすことができます。
反対に、繋がりが弱いと、動作はできるものの不安定だったり、遅かったり、ぎこちなかったりします。そもそも、その動作をすることが困難なケースもあります。
脳中脳によって脳の細胞が損傷を受けると、次の細胞へ司令が届かないため、手足が思うように動かなくなってしまいます。
司令を出す細胞は生きているけど、それを次に繋ぐ細胞がなくなってしまったので、次に繋がる細胞を強化したり、作り出そうとするという考えに立脚したのが、前回動画でご紹介した「皮質脊髄路(ひしつせきずいろ)」の文献です。
「脳・シナプスの可塑性」とは、「学習によって新たな神経回路を形成し、機能を高める過程」であると同時に「神経細胞(ニューロン)同士のつながり(シナプス)が強くなったり、弱くなったりする性質」も有しています。
長期抑圧
脳卒中リハビリにおける「脳の可塑性」では、「長期抑圧」も大きく影響を及ぼします。
「長期抑圧」とは、使わなくなった神経の繋がりが弱まり、動作はどうにかできたとしても、自信が持てなくなったり、動きが鈍くなったりする状態です。
例えば、昔は速く泳ぐことが出来ていたけど、今はその神経の繋がりが細くなっていて、同じようには泳げない…といった状況です。
脳卒中による後遺症も同じで、麻痺側を使わないことで神経の繋がりが弱くなります。強い神経の繋がりがある非麻痺側に対して、麻痺側は弱い繋がりしかありません。
これに恐怖や不安、嫌な体験の感情などが加わると、更に神経が働きにくくなります。
加えて、入院による長期安静で体力低下や筋力低下も起こるので、潜在的な能力が残っていても、益々シナプスの繋がりは弱まる傾向になります。
麻痺側の神経は完全に失われたわけではなくても、弱い繋がり(抑圧)+筋力低下+恐怖感などが複合して「マヒ」のように見える場合があります。
長期増強
「長期抑圧」に対して、「長期増強」というものがあります。
「長期増強」とは、シナプスからの神経伝達物質の放出が長期間にわたり増加する現象を言います。
神経回路の可塑性の基盤とされており、このメカニズムを活用することで、損傷した脳や神経の機能回復を促進することが期待されています。
長期増強、長期抑圧はどちらも正常な機能として、両方ヒトに備わっています。
しかし、反復的な運動や刺激によってシナプスの結合が強化される「長期増強」の結果として、望ましくない代償的な動作パターンが身についてしまう場合もあります。誤学習です。
この理由として過去のトラウマ的体験や恐怖心、効果的な練習が持続できなかったことなどが考えられます。結果的に、「長期増強」から「長期抑圧」になってしまうケースもあります。
麻痺や分回し歩行の原因と改善の可能性
前回の動画に対し、ゆにこさんという方から、ご質問を頂戴しました。
代償運動の代表格としてぶん回し歩行があると思うのですが、足をまっすぐに降り出すための筋肉に命令する神経の回路が壊れたので、代わりに働いてくれている神経のなすがままに歩くとぶん回し=代償になる、という考え方の方向性はあっているでしょうか?
ご質問への回答として、僕は異なる見解を持っています。
普通に動く可能性は持っているが、麻痺側・非麻痺側の両方でしっかり身体を起こすことができていないので、足をまっすぐに振り出せないと位置付けています。
分回し歩行という、現実的な「代償動作」は、神経の回路というよりは、筋肉の使い方で起こってくると考えています。
「神経は正常な歩行が出来る能力を持っている」が、その能力をうまく使えていない状態で練習を重ねてきた結果、が分回し歩行であるという理解です。
そして、分回し歩行自体は改善の可能性がある、というのが僕の個人的見解です。
分回し歩行をされている方は、多くの場合、健側に頼って足をよいしょと持ち上げ、骨盤を引っ張り上げて足を前に振り出す動作を覚えておられます。
これが分回しの原因だとすると、不安感や恐怖感をなだめてあげたり、弱くなってしまった筋肉を先回りして鍛えておいたり、分かりづらくなった動きを先に練習しておいてから、ゆっくり丁寧に非麻痺側の足で立ったら、分回しは改善される可能性はあると考えています。
では、「私の状態は良くなりますか?」と聞かれたとすると、「ゆにこさんのお身体を詳しく拝見しないと分かりません」という答えになります。
クライアントの例:能力を取り戻すのに6年かかった
動画 14:46 でご紹介しているのは、山田のクライアントです。
この男性は、発症から半年で左手がほとんど動かない状態でしたが、6年もの間、ほぼ毎日リハビリを続けることで、ペットボトルを握って手を動かせるようになりました。
強い麻痺の影響で回復には時間と根気が必要でしたが、潜在能力はあったため諦めずに努力を続けた結果です。
リハビリは学習と同じで、時間と根気が必要であり、積極的に取り組む姿勢も重要になります。
誤学習を上書きして修正する
先に述べたように、早期に歩けるようになっても、不安や恐怖で代償パターンが強まり、長期増強として誤った動きが固定されることがあります。
この背景には、病院で経験した不快な出来事や人間関係、療法士や医師との相性、病気に伴う情動なども含まれます。
正しい動きを取り戻してリセットするには、過去の感情や経験を棚卸しながら、本来の動きやすい動作を身に付けるアプローチも大切と思います。
「正しい動作」を何度も練習して上書きするイメージです。
(※正しい…と言う表現も誤解を招くことが多いですが)
ご自身の身体の状態に合わせ、丁寧な感覚のフィードバックも確認しながら、適切なリハを行うことで、動きやすい身体へと変容させるのは可能と個人的に捉えています。
つまるところ、回復の速さや質は、脳の損傷度合や出血量だけでなく、「学習過程・学習環境」が非常に大きいウェイトを占めているような気がします。
早いうちからリハを始めても…実感としては変わらない!?
とは言え、理想的な環境でリハビリを続けるというのは難しい事でもあります。
病院に入院中なら尚更です。
仮に、発症から数年経過していても、改善する余地はあるので、あまり悲観的になり過ぎる事もないです。
僕の知り合いの「超急性期」の患者さんのリハを担当しているセラピストの先生が、こんな事を言っていました。
「文献では、リハビリはできるだけ早いうちに始めた方がいいって書いてあるけどね、実感としてはあんま変わんないよ。やっぱりひとつ、ひとつ丁寧にやっていくのが王道。患者の認知力を考えながら練習した方が、最終的にいい回復を示すんだよね。」
論文では早期リハビリの効果が謳われていますが、「個人の状況に合わせてデザインをしてあげないといけない」というのが臨床の現場での実感です。
上記の先生のつぶやきは、『臨床家』であるからこその本音でもあるのでしょう。
経験豊富な専門家が必要とされるので、皆が簡単に出来る事ではありません。
しかし、諦めずに良い先生を見つけ、焦らず自分に合った丁寧なケアを続けることが、回復への近道だと言えるでしょう。
動画内容・チャプター
0:34 脳卒中からの回復レベルに差が出る理由
1:46 シナプス(脳)の可塑性(かそせい)
4:36 学習の結果・誰しもが持っている能力
5:06 脳卒中になると次の細胞へ指令が届かない
7:19 神経伝達物質
9:40 弱い繋がりがマヒのように見える
11:37 ゆにこさんからのご質問(ぶん回し歩行)
14:46 山田クライアントの写真(能力を取り戻すのに6年)
16:35 学習なので時間と根気が必要
17:50 長期増強が代償パターンになる場合も(誤学習)
19:46 丁寧な感覚フィードバックが必要
20:58 長期増強、長期抑圧はどちらも正常な機能
21:41 回復スピードの違い→学習要素は大きい
23:42 早いうちからリハを始めても…実感としては変わらない!?
25:26 学習が阻害された経験も影響
26:20 山田の話は長いです(笑)