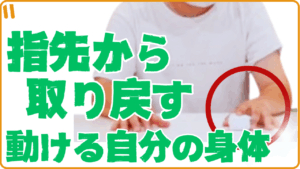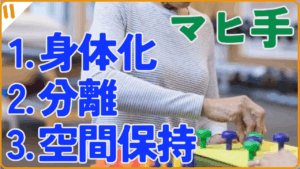【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢⑥】8割以上の方の麻痺手は動くようになるの根拠とは・「手首が曲がったまま伸びません」というコメントにお答えします

先日「8割以上の方の巻き手は動くようになりますよ」という動画を投稿いたしました。
その際、かず(kazu)さんという方から、「自分は手首が曲がったまま伸びません」というコメントを頂戴しました。
今回はこのコメントに回答する形で、「半球間抑制」と「姿勢コントロール」について解説しようと思います。
動画冒頭では、僕が今取り組んでいる活動や法人化の構想についてのお知らせもあります。
目次
手首が曲がったまま伸びない
かずさんのコメントの主旨は、「手首曲がったまま、指先使えず練習ができない」という意味かと思います。
「手首が曲がったまま伸びない」という状況をどうするのかというのを踏まえ、『8割以上の方がなぜ手が動くようになる』と僕が言いきれる背景について話をしようと思います。
“腕や手首が曲がっている状況”というのは、右側の脳に梗塞なり出血なりがあって、右側の脳が今十分に働いていない状況です。
この脳が働かないという状況は、「脳が寝ちゃってる状態」だと捉えています。
寝ちゃってるんだから動くわけねえじゃんというのが、基本的に僕の考えていることです。
現実的には筋肉が硬くなっているから、伸びなかったり、開かなかったりします。
でも、ちょっと考えてみてください。
先ほど言ったように、脳梗塞や脳出血によって、左側の手足を動かす右側の脳がうまく働いていません。
私はこれを「脳が寝ている状況」だと理解しています。
脳の損傷=脳が寝ている状態
では「寝ている状況」とは何でしょうか?
専門的な用語で説明すると「半球間抑制の異常な状態」なのではないかと考えています。
半球間抑制とは
半球間抑制とは、脳の左右の大脳半球がお互いに情報をやり取りしたり、抑制し合ったりする仕組みのことです。
脳には右側と左側があり、脳梁(のうりょう)という部分で繋がっています。
右脳と左脳はそれぞれお互いに感覚や運動などの情報を処理し、色々なことを脳梁を通して伝え合っています。
食事における左右の脳の働き
食事を例にあげます。
多くの場合、僕たちの意識は箸を持っている右手に向けられています。
箸が口元まで届くかどうか、注意しないといけません。
反対に、お茶碗を持っている左手には、右手ほど注意を向けていません。
このとき脳の中では何が起こっているのでしょうか?
右手の動きを司っているのは左側の脳なので、左側の脳は右手で箸を操作することに集中し、活動が高まっています。
一方で、左手を司る右側の脳は、左手にあまり注意が向いていないため、左側の脳に比べると活動は少し低めになっています。
このメカニズムを「半球間抑制」と言います。
半球間抑制では、右半球と左半球の脳がお互いに情報をやり取りしながら、「片方の活動は高めて、別の方の活動は低める」という調整も行っているのです。
この仕組みのおかげで、僕たちは右手も左手も自由に使うことができるわけです。
半球間抑制が異常になると…
半球間抑制が異常になるとどうなるでしょうか?
脳梗塞や脳出血で右側の脳に損傷が生じ、左半身に麻痺が起きた場合を考えます。
左半身を動かす右脳の活動が極端に低下し、反対に左脳の活動が過剰に高まる「過剰興奮」が起こります。
正常なら80kmで動くはずの車が、アクセルを踏みすぎて120kmになってしまうようなイメージです。
左脳がバンバン活動している一方で、右脳の活動は極端に落ちてしまいます。
僕はこの状態を「右脳が寝ている状態」と理解しています。
これを確実に証明するには、fMRI(機能的MRI)などの専門的な検査が必要で、臨床現場では脳内で何が起きているか正確には分かりません。
ですので、これはあくまで「仮説」として理解してください。
半球間抑制が異常になると、右脳の活動はもともと低いところからさらに低下し、結果として手が動かない状態になるのだと僕は考えています。
手首が曲がったままで伸ばせないのは、筋肉が局所的に硬くなっているからですが、大本の原因として、脳の影響で筋肉の活動自体が低下していることも関係していると捉えています。そして、それは「姿勢の調整」に起因しています。
姿勢コントロール(両側性)
次に、「姿勢の両側性コントロール」という話をします。
僕が今立ちながら話している状態や、ホワイトボードに字を書きながらカメラに向かって話し続けているような、「中途半端な姿勢」を保てているのは、姿勢コントロールのおかげです。
「姿勢コントロール」は両側性の制御機構です。
左側の脳は右と左の両方の姿勢筋に指令を送り、右側の脳も右と左の両方の姿勢筋に指令を送っています。
従って、脳の片側が損傷しても、もう片方の脳が正常に働いていれば、一般的には姿勢コントロールには大きな障害は出ないと言われています。
姿勢の自動調整を左右の脳が協力してやっているため、片側の脳がうまく働かなくても、基本的には姿勢コントロールは保たれます。
しかし、先に言及した「半球間抑制が異常になる」と姿勢制御に問題が出てきます。
片方の脳の過剰興奮が姿勢に与える影響
損傷により、右脳が寝ている状態にある中、左側の脳は80km制限のところを120kmで暴走している、つまり過剰興奮の状態にあります。
だから損傷を受けていない左側の脳も「普通」ではないのです。
左側の脳が正常に働いていないのなら、当然、その左側が司っている姿勢コントロールも正常ではなくなります。
これを理解せず介入してしまうと、見当違いのリハビリを行ってしまうリスクに繋がります。
脳卒中のマヒは麻痺側(片方のみに)に出るというのが一般的な理解なので、麻痺側だけに体重をかけた練習をしてしまう療法士や当事者の方が多いです。
本来であれば、両側にバランスよく体重をかけて支えられること、そして、過剰に頑張って暴走している左側の脳が落ち着くことが必要なのです。
左側の脳が「もうちょっとリラックスして楽に活動すればいいんだ」と気づけることが大切ですが、これがなかなか難しいのです。
8割のマヒ手は改善する
やみくもに麻痺側に力を入れて荷重することではなく、まず脳の興奮状態を落ち着かせることが大切です。
脳の右半球が「寝ている」状態であることが原因なので、起こすのは容易ではありません。それなら、過剰に興奮している左側の脳をなだめる方が効果的です。
テーブルの上に右手を軽く置いてリラックスし、左手の指先の感覚をしっかり感じ取ることで、左右の脳の活動バランスが整いやすくなります。寝てしまっている右側の脳も少しずつ目を覚まし、感覚が戻りやすくなり、手足の動きも改善されます。
また、動画で再現しているように、手首が曲がってしまうのは、身体が傾いて腰の筋肉が張ることで肩関節が内側に引っ張られ、それが連動して手首などの末端が曲がってしまうからです。
ここにも姿勢コントロールの影響が出ており、右側の脳が寝てしまっている事が関与しています。こうした状況でも、過剰に興奮している左側の脳をなだめる介入を優先的に行います。
発症後、だいぶ時間が経って筋肉が硬くなっている場合は、まず筋肉を伸ばす環境を整えてからケアする必要があります。
このような考え方とアプローチによって、8割以上の脳卒中片麻痺の方でマヒ手が動きやすくなり、改善が期待できると考えています。
法人化に至ったワケ
現在、臨床で20%くらいのパフォーマンスしか出せていない若手の療法士達に対し、僕が臨床で蓄積してきた知見をマニュアルとして共有することで、60%ほどの実力を発揮できるようになれば、より多くの患者さんを助けられるようになると思っています。
法人化した理由は正にこれです。
僕は自信を持って能力の8割の力を発揮できますが、多くの療法士は自分の力を存分に発揮出来ていないように見て取れます。
彼らが臨床能力を高めることで、より大きな効果が期待できるリハビリを受けられる当事者の方が増えるといいなと信じ、法人化を通じた認定・マッチング制度を構想中です。
動画内容・チャプター
0:33 手首が曲がったまま伸びない悩み
1:19 脳の損傷=脳が寝ている状態
4:43 手首が伸びない原因は筋の硬さではない?
6:00 半球間抑制とは
10:40 半球間抑制が異常になると…
11:40 脳が寝ている状態
13:20 姿勢コントロール(両側性)
15:27 片方の脳の過剰興奮が姿勢に与える影響
16:06 両側で支えられるのが重要
16:57 マヒ状況を再現
18:04 過剰興奮を抑えて脳を落ち着かせる方法
19:01 手首が曲がるメカニズム(姿勢の影響)
20:05 脳の過剰興奮を抑える方が効率的
21:30 理屈を理解していないとリハの方向性を見誤る
22:15 法人化に至ったワケ