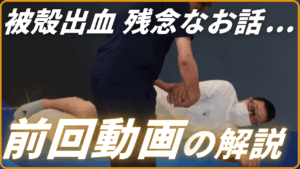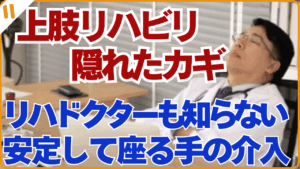【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢①】あなたの手が上がらない理由は?身体構造から原因を探る・麻痺の部位が違うワケ
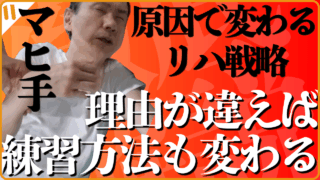
前回までお送りしてきた「被殻出血シリーズ」は一旦完了とし、今回からは「麻痺側上肢」について解説していこうと思います。
「マヒ」と一口に言っても原因や出現部位は人それぞれであり、原因要素に基づいてリハビリテーション戦略を策定する必要があるという事を、初回の概略としてお伝えしようと思います。
目次
麻痺側上肢の困り事
脳卒中片麻痺の方で、上肢が思うように動かせずに困っている方が多いと思います。
その内容をいくつか例をあげてみます。
①動かない・動くけど使えない
②感じない・感覚が無い(注意が向かない・分からない)
③痺れている
④痛む
⑤腕や肩が重い
マヒの種類
麻痺側上肢がなぜ動かないのか、また、その理由を踏まえてどういう練習が自分には必要なのかを考えてみます。
先ずはざっくり「マヒ」の種類をおさらいしてみましょう。
末梢神経損傷によるマヒ
末梢神経(まっしょうしんけい)は、脳や脊髄から全身に伸びており、運動、感覚、自律神経の機能を担っています。
末梢神経が何らかの原因で損傷を受けると、筋肉に対する司令が行き届かなくなるので麻痺が生じます。
脊髄損傷・完全マヒ
脊髄損傷(せきずいそんしょう)とは、末梢神経(まっしょうしんけい)が出ている大元の神経の束が損傷する事です。
脳からの司令を身体に伝える「脊髄(せきずい)」が損なわれることで、運動機能や感覚に障害が起こります。
損傷した部位より下の神経に命令が届かなくなってしまうので、全く動かない「完全マヒ」になることがあります。
例えば、首の部分(頸髄)が損傷されると、全身の運動機能や感覚に影響が出る可能性があります。背中や腰の方(胸髄や腰髄)の損傷では、下半身に影響が出ることが多いです。
脳の損傷によるマヒ
脳卒中片麻痺は、脳の損傷が原因で何某かのマヒが出ている状態です。
脳の損傷なので、基本的には『脊髄も末梢も生きている』はずです。
ただ、一部の機能が欠落してしまったために不全マヒが生じます。
末梢が損傷していないので、末梢から刺激を与える腱反射(けんはんしゃ)は多くの方が維持しておられます。腱反射とは、腱の伸長によって筋の緊張状態が変化する反射の事を言います。
脊髄から先の神経は生きているので、筋肉そのものも生きているワケです。
脳卒中片麻痺で、完全マヒになるのは考えにくいと個人的に捉えています。
弛緩性麻痺と痙性麻痺
脳卒中片麻痺では、末梢の随意性が乏しくなり、手足が動かしづらくなったりします。
この背景にあると考えられるのが「司令と調整」という機能です。
「司令」は、脳から「運動して下さい」という信号が末端まできちんと届いているか否かという状態です。
「調整」は、脳からの司令は届いているが、うまく調整ができずに硬くなったり、思うように動かせなくなるという状態です。
「司令系の障害」では弛緩性マヒ、「調整系の障害」では痙性マヒが出ます。
身体構造の問題でマヒ手が動かせない
マヒ手が動かない要因を考える際、身体構造を踏まえるのも大切です。
腕は肩甲骨から先の部位を意味します。手や腕を空中に上げるためには、肩甲骨の周りの筋肉がきちんと働いて、肩甲骨が手や腕を身体に引きつけておいてくれないと不安定になりブラブラして上がりません。
肩甲骨周囲の筋が働くためには、お尻や胴体の筋肉が正常に働くことが欠かせません。お尻や胴体の筋が働かないと、動きそうなのに動かなかったり、肩が重くて下がってしまう…といった問題が出てきます。
自分の肩が重く感じる原因は肩甲骨周囲に存在するのですが、更にそこから大本を辿ると、お尻の筋肉や胴体の筋肉がうまく機能していないという事実に突き当たります。
こうした原因から、マヒ手が上がらないと訴える方も少なくありません。
上肢の問題では事前準備が欠かせない
麻痺した上肢の機能改善を目指すためには、まずその原因や身体の状態、麻痺のタイプなどを正確に見極めることが必要です。
いきなり手を動かす練習を始めたり、やみくもに筋力トレーニングを行ったりしても、期待した成果が得られないことがあります。そうした無駄を避けるためにも、適切な準備段階が欠かせません。
僕のリハビリ講座でも繰り返しお伝えしていますが、準備の一環として、「立つ・座る」といった基本動作の練習が大変重要になります。
こうした基礎的な動作を通じて、はじめて肩甲骨周囲の筋肉が働ける環境が整ってきます。例えば、両脚でしっかりと体重を支えて立ち座りができるようになったり、お尻の筋肉が自然に使えて、座るのが以前よりも楽に感じられるようになったり、身体の揺れが減って安定感が増したと実感できるようになったりすることが大切です。
このような変化の背景には、「身体の構造的な問題」が関わっており、構造に着目することで、多様な練習方法が選択可能となります。
準備と練習を丁寧に重ねることで、結果的に肩甲骨の周囲の筋肉がしっかりと機能しはじめ、マヒした手の動きが改善されます。このようなケースは、臨床で頻繁に観察されます。
原因に応じてリハビリの戦略は変わる
皆さんのマヒ手に関しては、「どのレベルで動きづらさが出ているのか」によってリハビリの介入方法や実施すべき練習は変ってきます。
前回の動画でも言及したように、リハビリでは直接お身体を拝見し、評価した上で最適な提案が可能になるので、万人に向けた動画配信で、どこまで切り込んだ提案ができるかは未知数です。
皆さんにマッチした的確な練習になるかどうかは確約できませんが、麻痺側上肢のリハビリを実践する上での「考え方」には触れて頂けると思っています。
より詳しい解説をしていきますので、また来週お会いしましょう♪
動画内容・チャプター
0:43 被殻出血シリーズは一旦終了
1:19 自分のマヒの種類を理解しておく
2:01 麻痺の部位が違う
4:14 抹神経損傷によるマヒ
5:00 脊髄損傷・完全マヒ
5:41 脳の損傷・不全マヒ
6:52 脳中の完全マヒは考えにくい
7:25 司令と調整
7:50 司令系:弛緩性マヒ
7:55 調整系:痙性マヒ
8:44 身体構造の問題で手が動かせない
11:04 クッションを使った自主トレ
11:30 上肢の問題では事前準備が欠かせない
12:42 原因に応じて練習が変わる