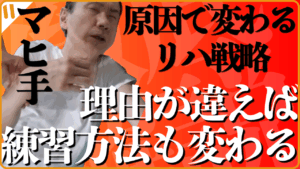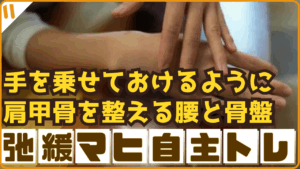【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢②】3つの要因 麻痺側上肢の潜在能力が発揮できない理由・病院で上肢に介入しない現状・廃用症候群
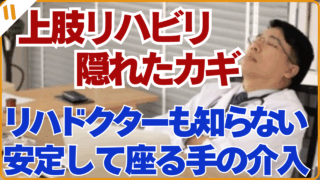
麻痺側上肢のポテンシャルを活かせない要因3つについて、急性期・回復期病院で積極的に上肢介入しない現状に触れつつ解説していこうと思います。
マヒ手は療法士が介入したからと言って治せるものではなく、改善こそ目指せるものの、何が麻痺手の原因になっているのか見定めないといけません。そう言った意味で「やってみないと分からない」というのが実情です。
目次
なぜマヒ手の潜在能力は引き出せないのか
脳卒中片麻痺の方で、マヒ手を動かせる能力が眠っているものの、それが「潜在能力」に留まり、具現化しないのは何故なのか?
こうした疑問を突き詰めて考えると、急性期・回復期において、早期から麻痺側上肢に介入する必然性があるという結論に至ります。
ところが、昨今の日本のリハビリテーション医療では、ADLの向上や日常生活への復帰、早期退院を第一と捉える風潮があるため、「マヒ手」に対する入念なリハビリがおろそかになっているように見て取れます。
加えて、医師によるムンテラ(病状や今後の治療方針などを説明すること)で、患者や家族に対して過度な期待を抱かせないよう、「寝たきり」など、最悪の事態を想定した発言がされる事もあるようです。
当事者の方やご家族としては、マヒ手の事なんていいから、とにかく歩けるように、最低限の日常生活が回せるように、先ずは脚の練習をして欲しいという方向に意識が向いてしまいます。
しかし、退院して暫く経つと、マヒ手が使えない事の不自由さを痛感され、「やっぱりマヒ手が使えるようになりたい」と願うようになる方は多いという印象を抱いています。
①下肢の支えがないので手が動かない
マヒ手の潜在能力が発揮できない要因として3つあげてみました。
まず第一に、「下肢・体幹の支えがないために麻痺手が動かない」というのがあります。
下肢が動かないので上肢が動かない。
この順序で考えると、「とにもかくにも、歩けるようにしたい」とう思考になるのは、あながち間違いではないです。
真っすぐに立ち、安定して身体を起こしておけるというのは、手や腕を動かすための重要な要素になります。
座るために麻痺手に介入する
脳卒中の発症初期では、麻痺側の手や脚がブランブランで、安定して座っていられない状況になる事があります。
この段階では、手の能力よりも、まずはちゃんと座っておける事が重要という判断になるでしょう。
これに対して、麻痺側上肢に介入することで、バランスの取れた状態で座ることができるようになります。
これは、あまり知られていない事実です。
体幹や座位のスタビリティに対して麻痺側上肢への介入が効果的である。
この「ノウハウ」は周知されておらず、リハビリテーション科の医師ですら知らない方も多いようです。
勉強熱心で最新の情報に触れている若手の療法士がこうした「使えるノウハウ」を入手した所で、病院の運営トップにあるドクターや先輩療法士がこのことを理解していなければ、思うようなリハは出来ないかもしれません…
手の重さが歩行に大きな影響を及ぼす
脳卒中片麻痺の方で、「歩く練習をいっぱいすれば、自由に歩けるようになる」と少し勘違いされている方がおられます。
マヒ手や腕の重さが支えられず、身体が前に潰れてしまうので、麻痺脚が効率的に動かせないという事が多々あります。
この事はリハビリ現場でもお伝えしているのですが、なかなか理解して貰えません。
脳卒中という病気から、認識・判断力が制御できなくなっているという側面もあるでしょう。
②筋が伸びてしまう
マヒ手の潜在能力が発揮できない2つ目の要因は、「筋が伸びてしまう」事です。
ヒトの脚は、地面を踏んづけて身体を支えていなければならない部位なので、ずっと力を出し続けています。
反対に、ヒトの手は、空中に置かれている事が大半です。ブランと身体から垂れ下がっているので、手が動かなければこの首から肩についてる筋肉や、胸から肩についてる筋肉は伸びきってしまいます。
一定レベルを超えて伸びきった筋は、もうそれ以上収縮しなくなり、筋が働かなくなってしまいます。
この「伸びきる・力が発揮できない」という状態は、1週間2週間単位で生じます。
脳卒中を発症し、病院で1週間安静状態になると、肩回りやお尻回りなど、「中枢部」と言われる筋群が15%減少すると言われています。
1週間で15%なので、2週間なら30%の低下。数ヶ月なら…それ以上です。
これを「廃用性萎縮」と言います。
筋力低下を防ぐために、急性期や回復期のでできるだけ早いうちにリハビリを開始し、上肢機能に欠かせない肩回りの筋にアプローチするのが望ましいのです。
しかし、先に述べたように、安定的に座る事や麻痺脚に荷重して歩く事などが優先されるため、上肢への介入は後回りにされる傾向があります。
すると、上肢を支えきれない筋肉はどんどん重さに引っ張られて伸びてしまいます。
筋委縮が進んでしまい、潜在能力が発揮されないままとなります。
手の練習に入るには必ず認識を使う
こうした時期は、当事者の方が、「マヒ手を自分の手として認識するのが難しい時期」でもあります。
手の機能は、認識に直結します。
脳卒中片麻痺の方が手の練習に入るには、必ず認識を必要とします。
何気なく動かしてるうちに段々できるようになった、というのは殆どありません。
ご自分の手が認識できるという事は、感覚や知覚・運動主体感・自己所有感・身体所有感を得る過程が必ず必要です。
③学習性不使用
また、手のリハビリには大変なエネルギーを要します。
手の練習に割くエネルギーは、マヒ脚を踏ん張る練習に比べて圧倒的に多い。
発症初期で意識がぼーっとした中、環境が整わないままリハビリをさせられたりして、思うような効果が出なかったり、膨大な労力だけが消費されると、嫌気がさしてきます。
麻痺側上肢のリハが二の次になり、日常生活でも利用する機会がなくなった結果、「学習性不使用」に繋がります。
「学習性不使用」とは、脳卒中などの後遺症により手脚に麻痺が生じた後、使わない状態が続くことで、「使わないこと」が習慣化され、結果的に脳がその部位の使用を避けるように学習してしまう現象です。
当初から、自分の手を認識できていない事も相まって、なかなか練習しづらいというのもあり、自分の手ではないと思うようになる「他人の手症候群」のようになる方もおられます。
マヒ手を取り巻く状況は、二重にも三重にもリハビリに取り組みづらいものとなります。
発症後だいぶ経過してから、「マヒ手を何とかしたい」と思うようになりますが、その段階では「手遅れ」になっている事もあります。
ここで言う「手遅れ」というのは、「能力があるにも関わらず潜在化して深く潜りこんでいるので、可能性を掘り起こしてくるのが大変になる」という意味です。
マヒ手はやってみないと分からない
上肢リハビリにおいて、僕たち療法士が麻痺を治せるワケではありません。
「動かない」という背景に、本当に麻痺が絡んでいないのかどうかも判断しなくてはいけません。
しかし、これは実際にリハビリ介入してみないと分かりません。
脳画像で、手の領域が完全に死滅しているように見える方でも、手は動く方います。
これとは反対に、上肢が麻痺されている方で、確かに「内包後脚(ないほうこうきゃく)」まで障害が及んでいる事がハッキリ見られる方もいます。
このように、障害像や重篤度、リハビリ効果は人それぞれで、やってみないと分かりません。
「こういう練習をしたら必ず良くなりますよ」とは言い切れないのです。
こういうレベルで、こうした傾向のある方は、こんな練習をしてみると、比較的改善する可能性はあるだろう…という僕の臨床経験ならお伝えできます。
今後の配信では、そうした事をメインにお伝えしていく予定です。
動画内容・チャプター
0:56 潜在能力がなぜ発揮できないのか
1:31 回復期病院で上肢に介入しない現状
3:40 ①下肢の支えがないので手が動かない
4:41 真っすぐ座るために麻痺手に介入した方が効果的
7:33 歩く練習をすれば歩けるようになると思っている
8:27 ②筋が伸びてしまう
9:50 中枢部の筋は15%落ちる
11:10 自分の手として認識することも難しい時期
12:50 手の練習に入るには必ず認識を使う
14:08 ③学習性不使用・他人の手症候群
15:52 療法士が麻痺を治せるワケではない