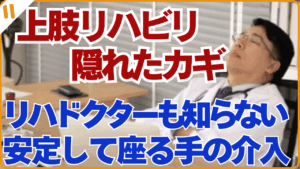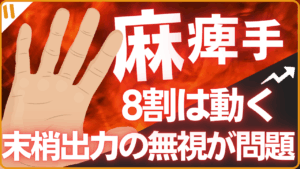【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢③】弛緩性マヒ・肩甲骨の状態を整えるための腰と骨盤周りの練習・上肢の自主トレの要は姿勢です!
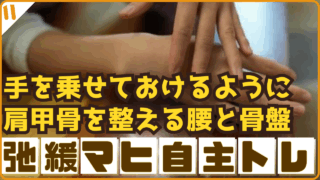
今日は、主に弛緩性マヒの方を対象とした、上肢自主トレをご紹介します。
マヒ手をテーブルに上げておくのが難しい方がメインの対象です。
最終目標は「手の随意性を高めること」ですが、前段階として、肩甲骨の状態を整えるための“腰や骨盤周りの練習”を提案したいと思います。
10:54 から「全体のまとめ」が始まりますので、チャプターをクリックしてご覧下さい。
目次
準備するもの
1. クッションか枕
2. ハーフポール(半月ポール/ストレッチポール)
サランラップの芯とタオルでも代用可
解決したい事は何か?
この自主トレの最終目標は、マヒ手の動きを良くしたり、随意性を高めるという事です。
最終目標に至るまでには複数のステップがあり、事前にやらなければいけないことがいくつかありますが、途中経過の問題は皆さん共通しています。
自主トレでは、肩甲骨や骨盤周りの問題を解決・改善するのを目指します。
肩甲骨を整え、腰や骨盤周りを使う
肩甲骨の状態を整え、腰や骨盤周りを使う練習をします。
主に弛緩性マヒの方で、手をテーブルの上に乗せておくと、後ろに落っこちてしまうという方は、是非この練習をしてみて下さい。
こういう方は、座っている時に背中がクチュンと潰れていることが多いです。
骨盤がねじれてしまっていて、手をテーブルの上に置くための、身体横の線が整っていないからです。
この横線を整えるのに、ハーフポールをお尻の下に置いて使います。
良い姿勢に対する誤解
ハープポールとクッションを使った自主トレを実施する前に「良い姿勢」に関して、皆さん誤解されている事があります。
『いい姿勢を取りましょう』とお伝えすると、皆さん椅子に座って、背中をぐっと張る体勢を取ってしまいます。
後ろにのけぞるような姿勢は望ましくありません。
背中を張るのではなく、「腰・骨盤を起こす」という意識が大切です。
椅子に座った状態でハーフポールの上に乗っかったら、一度ストンと腰を後ろに降ろして構いません。
背中を丸くした状況で前後に体重移動してみると、ああ、ここにお尻がある!という感覚が得られるスポットがあるはずです。
“自分のお尻があったわ”という感覚は、硬い骨が当たる感覚です。
お尻には「坐骨結節(ざこつけっせつ」という骨の塊があります。「座骨結節」に自分の体重をちゃんと乗せるのが重要で、ここに体重が乗ると、身体は起こしやすくなります。
「肩をちょっと上げる」というのをイメージしてやってみて下さい。
練習課題
ハーフポールかラップの芯とタオルを下に敷いて、お尻の上にふわっと乗っかったら肩を起こす。
これが今日の練習課題です。
座れるようになったら、脇が十分に前に開くようにして、マヒ手をテーブルの上に乗せ続けておくことができるように練習してみます。
マヒ手をテーブルに上げておくことが難しい方は
麻痺側上肢をテーブルの上に上げておくことが難しい方は、姿勢が崩れていたり、脇が開いていない可能性があります。
加えて、ご自身の手そのものが分かりづらくなってる方も多いです。
感覚が乏しい状態で、変な緊張を抱えたまま身体が沈み込み、筋肉に引っ張られてマヒ手がズルズルと落ちていってしまう…
こうした状況を改善するのに、先ずはしっかりとお尻の上に乗ったら肩を上げるっていうことをやってみて下さい。
中には、麻痺側の肩を上げるのが難しいという方もいると思いますので、そういう場合は、非麻痺側の手でマヒ手を持ち上げ、軽くクッションの上に叩きつけてみて下さい。
すると、ご自身の手の存在が分かると当時に、背中の緊張が落ちてきます。
健側の手で、麻痺側の手や腕を持ち上げるのが難しい方は、非麻痺側の手でマヒ手や腕を軽く叩いたり、さすったりして刺激を与えるのでも構いません。これを「タッピング」と言います。
マヒ手の感覚を脳が受け取って、その結果として、筋肉はこうやって働かせて下さいという信号を身体に出力する事になります。
脳がマヒ手に対して注目できるようになると、不思議と身体は起きてきます。
全体のまとめ
①テーブルの上にクッションを乗せる
②椅子の上にハーフポールを置く
(ラップの芯にタオルを巻いたものでもOK)
③その上に座る
④腰をストンと後ろに下ろして余計な力を抜く
⑤頭の重さを使って前後に揺らし「お尻の位置」を把握する
⑥肩をちょっと起こす(健側の肩だけでもOK)
⑦非麻痺側の手でマヒ手を持ち上げてクッションを叩く
マヒ手をさすったり、軽く叩いたり、つねったり、何らかの刺激を与える
⑧マヒ手に注意が向き、脳や身体が感覚を受け取る事ができるようになる
この自主トレで肩甲骨の状態を整え、腰や骨盤周りを使うことができると、身体が自然と起こせるようになります。
脇が開いて、背中の筋が潰れるのが防げるので、身体の横の線が整う事が期待できます。
次の練習に進むための準備
この自主トレによって、全員のマヒ手がテーブルに置いておけるようになる…とはいきません。
練習もたった1回でできるようにはならず、1週間や2週間程度は継続する必要があるでしょう。
出来る範囲で継続することで、ご自身の手の存在に意識を向けることができるようになり、段々とテーブルから落ちなくなってくるのが実感できると思います。
この段階に来たら、次の練習に入れるサインです。
痙性マヒの方は来週以降の動画
今日の自主トレは「弛緩マヒ」の方を想定してします。
「痙性マヒ」の方で、手や腕が曲がって固まってしまい、前に出すのも難しいという方を対象とした自主トレは、来週以降に発信できればと思っています。
動画内容・チャプター
0:22 初期の頃のリハビリの復習
0:43 解決したいのは何か?(共通項)
1:18 ハーフポール・ストレッチポール(ラップの芯)
2:35 クッション
2:48 肩甲骨の状態を整える:腰・骨盤周りの練習
3:05 実践方法解説
3:54 良い姿勢の誤解
6:38 ラップで代用する場合:座骨結節が前に来るように
7:29 脇が十分に開いていない
7:59 段ボールにタオルを乗せる方法でもOK
8:22 マヒ手をテーブルに上げておくのが難しい方
9:17 クッションの上にマヒ手を叩きつける
10:49 信号を出力することで身体は起きてくる
10:54 全体のまとめ
12:17 弛緩マヒの方向け・痙性マヒは次回以降で