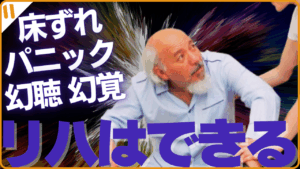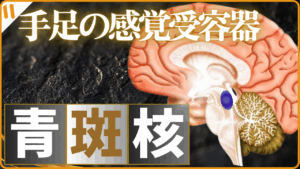【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血⑤】被殻出血の後遺症が重篤になる背景・筋緊張/トーンが変化しないのが問題
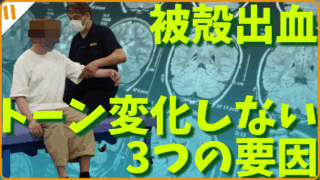
今日は、被殻出血の方で「トーンが変化しないのが問題」というお題で、動きづらさの背景を探っていこうと思います。
例によって、前置きや回り道が多いですが、結論は「トーン=筋緊張が変化しない事が動きづらさの背景にあり、脳機能の全体・左右・上下の3つの要因を考えることが重要」という事です。
目次
脳卒中データバンク
僕のスタジオにお越し頂くクライアントには被殻出血の方が多いです。
この理由は定かではありませんが、「Let's ケーススタディ」に掲載している症例も被殻出血が多くなっています。
以前に配信した動画「【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血①】マヒが原因ではない!」では、「日本脳卒中データバンク」の報告書をご紹介しました。
https://willlabo-blog.com/?p=997
国立循環器病研究センターが公表している「脳卒中データバンク」の2024年の報告書によると、 脳卒中の中で脳梗塞が占める割合は4分の3で、約72%となっています。
残り4分の1が脳出血で、被殻出血は脳出血のうち3分の2程度です。
つまり、脳卒中のうち、被殻出血は20%程度となります。
被殻出血は後遺症が残りやすい傾向
日本脳卒中データバンクによれば、脳梗塞を発症した人で、急性期病院から回復期病院へ移転した人は、全体の約3割だそうです。
脳梗塞を発症した約7割の人は、症状は比較的軽度であったために、急性期病院から回復期病院へ転院せずに退院したという事です。
一方で、被殻出血の方は、半数以上の方が、急性期病院から回復期病院へ移転しているとのこと。脳梗塞の人よりも、被殻出血の人の方が、発病後の状態が芳しくないという事です。
個人的な経験ベースになりますが、僕のスタジオにいらっしゃる被殻出血の方も、後遺障害が残りやすいなと理解しています。
トーン=筋緊張が変化しないのが問題
被殻出血で後遺障害が重くなってしまう要因の一つに、「トーンが変化しない問題がある」と考えています。
「トーン」というのは「筋緊張」と表現されます。
通常、ヒトの筋肉が働くための力を「筋力」と呼び、筋肉自体が持っている力を指しますが、それに対して、「筋緊張」は、筋活動の量を変化させることで関節運動を起こすものを言います。
自動車に例えるなら、筋緊張はエンジンを回しているアイドリング状態で、活動を継続させながら、活動量をコントロールすることで運動機能を制御しています。
筋緊張がないと、筋力は発揮されません。
よって、筋力を考える前に、筋肉がずっと持続的に働いている状態の「安静時筋緊張」を保つが不可欠になります。
筋緊張の制御
筋緊張がそもそも変化しない「低緊張」状態が続いたり、痙縮などで筋が硬くなってしまう「高緊張」状態もあります。
高緊張では、エンジンがすっと高回転で回っているのを同じで、関節や筋が変化しないので、動きにくさに繋がっていると認識しています。
これらはあくまでも、僕の臨床上の経験から考察している事なので、個人的な理解の粋は越えませんが、メカニズムに関して色々な見解はあれど、実際に脳内を観察する事はできないので、どうなっているかは誰にも分かりません。
トーン=筋緊張が変化しない3つの要因
トーン=筋緊張が変化しない事に対して、3つの要因に分けて考えてみましょう。
①脳全体の機能不全:浮腫・炎症
脳梗塞や脳出血の発症初期では、脳全体が浮腫(ふしゅ=むくみ)を起こして炎症が生じます。
炎症は傷を治すのに必要な過程ですが、脳機能を低下させることに繋がる場合があります。
また、血流が悪くなって循環が滞ることで、脳が浮腫を起こします。
脳がむくむと、脳内の内圧が亢進します。
脳の内側から外側に押す圧力が強くなり、脳がむくんで大きくなると、頭蓋骨に脳が押し当てられ、押し当てられた脳の機能は低下します。
すると、脳卒中の発症初期は非常に重得な状態になります。
脳浮腫や炎症が徐々におさまってくると、生命を維持しなければならない緊急の状態から、段々と意識も回復してきます。車椅子に1人で乗っていられるようになるなど、一定レベルで身体機能が回復してきます。
②脳の上下間の機能差:小脳や脳幹にも影響
急性期から回復期病院に移り、本格的に身体を動かすフェーズに移行するワケですが、全体的な脳機能が落ちている状況の時では、脳の表面の一番上にある「大脳皮質」だけではなく、小脳や脳幹にも影響が及ぶケースがあります。
脳圧更新で脳が膨れ上がり、大脳以外に小脳や脳幹までもが、頭蓋骨にあたって押し潰されると、こうした器官も機能不全となる可能性が出てきます。
急性期に手足が動かないのはマヒだったか?
急性期で麻痺手足が動かないのは、本当の意味で「マヒ」だったのか、それとも、一時的な脳圧の亢進や炎症によるものだったのか…
脳圧や炎症がおさまると、自然に手足が動くようになる方もいますし、この時期のコンディションによって将来的な予後も変わってきます。
僕は「ボバース・コンセプト」を習得してきたセラピストなので、リハビリにおいて『麻痺側の上下肢に介入しない』という選択肢はあり得ません。
③脳の左右間の機能差:麻痺側の脳は寝ている
脳には左右間の機能差があるという事も麻痺側上下肢への介入に関係しています。
被殻出血で手足が動かなくなる原因は、被殻が損傷された事によって生じるというよりも、脳圧の上昇や炎症によって押し潰された大脳皮質や小脳、脳幹が、正常に機能していないために起こっている事もあります。
これらの器官に対しても介入しないと、左右間で脳機能に差が生じる事になります。
その一つの例が、大脳基底核です。
大脳基底核によるブレーキ
基底核は、周囲の状況に応じて動作にブレーキをかける働きをしています。
横断歩道を渡る際、信号が赤になったり、向こうから車が走って来たりすると、「歩行を開始しないで」という命令が基底核から発せられます。僕たちは、歩ける能力は保持していても、「歩き出したら危ない」という判断が下り、動きを止めます。
信号が青に変わり、周囲の安全か確認できると「歩きだしても大丈夫」という判断が下り、動作が開始されるのですが、大脳基底核が何らかの形で障害されると、基底核による調節ができなくなり、ずっとブレーキがかかりっぱなしの状態になってしまいます。
本来であれば、横断歩道を渡り始めて問題ないのですが、被殻出血でダメージを受けた方の脳全体が“休眠”している状態になっているので、正常に働いている脳と損傷を受けた脳の間でバランスの乱れが生じます。
健側の脳は通常通り活動して脚を一歩踏み出せるのに、麻痺側の脚が出てこない。
これは、被殻出血の片麻痺の方に良く見られる光景です。
トーンが変化するよう上下肢に介入する
こうした身体の不具合を修正し、トーン・筋緊張が変化できるようにするためには、きちんと麻痺側の上下肢にアプローチするのが大切だと考えています。
臨床現場では、「鏡を見ながらリハビリ」をするケースもあるようですが、マヒや痙縮、低緊張などによって左右非対称になっている状態で、「鏡を見て修正して下さい」と療法士が伝えた所で、トーンが変化しないままに意識で姿勢を変えようとしても意味はありません。
お休みしているマヒ側の脳を目覚めさせるためには、基底核に働きかける必要があります。
自覚するのに分かりやすいのは手足の動きなので、繰り返しになりますが、「麻痺手麻痺にアプローチをしない」という選択肢は、僕の中にはありません。
麻痺側に介入して、「ああ自分の脚がちょっと動きそうだ」「自分の手が今ちょっと動いてるかも」といった具合に気づけて貰えたら、脳は目覚めてくれます。
そうすると、左右間の脳の機能差が小さくなり、『手の練習をしたのに、歩きやすくなった』という結果が実際に得られるのです。
具体的なリハビリ方法は、当事者の方の状況に応じて都度アイディアを練ります。
例として2025年5月13日にカラーコーンを利用した、被殻出血・右片麻痺の方への介入をショート動画にアップしています。
https://www.youtube.com/shorts/Z7fmS7nCQ0w
納得して自分で自分のマヒ手が動かせると脳が目覚める
療法士が手を変え品を変えサポートする事で、ご本人が自分で自分のマヒ手を動かせ、納得できるまで繰り返しできるようになると、脳は目覚めてきます。
痙性のために硬いままであっても、マヒ手がちょっとでも動いた!という体験が得られれば、それは大きな差を生みます。
まとめ
被殻出血例で頻繁に観察されるのが「トーン=筋緊張の変化が起こせない」という事であり、すなわち、「自分の身体が分からない」という状態です。
自分の身体が理解出来ていないのですから、「マヒ足で支えて体重を乗せたら伸ばして下さい」と療法士が伝えた所で効果はありません。
当事者の方が、ご自身の身体の存在を自覚できるようになるために、マヒ足を台の上に乗せたりしてちょっと動かしてみる。具体的な練習方法は色々ありますが、基底核に働きかけ、脳が目覚めさせるように誘導するのが大切です。
身体全体にトーンの変化が起こせると、ラクに歩きやすくなると同時に、上肢にも改善が見られます。
動画内容・チャプター
0:51 被殻出血のクライアントが多い
1:07 日本脳卒中データバンク
2:15 被殻出血と脳梗塞の回復の違い
3:20 被殻出血は後遺症が残りやすい印象
4:06 トーン=筋緊張が変化しないのが問題
4:56 安静時筋緊張が変化しない・痙縮でずっと硬い
6:25 全体の機能不全:脳浮腫・炎症
8:48 全体的な機能が落ちている時は小脳や脳幹にも影響
9:30 急性期で手足が動かないのは本当のマヒか
10:11 脳の左右間の機能差
11:22 基底核はブレーキをかけ続ける役割
13:27 非麻痺側は動き出せるのに、麻痺側の足が出ない
13:45 トーン=筋緊張が変化しない3つの要因
15:03 麻痺側の上下肢にちゃんとアプローチする
15:33 鏡だけ見るリハではトーンは変化しない
16:11 目覚めるために基底核に働きかける
17:32 マヒ手でカラーコーンを持つ練習
19:27 納得して自分で自分のマヒ手が動かせると脳が目覚める
20:28 トーンの変化が起こせない:自分の身体が分からない
21:11 「マヒ側の手足に触らない」という選択肢は無い
24:18 今日の結論