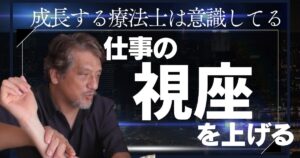【脳卒中片麻痺】 しびれと痛みの違いを解説:痛みに対する過敏さを緩和する股関節と肩のストレッチ
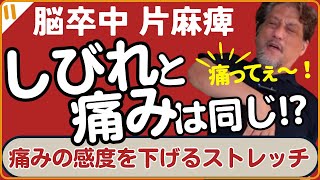
こんにちは!Will Laboの山田です。
今日はしびれと痛みについてを解説しつつ、痛みをどういうふうに緩和したらいいかのやり方について、皆さんにお伝えしようと思います。
目次
痺れは視床出血由来?
先日、僕のYouTubeにて、視床通や痺れが強いという視床出血の方からの問い合わせにお答えをしました。しびれは、「中枢神経の脳入ってきた感覚を処理できなかった結果起こっているんじゃないだろうか」という一つの仮説を皆さんに提案いたしました。
引き続いて同じ方から、「しびれと痛みって同じように考えたらいいんですか」というお問い合わせがありました。
痛みについては、特に最近ちょっと片麻痺の方の痛みをもう一度考え直し、やはり筋膜の影響が大きいなと思うようになりました。
片麻痺の方で、「触られると痛い」とか「常時なんか痛くて痛くてっ!」というような方は、『筋膜の介入』で状況が変わるんじゃないかなという実感を持っているので、それについてお伝えしようと思います。
療法士は患者の訴える「痛み」に耳を傾けるべし
本題に入る前に、療法士さん医療者に是非お願いをしたい事があります。
「痛み」の感覚は、基本的には主観的な体験なんです。
主観的な体験、つまり、今現在、目の前では起こっていなくっても、目の前の方が「痛いっ!」て言われたら、そこに痛みはあるんだと理解をして下さい。
どうしても我々セラピストは科学的な立場を取るので、客観的な状況として、ただベッドに横になっているだけなのに痛みなんて起こるわけないよねとか、ほんの少しの力で触っただけなのに痛みなんか起こるわけないよねって思いがちなんですよ。
僕自身、療法士として長年自分の手を通してヒトの身体に触れているので、結構あっちこっち痛いんですよ。何のきっかけかわからないけれど、何にもしてないのに痛むことがあります。
痛みっていうのは、主観的なものです。
痛みを覚えているその人しかわからないことなので、痛みを否定をしない方が良いと個人的には考えます。
痛いと訴えた方に対して、「そうなんですね」と肯定的に向き合ってあげた方が絶対いいです。
新人セラピストの痛みに対するエピソード
もう20年ほど前の話になります。僕が勤務していた施設に1人若い女性の実習生が来ました。
実習期間、僕が担当している患者さんをその女性と一緒に診て回り、僕が指導しながらやるのですが、その際、患者さんが酷い痛みを抱えていらっしゃったんですよ。
その患者さんが実習生と何回かやり取りをしているうちに、関係ギクシャクしてきたんですね。なぜ関係がうまくいかなかったのかなと振り返った時、どうもその女性実習生は、患者が訴えた痛みに対して「いえいえ、今は何もしてないですよ、痛くないですよっ」てつい言ってしまったんですよね。
そこから実習生と患者との間で関係性が崩れてしまいました。
そうしたことがあったので、若い女性の実習生には、「患者が痛みを訴えているんだから、訴えにはちょっと耳を傾けた方が良いのじゃないだろうか」というサジェスチョンをし、実習生は受け入れてくれました。
実習生が患者に「そうなんですね、痛いんですね、大変ですね」という声掛けをして対応を変えてみたところ、案の定、セラピストに対する患者側の受け入れが非常に良くなったというエピソードがありました。
こうしたことからも、実際の臨床現場では、患者が現実的に痛みを抱えているのかどうか…はちょっと置いておいて、「痛い」と訴えられてるんだったら、何かしら痛みがあると理解をしてあげた方が、双方の関係性を考えても賢明なように思います。
感覚が鈍い状態が痺れ
さて、痺れについて深く見ていきましょう。
歯医者さんで抜歯する状況を考えてみてください。
あまりにも痛みがひどくて抜粋の為に麻酔をします。あるいは手術を受けたことがある方は、麻酔をすると感覚なくなっていく経験はされていると思います。
麻酔の後、徐々に感覚が戻ってくると、最初はしびれ感として戻ってきますよね。
正座をして、立ち上がろうとした途端、足しびれて動けない事も多いです。
ねってなりますよね。あれも言っときどこか結果を潰してしまったり神経を圧迫してしまって、その神経の流れがうまく届かなくなったおかげで、感覚が鈍くなっている状態がしびれなわけですよ。
このように「しびれ」という感覚があるんじゃなくて、「訳がわからない感覚のこと」をどうも僕たちは痺れとして感じているようだなというのが僕の考察でした。
痛みは侵害刺激(しんがいしげき)
ところが「痛み」に関しては、確実に「侵害刺激」です。侵害刺激とは、ヒトの身体に何か悪影響が及ぶような刺激が入ってきたから気をつけろよっていう注意機構なわけです。
痛みが末梢神経由来かどうかは議論の余地がありますが、僕個人はほぼ末梢神経だと思っています。それと同時に、痛みは「侵害刺激」なんだということをちゃんと頭に置いておく必要があると思います。
結論として、痛みは「筋筋膜症候群」の可能性が高いというのが、最近の僕の見解です。
脳卒中片麻痺の方では、特に麻痺側を中心とした痛みが結構あります。「片手症候群」というものです。
療法士さんが軽く触れただけも「痛い」と騒ぐような方いらっしゃいますよね。
こういう状況の時、「痛みに対して過敏になっている」と理解をします。その過敏性は単に心理的な過敏性ではなくて、現実的に筋膜が張ってるんだと見ています。
筋膜へのアプローチ
「筋膜」というのは、皮膚の下にあります。
皮膚と筋肉の間には膜の層があり、何層かに分かれています。
筋膜があるお陰で、隣り合っている筋肉と筋肉を別々に動かすことができるんですね。
例えば、親指を曲げる筋肉と人差し指を曲げる筋肉が同時に働いてしまったら、親指を曲げようとして人差し指も曲がってしまいます。
片麻痺の方で親指と人差し指の両方が同時に曲がってしまう方がいます。
筋膜が癒着して、親指を曲げる筋肉と人差し指を曲げる筋肉が一緒に働いてしまう、筋の硬さがあるということですよね。
筋膜は、筋肉を覆っている膜で、筋肉と筋肉を分けながら、筋肉がそれぞれ別個に動くよう「滑走性:を持っています。
この「滑走性」が枯渇してしまうと、筋肉が引っ付いて癒着してしまう。癒着してしまう状態になると、ふと動いた時に問題が出るケースがあります。
僕が自宅でリラックスしてテレビを見ながら、突然の痛みに襲われるとき…
恐らく、高級とか心臓の拍動とか、血流血液の流れによる振動で何か変な刺激が、患部ないしは周辺に起こっていると僕は理解をしています。
傍から見れば、僕がリラックスしているように見えたとしても、実際にはヒトの身体は動いています。呼吸によって動くとか、ちょっとした音の刺激にふっと首を向けただけでもこれ動きますよね。
こういう細かい動きによって、遠い部分の筋膜の癒着がキュッと引っ張られると、痛みに感じるんだという事です。
従って、痛みは「筋筋膜症候群」として考えた方が良いというのが僕の結論です。
痛みを「筋筋膜症候群」として捉えると、絶対この痛みは取れるというのに行きつきます。
視床由来の痛みを訴える方はいます。視床の出血や視床に拘束があるせいで、違和感や痛みを訴えられる方はいます。
少なくとも僕は、瞬間的にではあるけれど、その日、あるいは1日2日ではある程度改善されるのは、臨床経験上実感としてずっと持っています。
痛みが永続的に消失するかどうかについては、視床がどの程度回復してくるかによって変わるので、永続的に痛みがなくなるかどうかは保証はできません。
しかし、少なくとも、筋筋膜に介入し、滑走性を良くすることで、その瞬間あるいは1日2日は痛みなく楽に過ごせるという方は多いです。
ということで、「筋筋膜症候群」として考えた方が良いなという事を一つ提案として皆さんにお伝えしておきます。
感覚の話 身体へのアラート
しびれと痛みを巡る考察の中で、「感覚」とは何かを考えてみます。
「感覚」は個体の生存を助けるためにあるものです。
個体の生存というのは、1人の人間、山田稔という人間が生きながらえていくために、身体を傷つけてしまったり、障害してしまうような刺激に対して「ちょっと危ないぞ、気を付けろ」と注意喚起するシステムです。
危険だから気を付けてね…という「侵害刺激(しんがいしげき)」に対し、「侵害受容器」が発火するとそれが痛みとして脳に伝わる仕組みです。
基本的には、侵害刺激=悪影響が及びそうな時に、「痛み」として感じるのです。
。片麻痺の方の痛みは、侵害刺激からの痛みを感じ過ぎてしまうのが問題なのではと考えています。
先にも触れたように、痛みは個体を守るために備わっている機能なので、痛みを感じなくなら問題です。
しかし、痛みに敏感になり過ぎて動けなかったり、痛みを感じ過ぎて安眠できなかったり、落ち着いて生活ができなければ、「問題」と捉えるべきです。
「痛みに対する感度を下げる」必要があるわけです。
痛みに対する感度を下げる2つのポイント
- 痛みに対する感度を下げるために、筋筋膜の滑走性を取り戻す
- ストレッチをすること
僕はもう還暦を過ぎているので加齢に伴う体力的な側面もあります。
昔より体力が落ちたり、活動に伴う痛みが生じる時もあります。
一方で、少し掘り下げてみると、関節の動きを邪魔してしまう筋筋膜の癒着がどこかにある為に、体が引っ張られる。だから、それ以上動かすとダメ、それ以上動かすやヤバいという「侵害受容器」が働いて痛みであったり、しんどいという感情になる。
それを自分自身で修正するのには、股関節周囲をきちんとストレッチするとすごく軽くなるような気がしています。
ストレッチは少々辛いけど効果あり
このストレッチをしてる時は辛いんですよ。
やり始めて1日2日は、ずっとビリビリと皮膚が擦り切れたような感じます。
擦過傷(さっかしょう)と言われる、擦り傷ができたような感覚が生じます。
そういう多少の辛さはあれど、今からご紹介するストレッチやっていると、やはり身体の動きは良くなるので、筋筋膜のストレッチ方法を皆さんにお伝え致します。
因みに、筋膜については最近いろんな研究がされており、ストレッチよりも、温熱とスピード効果で、温熱によって細かくゆするような動きが筋筋膜には良いと言われています。
近年では整体やリラクゼーションでも筋膜にフォーカスした施術が提供されていますが、職人技なので、動かないポイントをピンポイントで当てられる経験豊富な人じゃないと難しい面はあるような気がしています。
ストレッチ実践
今まで「痺れと痛み」について僕の考察を述べてきました。
簡潔に言うと、僕らの関節で感じてる痛みは、別の筋膜の癒着によって生じている事が非常に多いので多いので、ストレッチが良い解決策だと思っています。
実際のストレッチ
実際のストレッチの方法は、動画でご紹介していますので、そちらをご覧ください。
該当する場面に飛びます。
17:44~ 痛みに対する過剰な感度を下げる股関節・大腿直筋ストレッチ
22:23~ 肩のストレッチ
ストレッチをするときのコツ
痛みに対する過敏さを緩和する股関節と肩のストレッチ」を実践するさいのコツは、グイグイするのではなく、痛いとところを探したら、「その痛みが散るまで」というのを目安にすると良いと思います。
痛みはなくなるわけではないので、散る、収まる、なだまる…レベルを目指すのがアリかなと思います。
しびれと痛みの違いに対するまとめ
ストレッチ動画、如何でしたでしたでしょうか?
山田先生は健康体で麻痺もなく、普通に動けるからできるんだろう!」と言われそうですが、確かにそうです。
片麻痺の方で、手足がうまく動かない方が、動画と同じことをやれと言われたらできないかもしれない。
しかし、少なくとも視床だけの障害であれば、手足の髄性は残っているはずです。
残っている随意性を使って、動画のストレッチのように身体全体や背中の筋膜をずっと緩めてみるのはアリだなと思います。
その際のコツとして2点あげましたが、やはりじっくり・じわじわやることです。
僕たち結果を出したい余りに焦って短気な面が出ることがあります。
結果を早く求めたいので、たくさんやる、強くやる、早くやれば良い結果に繋がると理解しがちですが、それはあり得ません。なぜなら、長年かけてちょっとずつ悪くなってきたものを一瞬にして良いものへと変化させることはできないからです。
そういう意味で、じっくりじっくりと、辛い辛いと言いながらも、自分でゆっくりストレッチをすると結構楽になったりします。
股関節周りや大腿直筋をストレッチでしっかり伸ばしておくと、やった感覚の痛みは残っているけれども、体の動きそのものは軽いなっていう感じがするはずです。
片麻痺の方でもそうした実感を持たれている方が多いので、痛みはそんな風に対応していく。あるいは、担当している療法士が痛みの要因である、「筋筋膜の癒着」をうまく剥がしてあげられたら良いように思います。
動画内容・チャプター
1:37 療法士は患者の訴える「痛み」に真摯に向き合って
3:14 一人の実習生の失敗と成長
5:40 痛みは侵害刺激(しんがいしげき)
6:45 痺れとは感覚が鈍くなっている状態
7:37 痛みは筋筋膜症候群の可能性が高い
10:56 筋筋膜に介入・滑走性を良くすると数日痛みは消える
17:44 痛みに対する過剰な感度を下げる股関節・大腿直筋ストレッチ
22:23 肩のストレッチ
24:51 コツはじっくり・ジワジワやる