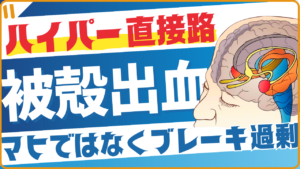【片麻痺者が動けないのはなぜ?番外編3】脳卒中エビデンス鵜呑みは危険!誰のためにどう利用する?脳機能は未だにナゾだらけ
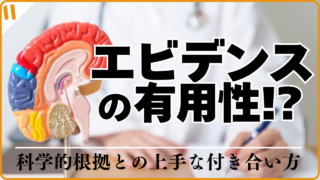
今日は脳卒中の「エビデンス」について考えてみたいと思います。
結論としては、科学的エビデンスを鵜呑みにせず、自分の中で根拠や裏付けとなるデータを判断できるようになる事が重要です。
目次
CI療法と川平法
脳卒中のリハビリにはいくつか手法や方法論がある事は、皆さんもご存知かと思います。
川平法(促通反復療法)、CI療法、認知運動療法、タナベメソッド、ボバース、PNF(固有受容器神経筋促通術)、電気刺激療法etc…
動画内で川平法とCI療法のエビデンスレベルについて触れていますが、2025年現在は下記となっています。
川平法
・脳卒中治療ガイドライン 2015:
グレードB 推奨する
・脳卒中治療ガイドライン 2021:
促通手技を反復する訓練が, 軽度から中等度の上肢麻痺を改善させることがRCT で報告されている。末梢への振動刺激,…. しかしながらこれらの療法については未だ文献数が少なく, システマテイクレビューなどによる検証が十分になされていない
引用リンク:https://x.gd/BOcJU
CI療法と修正CI療法
・米国脳卒中学会のガイドライン
エビデンスレベルⅡ、推奨度A
・脳卒中治療ガイドライン 2021
推奨度A エビデンスレベル高
エビデンスにまつわる諸々…
以前から僕が手に取っている書籍や、最近視聴している動画に「エビデンスとは何か?」を考えさせるものがいくつかあります。
また、精神疾患に対して「ロボトミー手術」というのがあり、頭蓋骨に穴を開け、脳の前頭葉の一部を切除する行為が行われていた過去があります。これは「人類最悪の手術、呪われた手術」とも言われています。
一連のエピソードに加え、普段の僕のリハビリでの臨床活動を踏まえつつ、「科学的なデータを鵜呑みにしてはいけない」という見解を述べたいと思います。
確立されたエビデンスは存在しない
前回の動画で、「被殻出血の動きづらさは麻痺ではなく、大脳基底核がブレーキをかけているせいだ」というお話をしました。
視聴者の方からは、様々なコメントが寄せられました。
多くの方から好意的なコメントを頂くのは嬉しい事ですが、「リハビリ講座」で発信している内容はあくまでも臨床経験に基づいた知見を提案しているのであり、これが「唯一無二の正解!」では決してありません。
僕の見解に対して「腑に落ちる」と感じて下さるのは有難いですが、僕の言う事を過信し過ぎるのは危険です。
「台には麻痺側の脚から乗った方が良いのですね」と信じた方もおられたようですが、階段昇降と段差を使った麻痺脚への荷重練習は、中身が全く違うものです。
極端な事を言えば、麻痺側から乗ろうが、非麻痺側から乗ろうが自由です。
各療法士によって考え方や進め方も違うでしょう。
療法士によってリハビリの思想や哲学、実践方法の手順が異なるといった事を鑑みても、リハビリ業界では「確立されたエビデンス」というのは存在しません。
「リハビリ講座」でも、折に触れて「エビデンスはありません」と断言しています。
エビデンスとは一体なにか?
エビデンスとは「科学的な根拠を元にした確からしさ」です。
「絶対的な正解」ではなく「確からしさ」を示すために、根拠としてデータが必要になります。
動画冒頭で紹介した書籍「禍いの科学」で著者が指摘していますが、「科学的データ」とはどこまで指すのか、定義づけるのはなかなか難しいのです。
脳の機能はナゾだらけ
前回の動画で、「麻痺側の脚を台の上に乗せて、麻痺側で立つ練習をする際、お尻の所にそっと触れてあげると支える力が出てくる」という話をしました。
このメカニズムの背景として「大脳基底核に対して、感覚情報を提供しているのではないか」というのが個人的な仮説です。
脳の回路や被殻出血による症状にフォーカスして考えてみると、「大脳基底核」の他に「小脳」にアプローチしている可能性も非常に高いと感じています。
脳機能はまだまだ解明されていない事がたくさんあります。
大脳基底核の研究における第一人者でおられる彦坂興秀先生によれば、ヒトには遺伝的に備わっている運動機能があるそうです。
生得的に持っている運動機能の他に、後天的に学習する運動機能が身につき、更に成長や経験、学習を通じて獲得される日常生活動作がある。
更にこれらの上位に、脳にはシミュレーターの機能があり、僕たちは1度シミュレーションしてから、実際に行動を出力します。
脳の中では既に運動が起こっており、これがいわゆる、運動パフォーマンスを向上させる「イメージトレーニング」となりです。
イメージトレーニングでも脳の神経回路は変化するので、リハビリの手段としても一定の効果はあると考えられると思います。
ところが、「イメージトレーニング」で、当事者が具体的に何をイメージしているかなんて、誰にも分かりません。
赤ちゃんの頃から生得的に持っている足をパタパタさせる運動から始まり、成人になる過程で身に付ける重力に抗う姿勢反応や運動などに発展していくわけですが、発達や運動獲得の過程でどこの機能が高くなっているのかも、まだハッキリとした事は分かっていません。
僕たちがこんな風に自由自在に手が動かせる理由に関しても、科学的論争は絶えません。
あくまで臨床経験に基づくもの
脳卒中のリハビリに当てはめた場合、なおさら、事は複雑になります。
麻痺手を動かす練習の時に三角筋をちょっと触れてあげたり、三角筋の筋を集めたりすると、当事者の方の腕が軽く動く事を僕は知っています。
台の上に脚を乗せて、お尻に触ると足が軽くなるというのと同様に、肩回りに触ると手が軽く動くようになります。
僕は経験則としてこのような事実を何度も目の当たりにしてきましたが、科学的根拠を示すことはできません。
被殻出血の方を対象とした、母数が10万位の研究データなら、科学的根拠があると言えるかもしれませんが、山田ひとりの臨床経験ではエビデンスと言うには乏しいです。
リハビリ介入の効果判定は客観的ではない
ファンクショナルMRIという磁気共鳴画像装置で脳活動を調べる技術があります。
ファンクショナルMRIで、脳内の血流量の増減を調べている研究が幾つかあります。
例えば、歩行誘導の際、骨盤の横側をサポートして一緒に動かすと、歩行に関係する部位で血流量が増える…といったものです。
この研究は有用ですが、あくまでも実験環境下で測定されたデータに過ぎません。
現実的に、日常生活の中でも脳内の血流量が増減しているかは誰も分かりません。
言い換えれば、脳卒中の後遺症が改善されたのかどうか「効果判定」そのものも難しいのです。
僕たち療法士のリハビリ介入で、ある程度のレベルまでなら改善したという実感が沸くかもしれませんが、本当にリハビリによって脳が変化したのか、脳卒中そのものが良くなったのかは、今のところ誰も判断できないのです。
職人技はデータ化できない
僕が臨床で実践している「お尻に触れる」とか、「肩に触る」といった介入において、触り方の程度や触る面積、どういうタイミングで触り、力を加減しているかは「職人技」です。
山田が独自に身に付けたものなので、言語化するのは困難です。
講習会などで若い療法士の先生に「ここを触ってあげたら手が軽く動きますよ」とはお伝えするものの、「山田先生の言う通りに触ったけど、患者さんの手が軽くなりません」と返ってくることが大半です。
恐らく、僕は自分で気づかない所で「触る」という介入に対し、プラスアルファで何かをしているのでしょう。それは僕自身の自覚にものぼってきません。
クライアントの身体に触れながら、返って来た感覚を元に、無意識に何かを調整しているのだと思います。
脳卒中の後遺症は運動機能だけの話ではない
脳卒中片麻痺の方には、運動ができる能力が持っています。
しかし、脳卒中は運動機能だけの話では解決しません。
筋肉と関節の話だけでは済まないから、脳卒中片麻痺のリハビリは難しいのです。
たとえ、リハ室の中で小走りで動けたとしても、外の環境で、信号機を見た途端にピタッと身体が止まってしまう方もいます。
その時の気分や感情、車の騒音や周囲にどれだけ人がいるのか…
様々な要因から、動こうとした時にタイミング良く動けないという問題が出てしまいます。
運動機能とは違うレベルで、脳の中でうまく処理が行われていないのかもしれません。
論文を再現できるか?
脳卒中の後遺症に対する論文を全て疑うつもりはありません。
大切なのは、「僕たちはその論文で示された通りに再現できるか?」を考える事だと思います。
論文に書かれている事をご自身で再現してみて、再現性が確認できたら、その技術はある程度間違っていないという事になります。
「正解」ではなく、あくまでも「間違ってはいない」というレベルです。
エビデンスとは、誰がやっても同じ効果が得られるのを目指して実施されている。
言い換えれば、「注射をすれば病気が治る」というような画一的な結果を最終ゴールとして取り組まれているものと捉える事ができると思います。
どういうエビデンスに基づいて介入するか
冒頭からエビデンスを否定するような発言ばかりしてきましたが、日頃から論文や研究発表に目を通しておくのは大切です。
療法士の方は、エビデンスという言葉を鵜呑みにしない代わりに、一体どういうエビデンスに基づいて自分がリハビリ介入するのかを意識してみて下さい。
「先生は何を根拠にこのリハビリをしているのですか?」と患者さんに聞かれたら、ちゃんと答えられるように知識・倫理武装するのも必要かもしれません。
エビデンスに固執せず、臨床で場数を踏みながら、判断できるスキルを養うようにして下さい。
関連リンク
「エビデンスが重要という証拠はない」エビデンス至上主義の“落とし穴”とは?
(高島宗一郎、中室牧子、成田悠輔、宮田裕章)
YouTube:ニュースピックス
https://x.gd/PKvJ0
禍いの科学 正義が愚行に変わるとき
ポール・A・オフィット (著)
https://x.gd/76MKN
沈黙の春
レイチェル カーソン (著)
https://x.gd/N4G7f
動画内容・チャプター
0:22 脳卒中エビデンについて考えてみる
1:20 ロボトミー手術:頭蓋骨に穴を開ける精神外科手術
2:06 無農薬栽培の功罪
2:38 レイチェル・カーソン 沈黙の春
3:34 科学的データは鵜呑みにしない
4:09 山田稔は臨床経験に基づき、臨床で得た知見を提供している
4:42 階段昇降と段差を使った麻痺側への荷重練習は全く違う
5:30 山田稔の話にエビデンスはない
6:28 エビデンスとは:科学的な根拠を元にした確からしさ
6:47 科学的データの定義づけは難しい
6:57 本日のテーマ3つ
8:05 脳の機能はナゾだらけ
8:14 大脳基底核研究の第一人者:彦坂興秀先生
9:46 赤ちゃん:生まれる前からヒトに備わっている運動機能
10:56 なぜ手が動かせるかの定説はない
11:08 三角筋や殿筋を触ると動きやすくなるのは経験則から知っているが根拠は不明
12:34 ファンクショナルMRI:磁気共鳴画像装置で脳活動を調べる技術
13:54 脳卒中へのエビデンスが多いのはCI療法と川平法
14:39 死滅した脳細胞は復活しないが可塑性がある(学習する)
15:16 リハビリ介入:職人技なのでデータにならない
16:57 脳卒中の後遺症は運動機能だけの話ではない
18:15 脳卒中の初期症状と慢性期症状は異なる
20:33 脳卒中片麻痺を完全治癒するのではなく別の要素を学習する
21:03 論文を再現できるか?
22:01 脳卒中リハビリテーションにおけるエビデンス
23:00 誰がやっても同じ結果が得られるのを目指して
25:10 担当療法士は何を根拠にその介入をしてる?
25:54 鵜呑みにせず、且つ、判断できる目も持っておく