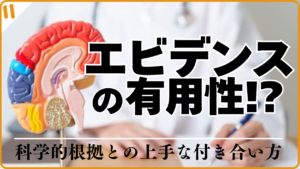【片麻痺者が動けないのはなぜ?番外編4】EBMと民間療法:"確からしさ"があるものを安全に組み合わせる・堀尾法・ボバース・無資格者と有資格者

昨今の病院リハビリではEBM(エビデンス・ベースド・メディスン)を実施することが主流になっており、病院所属のPTやOTはEBSを重要視しつつ、ドクターの指示に従ったリハビリを提供するのがコンセンサスになっているようです。
前回の動画では「脳卒中エビデンスを鵜呑みにするのは危険」という話をしました。
一方で、僕が「リハビリ講座」で発信している内容は、あくまで個人的な経験に基づいて話しているものです。30年以上の臨床経験から積み上げたデータがあるので方向性は正しいと言えますが、全てにおいて100%正しいと断言することはできません。
「エビデンス/データサイエンス」と「民間療法/代替医療」は二者択一的なものではなく、『安全性と有用性を確認しながら使いこなす』のが良いという見解を述べたいと思います。
目次
ピルクルさんから寄せられたコメント
前回アップした動画「脳卒中エビデンス鵜呑みは危険!誰のためにどう利用する?脳機能は未だにナゾだらけ」にピルクルさんからコメントを頂きました。
--------------------------------------
・ピルクルさん
エビデンスを鵜吞みにしないことを突き詰めると
無資格者による、いわゆる民間療法的な問題にぶち当たります。
この辺りは問題視されていますでしょうか?
--------------------------------------
・山田からの返答
いつもご視聴頂きありがとうございます。もっともな疑問です。
有資格者の「ホメオパシー」という医療行為について2010年に日本医師会会長が通達した文章をご紹介します。https://jams.med.or.jp/news/013.html
「会長談話」としか表現できないところが「科学的な立場に立つ」ということなんだと納得させられます。『正しいとか間違っていると100%断言できない』、ということです。
僕の見解は「科学的知見に基づいてデータを集めても誤解を信じてしまう人はいる」です。
で結論。
僕たちに出来ることは「可能な限り科学的知見に基づいたデータを収集して、それを一定の理論に引き上げる作業=ディスカッション」を継続するしかないと考えています。
被殻出血クライアントのエピソード
先日、横浜に出張リハビリに行った被殻出血の方のエピソードをご紹介します。
入院中から僕のYouTubeチャンネルをご覧頂いていた方で、回復期病院で実施されるリハビリの内容に不安や疑問を抱かれ、僕の所に依頼がありました。
片麻痺と重度の失語症をお持ちの方でしたが、案の定、「もっと回復期病院で何かできたはず」と思うような状態の方でした。
病院所属のPT/OTらの責任を問うつもりは全くなく、社会的・医療的・教育的な要因が背景に潜んでいる気がしています。
歩きましょう!が最高ランクのエビデンス
2025年現在、脳卒中リハビリで「エビデンスレベルA」など、エビデンスレベルが高いと定義づけられている方法は「歩行を沢山しましょう!」というものです。
沢山歩けばいいよと…
では、脳卒中の後遺症で歩けない人はどうしたら良いのでしょうか?
麻痺側の脚はどう使っていけば良いのでしょうか?
歩けない人は「重度のマヒ」といって片づけられてしまうのが現状です。
一般的なリハビリ病棟では、下肢の筋力強化やサーキットトレーニングが行われるケースが多いようですが、こうしたリハビリに適用しない人、実践したけど改善しない人は「重度マヒだから仕方ないよね」といなされてしまいます。
麻痺側は治らないので、健側に重きを置いて、歩行練習をしてADL(日常生活動作)の向上を目指すという流れのようです。
脳卒中片麻痺のリハは「代替療法」が大半
脳卒中リハビリにおいて、僕のように個人で開業している人達も含め、独自のサービスでやっている人達の殆どが「代替療法・民間療法」のくくりとして語られます。
僕は作業療法士として養成学校で勉強し、国家資格を取得しています。
生涯にわたって解剖学、運動学、神経学などを勉強し続けているわけですが、それにプラスして、整体やカイロプラクティック、正常運動などの知見に自分の仮説・経験を組み合わせ、その時々で最善と考えるリハビリを提供しています。
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血①】マヒが原因ではない!被殻出血はブレーキを緩めるのが重要・基底核疾患・ハイパー直接路
で紹介したのも、知識と経験の集合体と言えます。
https://x.gd/uOWUr
片麻痺者が歩けなかったり、動けなかったりするのは「重度のマヒだから…」とはぐらかすのではなく、立ち座りや台を使った練習をすれば麻痺脚でも動く!というのを体験して貰えるようにしています。
「マヒだから動かない」とあきらめてしまうのではなく、他に可能性は無いのだろうか?と常に自問自答しながら、僕は日々のリハビリと向き合っています。
色々な民間療法・代替医療
脳卒中片麻痺のリハビリに限った話ではありませんが、世の中に沢山ある健康関連の施設・手法は民間療法が殆どです。
漢方、ハーブ、鍼灸、整体、カイロプラクティック、瞑想、ヨガ、音楽療法、アーユルベーダ、中国医学、ホメオパシー、自然療法薬etc…
こうした療法を実践されている方は多いですし、実際に効果を感じている利用者の方もいると思いますが「なぜ効果があるのか」は、どれも科学的に立証されていません。
例えば、東洋医学では、経絡(けいらく)というエネルギーの流れの通路に沿って存在するツボ(経穴)を刺激することで体の調子を整えます。
しかし、経絡は解剖学的には存在しません。
一部、リンパ節や筋膜が集まっている所に近いのではないか?と推察されていますが、明確なデータは存在しません。
ですが、鍼灸治療は世界保健機関(WHO)や米国国立衛生研究所(NIH)などから、様々な症状や疾患に効果があると正式に認められています。
また、カイロプラクティックは国によっては教育機関があり、正規の医療行為として認められているので地域差もあります。
科学的データが出せず証明できないだけで、「民間療法」でも効果があるのは事実です。
脳卒中奇跡の復活「堀尾法」
脳卒中片麻痺の当事者・ご家族の方なら、「奇跡の復活: 脳卒中麻痺からの生還」という書籍についてお聞きになった事はあるかもしれません。
故堀尾憲市(ほりおけんいち)氏による書籍で、脳卒中で倒れた著者が独自のリハビリ方法で麻痺を完全克服した体験談が記されています。
賛否両論あるようですが、僕個人の意見としては、実践方法そのものはそれ程間違ったものではないと感じています。
しかし、「これをやれば片麻痺は治る!完全回復する!」と断言しているのは、若干大げさかなという印象を受けます。
加えて、「下肢装具を外しても問題ありません」とクライアントに指導するのであれば、当事者の安全を確かめた上で装具を外したり、運動学的・解剖学的な知識に則った上で、別のタイプの下肢装具を提案するなど、当事者が絶対に転倒したり、骨折したりしないような助言は必要だったと思われます。
人の誠実さとリテラシーに頼るしかない
結局、「人がやること」に100%正解は無いので、EBM(エビデンス・ベースド・メディスン)であれ、民間療法であれ、絶対はありません。
特に、日本で民間療法や代替医療と見なされている医療行為的なものを実施する場合、対象者の安全性と有効性を確認するのは必須です。
これを担保するには「人の誠実さとリテラシー」に頼るしかありません。
無資格者であれ、有資格者であれ、専門知識があるのであれば、どんな方法論でも「良くなればいいよね」と思うわけですが、それは行為を行う人の責任感や真摯な姿勢があって初めて成り立つものでしょう。
これはEBM(エビデンス・ベースド・メディスン)にも当てはまります。
エビデンスだけで成り立っている人間社会はない
世の中に「エビデンス・科学的根拠」と呼ばれるものはゴマンとあれど、人間社会はエビデンスだけで成り立ってはいません。
理屈はよく分からないけど、効果があるものも沢山存在します。
僕のリハビリもそうです。
前回お伝えしたように、麻痺手を動かす練習の時に三角筋をちょっと触れると手が軽く動くようになったり、麻痺側で立つ練習をする際に、お尻に触ると足が軽くなるというのもこれに該当します。
僕は臨床経験からこの事を知っていますが、科学的根拠やメカニズムを正確に述べることはできません。
今現在はエビデンスが確立されていないくても、将来的にエビデンスが示される療法も登場してくるでしょう。
エビデンスを過信するのは危険ですが、かといって、無資格者による民間療法に傾倒するのもリスキーです。
バランスを取りながら両者を使いこなすのが理想ですが、それには「人の誠実さとリテラシー」が大前提だという事は覚えていて欲しいです。
動画内容・チャプター
1:00 ピルクルさんからのコメント:EBMと民間療法について
1:55 被殻出血のクライアントへの訪問リハビリ
2:18 回復期病院のリハビリが正しいのか不安
3:46 脳卒中片麻痺のリハは「代替療法」が大半
5:38 病院ではエビデンスレベルが高いものが採用される
6:37 病院勤務のPT/OTはEBMと医師の指示に従ったリハしかできない
8:15 批判されがちな「ボバースコンセプト」
10:43 漢方や鍼灸も民間療法・代替医療
12:13 民間療法:科学的データが出せないだけで効果がある場合も
14:57 脳卒中 奇跡の復活「堀尾法」について(堀尾憲市)
17:11 人の誠実さとリテラシーに頼るしかない
17:17 専門知識:無資格者と有資格者
18:30 安全性と有効性を確認する
19:11 EBMも考え方は同じ
20:11 エビデンスだけで成り立っている人間社会はない