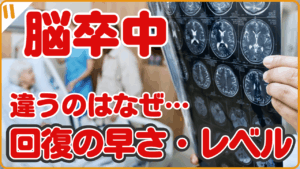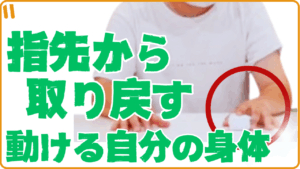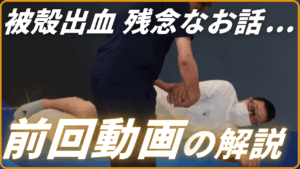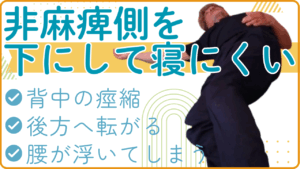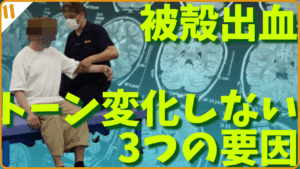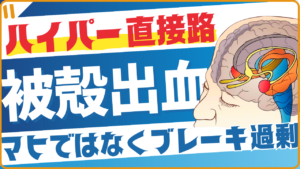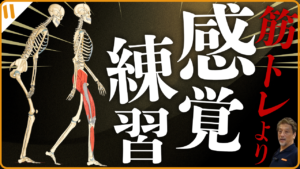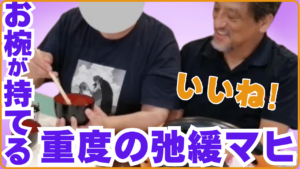【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する③】回復の早さやレベルが違うのはナゼ?学習の結果・早いうちからリハを始めても…実感としては変らない!?脳の可塑性・神経伝達物質
今日の動画では、脳卒中からの回復速度や程度が人それぞれ異なる理由について、脳の可塑性(かそせい)を踏まえて説明していきます。 シナプス・脳の可塑性(かそせい) 脳の可塑性とは、脳卒中などの病気になった後、脳が構造や機能を […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢⑧】分離運動:麻痺側上肢の回復段階・ブルンストロームステージ
前回の動画では、マヒ手を動かすための3つの達成目標として①身体化 ②分離 ③空間保持を取り上げました。そのうちの「②分離(分離運動)」について深掘りして考えてみたいと思います。 シグネ・ブルンストロ−ム著 「片麻痺の運動 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢⑤】介入場面全公開・マヒ指の練習から全身を調整する・被殻出血左片麻痺 ソムリエ石橋さん
今回は、脳出血・左片麻痺の石橋さんへの介入場面を全公開します。 石橋さんはレストランでソムリエとして復帰するためにリハビリに取り組んでおり、人差し指の練習を重点的に行っています。 「指が動く」と「体が整う」は密接な関係 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血⑧】前回介入場面の解説と残念なお話・運動主体感・遠心性コピー・身体所有感と自己と他者の区別
今日は、前回配信した40代男性 被殻出血 ソムリエの方に対する介入場面の詳しい解説をすると共に、皆さんに残念なお話をしようと思います。 いつもにも益して冒頭の前置きが長く、療法士向けの専門的な内容にも言及しますが、最後ま […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血⑦】介入場面を公開!手が動きそうな感覚・麻痺側上肢に介入する理由と実践方法
今日の動画では、麻痺側上肢に介入する動画をお届けしようと思います。 ソムリエの仕事に復帰 動画に登場頂くのは、被殻出血・左肩麻痺の若い男性で、ソムリエとして働いていらした方です。 リハビリでは、ソムリエに復帰するために必 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?回答編2】被殻出血・背中の筋の短縮と痙縮・健側を下にして横になりづらい:筋の硬さを解放する考え方
今回は「ヒロユキさん」から寄せられたご質問にお答えしながら、被殻出血の方における「背中の筋の短縮と痙縮」を中心に、筋の硬さを解放する方法について考察していきたいと思います。 脳卒中の後遺症・原因と解決法 脳卒中による後遺 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血⑤】被殻出血の後遺症が重篤になる背景・筋緊張/トーンが変化しないのが問題
今日は、被殻出血の方で「トーンが変化しないのが問題」というお題で、動きづらさの背景を探っていこうと思います。 例によって、前置きや回り道が多いですが、結論は「トーン=筋緊張が変化しない事が動きづらさの背景にあり、脳機能の […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血③】触られているのは分かるがどこを触られているのか分からない!感覚が問題・視床の体部位局在と運動の分解能
70代男性 左被殻出血・右片麻痺 失語症の方への介入もようをお届けします。 2025年4月29日に「リハビリ職人育成講座」にアップした『【新卒療法士向け ROM講座⑤】実践編:ROMの技術でどこまで改善できる?』の別場面 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血②】痙縮が問題・誤学習した歩行パターンを感覚を使って修正する・代償動作の修正介入
今日の動画では、「Let's ケーススタディ」に掲載している症例を取り上げ、誤学習した歩行パターンを感覚を使って修正する際の考え方などを解説してみようと思います。 右被殻出血・左片麻痺例 Let's ケーススタディ 症例 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血①】マヒが原因ではない!被殻出血はブレーキを緩めるのが重要・基底核疾患・ハイパー直接路
これまでシリーズとしてお送りしてきた「片麻痺者が動けないのはなぜ?」では、自動的姿勢調整や伸展反応とバランスなどの考え方に基づき、椅子や平行棒などを利用して片足立ちする練習方法をご紹介してきました。 今日はからは「被殻出 […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?⑩】ラクに歩く!最初は感覚の練習→筋肉を使う練習(14:56~)伸展反応とバランス=自動的に最適な位置に
シリーズ「片麻痺者が動けないのはなぜ?」第10回目として、今回は「片麻痺の方が自由に歩けない理由」を「伸展反応とバランス」という2つの側面に分けて解説しようと思います。 リハビリの在り方も2通りになる訳ですが、その練習が […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?④】寝起きから始まる脳の誤作動・健側の肩甲骨の過使用・麻痺側の身体が存在しない感覚で動くのが当たり前になってしまう!?
今日のテーマは「脳の誤作動とイメージ」です。 結論は『本当に障害されている機能と残されているはずの機能をきちんと見極めましょう』ということです。見極めるためには「正常運動」の知識を持っておく事も大切です。 話の流れとして […]
【片麻痺者が動けないのはなぜ?①】重度弛緩マヒと亜脱臼からお椀が持てるようになるまで
昨年からお送りしている「脳卒中の後遺症を理解する」シリーズの一環として、『片麻痺者が動けないのはナゼ?』というのを考えてみたいと思います。 第一回目は、山田が執筆した「Let's ケーススタディ 脳卒中リハビリテーション […]
【脳卒中の後遺症を理解する①】脳卒中片麻痺から完全回復したと言ってる人は自分と何が違うのか・発症の経過と障害の違い
本日から5回にわたり「脳卒中の後遺症を理解するシリーズ」として、脳卒中の病態や後遺症をどう理解すれば良いのかという概論をお伝えしていこうと思います。 解説テーマ(予定) 第1回:発症からの経過と障害の違い(本当に障害され […]